
続いて訪れたのが以前より行きたかった場所 岡崎城がある「岡崎城公園」です。岡崎城と言えば家康の生誕した地で、桶狭間の合戦での今川義元の戦死後、東に勢力を伸ばす拠点ともなった軍事的にも重要な拠城です。
2023年には、大河ドラマブームで一躍脚光を浴び多くの観光客が訪れていたようです。
岡崎城公園へは、愛知環状鉄道 中岡崎駅、名鉄 岡崎城公園前駅、東岡崎駅、よりそれぞれ徒歩で15分ほどで行く事が出来ます。

東照公産湯の井戸 竹千代君(家康の幼少名)の産湯に、この井戸の水が用いられたことから開運スポットにもなっています。


清海掘 本丸と持仏堂曲輪を隔てる大規模 な空堀で、岡崎城の最初の築城者、西 郷頼嗣の法名「清海入道」に因み「清 海堀」と呼ばれています。 二の丸から本丸大手門へのルートは 持仏堂曲輪へ入り、180 度方向転換を して清海堀に沿った幅の狭い通路(帯 曲輪)を通らなければなりません。帯 曲輪には絶えず本丸からの横矢が掛か る仕組みになっています。こうした本 丸周辺の厳重な守りは戦国時代後期に 徳川家康が築き上げた縄張りをあらわ すともいわれています。(こちらより引用(PDF))

龍城(たつき)神社 家康公生誕の朝、城楼上に雲を呼び風を招く金の龍が現れ、昇天したという伝説があり、家康公、幕末の岡崎城最後の城主であった本多氏の祖、忠勝公が祀らています。

由緒案内

竹千代君と家康公の観光用ベンチ

岡崎城 その起源は15世紀前半で、西郷頼嗣(さいごうよりつぐ)によって築城されました。1531年(享禄4年)に松平清康(徳川家康の祖父)が現在の場所へ移築し、岡崎城と称されるように。明治維新後、1873年(明治6年)から1874年(明治7年)にかけて城郭の大部分が取り壊されてしまいましたが、市民の想いによって1959年(昭和34年)に3層5階建ての天守閣が復元され、2006年(平成18年)には「日本100名城」に選定されています。
(こちらより引用)
 大河ドラマに合わせ2023年1月に、館内はリニューアルされたそうです。
大河ドラマに合わせ2023年1月に、館内はリニューアルされたそうです。
天守からの眺望 市内方面

続いて岡崎城公園内にある「三河武士のやかた家康館」へ
大河ドラマ「どうした家康」ではドラマ館として使われたそうで、今年2024年3月にリニューアルされたばかりだそうです。

こちらでは、家康公の出生から天下統一に至るまでを年代ごとに分かりやすい展示方法で紹介されていて、インタラクティブな展示も多くなかなか興味く深面白かったです。

グレート家康公「葵」武将隊の家康公がわざわざお出迎えの記念撮影に収まって頂けました。イケメンお兄さん!何でも家康公が身に着けている甲冑は紙製なんだとか。

予定ではこのあと駅に戻り名古屋への帰路に着く予定でしたが、マップを見ていて驚きの発見をしました。
※トップ写真は復元された大手門 ただしこの建っている場所は二の丸にあたるので城マニアの方には疑問視をされています。
続く




















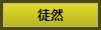



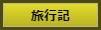
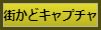

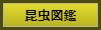


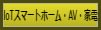

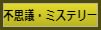
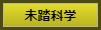
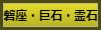


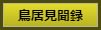
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます