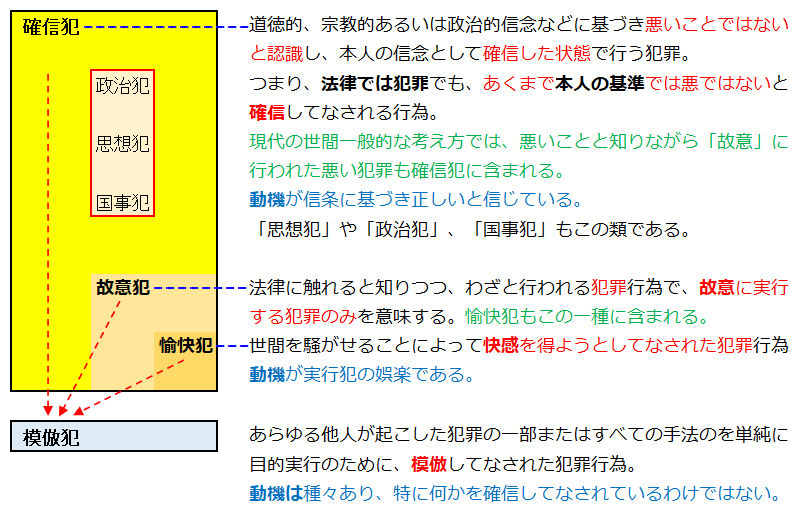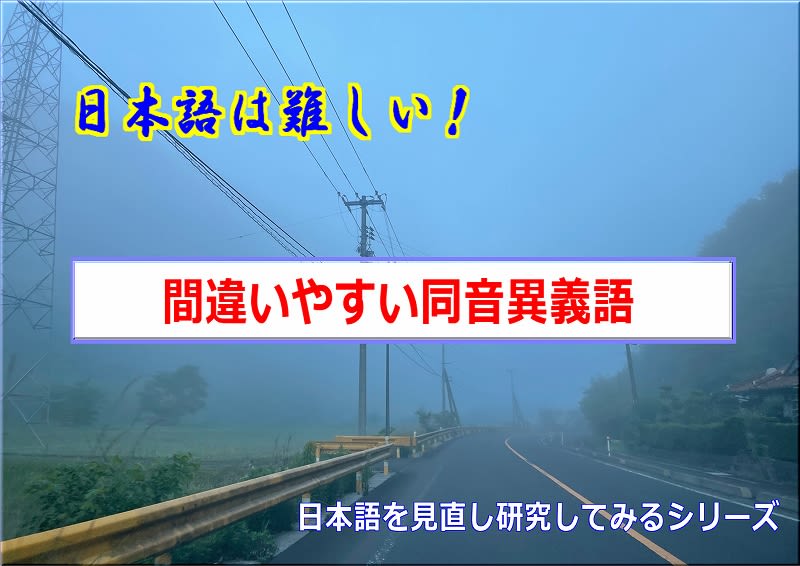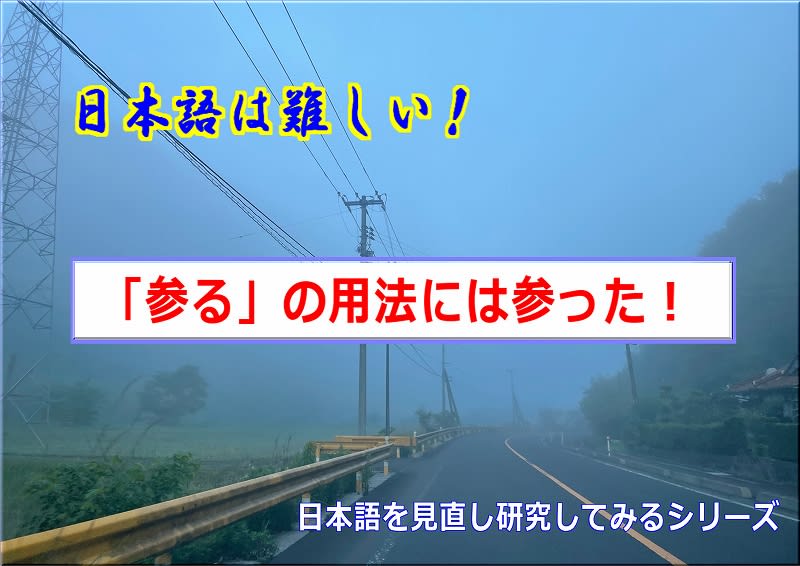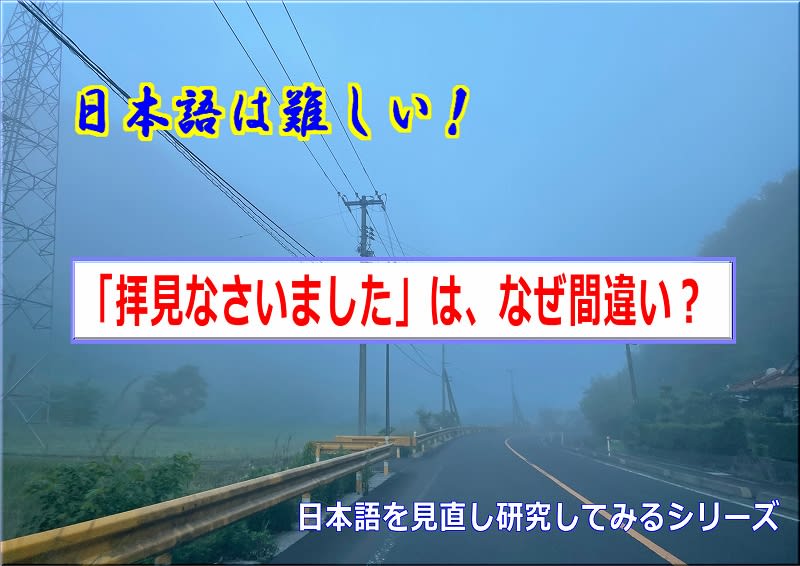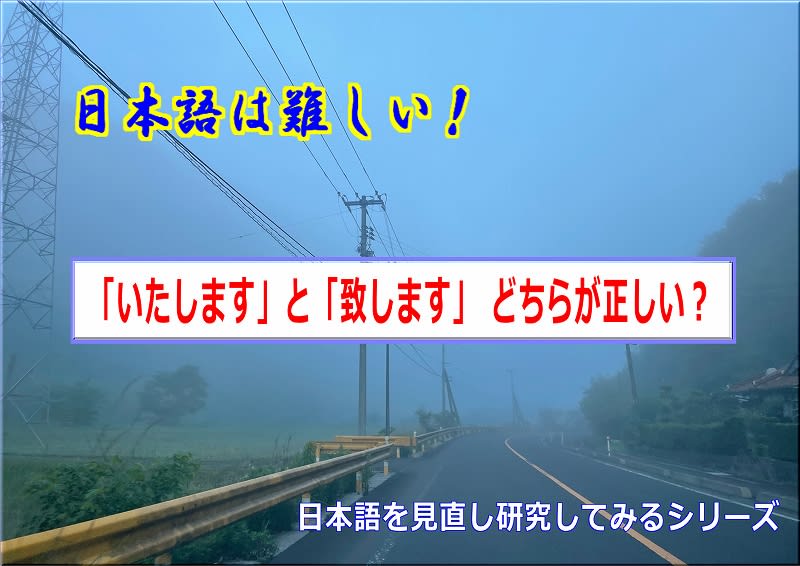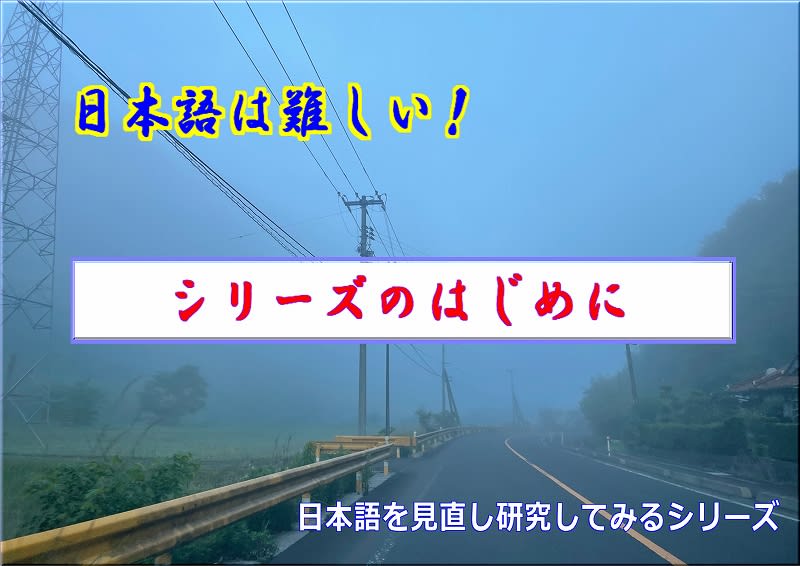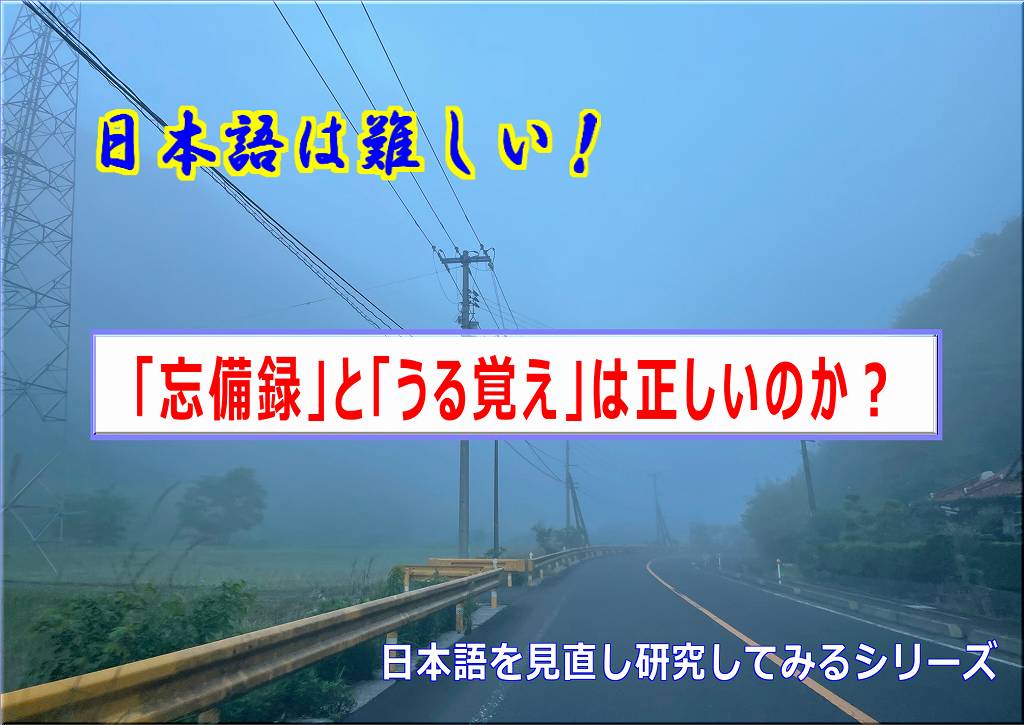
久し振りに、日本語の研究をしてみることに。
highdy も言語学者ではないので、あまり深く研究もできておらず、自分でもうっかり誤用して慌てて修正することもある。ブログの投稿も数日経って慌てて修正することは度々で、誠にお恥ずかしい次第である。
忘備録と備忘録はどちらが正しい?
本来は「備忘録」が正しく、「忘備録」は間違いである。
本来は「備忘録」が正しく、「忘備録」は間違いである。
どちらも現代では同じ意味に解釈され混同されており、辞書によっては「備忘録を忘備録ともいう」と記述されていることもある。
日本における二字熟語(和製漢語の造語法)は、ある一定のルールにより構成されており、目的語+動詞(例:備忘録)であったり、その逆の動詞+目的語(例:読書、作曲)のケースがある。その意味では必ずしも忘備録が間違いとは言い切れないが、一般的には備忘録の方が正しい。
日本における二字熟語(和製漢語の造語法)は、ある一定のルールにより構成されており、目的語+動詞(例:備忘録)であったり、その逆の動詞+目的語(例:読書、作曲)のケースがある。その意味では必ずしも忘備録が間違いとは言い切れないが、一般的には備忘録の方が正しい。
言葉は生きており、時代ともに間違いと思われていたものでも常用されて、あたかも正しい日本語のように使われている場合も多い。
とりわけ紛らわしいもの例として、「全然」がある。
例えば、「全然大丈夫です!」などと、本来は「全然」の後に打消しの言い方や否定的な意味の表現を伴って「ーー足りない、ーー読めない、ーー聞こえない」などと使われるものであった。(が正しい! highdy の時代)
highdy の時代の教育指導要領は上記の通りで、「全然大丈夫です」では笑い者にされていた。同世代の方は現代でも、8割程度は否定表現を伴って使っておられる。
しかし、いまの若い世代では、 日本に入ってきた当初の用法(字義的にはこちらが正しい)で、「完全に、全面的に、非常に、問題なく」などといった意味で、否定表現を伴わずに使っている。しかも、文部科学省までも問い合わせに対しては、後者の「肯定的な表現で使うこともある」という回答があるそうだから、間違いとは断言しづらい。
例えば、「全然大丈夫です!」などと、本来は「全然」の後に打消しの言い方や否定的な意味の表現を伴って「ーー足りない、ーー読めない、ーー聞こえない」などと使われるものであった。(が正しい! highdy の時代)
highdy の時代の教育指導要領は上記の通りで、「全然大丈夫です」では笑い者にされていた。同世代の方は現代でも、8割程度は否定表現を伴って使っておられる。
しかし、いまの若い世代では、 日本に入ってきた当初の用法(字義的にはこちらが正しい)で、「完全に、全面的に、非常に、問題なく」などといった意味で、否定表現を伴わずに使っている。しかも、文部科学省までも問い合わせに対しては、後者の「肯定的な表現で使うこともある」という回答があるそうだから、間違いとは断言しづらい。

うる覚えとうろ覚えは?
これには諸説あって、「うる覚え」は地方(茨城県だったかな?)の訛(なま)りだという人もいれば、発音しやすいからとか、語呂が良いからという説もある。
が、これにはしっかり理由があり、「うろ覚え」が正しい。
「うろ」とは、「空、虚、洞」などの字が当てられる。つまり、内部が「空」であるところ、例えば、木の「うろ」のように古い大木の幹に空いた「洞」(ほこら)のような部分を指している。
また、「胡乱」(うろん:確かでない怪しいこと)を意味したり、「胡散」(うさん:偽物っぽいこと)臭い様子などを示すことから「うろ覚え」は、不確かなことを意味している。「胡散」は怪しい、疑わしいという意味を持つが、断定できない場合には「臭い」をつけて曖昧にしている。
よって「うろ覚え」も曖昧でアテにならないことを意味している。
オマケのお話
文中に出た「茨城県」の読みも良く問題になる話で、多くの方々が間違って読んでいる。highdy も以前はそうであった。
こちらに短い記事と動画あるので、正解を確認して頂きたい。