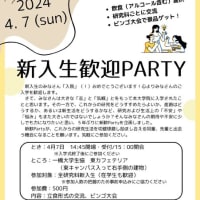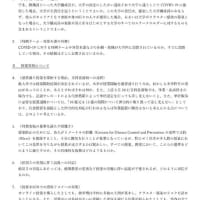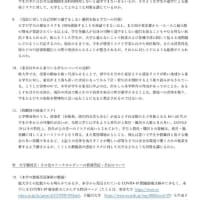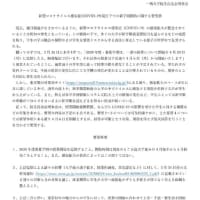三者構成自治を否定する坂内副学長の暴挙!
~5・14副学長ミーティングで抗議の声をあげよう!~(つづき)
<副学長会合問題資料集>
<資料1>
学部・院生自治会への提案とお願い
2008年3月16日
教育・学生担当副学長
坂内徳明
これまで行なわれてきた月例会合の場においては、大学が学生諸君のさまざまな意見・考え方や要望をじかに聞くことができ、一定の成果があったと考えます。この点について、これまでの努力と協力に深く感謝するものです。しかし、以下の状況と理由により、平成20年度から、新たな形態の学生との会合へ発展させたいと考えます。なお、この提案はすでに学生委員会の支持を受けております。
ご承知のとおり、平成16年度4月から全国の国立大学は法人化され、国立大学法人となりました。法人化後の多くの課題が現出する中、特に「学生支援体制をいかに充実するのか」という課題がきわめて大きなものとなったことは、本学だけでなく全旧国立大学が共通に認識していることです。なぜならば、国立大学時代の学生支援とその方向は、一言で言えば国の予算次第であり、一部民間の各種財団からの援助や、幸いなことに本学は同窓会組織の支援があったとはいえ、大学が自らの判断で学生支援のあり方を考えることはほとんどありませんでした。今後は、大学が自らの責任を果たすべく明確に意識された学生支援の方向を模索しなければなりません。そのために、本学は近年、地味ながらもいくつもの試みを行なってきたことは周知のとおりです(学生相談室・キャリア支援室への再編など学生相談体制の充実、教職員・学生へのアンケート・調査報告の「学生支援 現状と課題」、「学生生活実態調査報告書」、意見箱、学長メール、学生モニター会議の開催など)。
このような本学の現状を考えた上で、新たな会合を提案したいと考えます。すなわち、大学と学生との会合は原則的に全学生に開かれたものとし、より多くの学生の声を今後の本学の学生支援に反映し、より公正かつ効果的な支援を強化すべく今回の提案は行なわれるものです。大学はこれまで以上に前向きな姿勢でこの会合に臨むものであり、そのために学生委員会の場で議論をし、理解を得られています。
具体的には、平成20年度5月から「月例ミーティング」(仮称)を本館内の教室を使用して行なう、参加は全学生に呼びかけ、大学側は学生担当副学長、補佐、学生委員会委員数名、関連事務職員が参加、議事進行等については自治会と相談、話し合われた事項については大学ホームページに報告、といった形を考えております。
ご理解ならびにご協力をお願いします。
以上
<資料2>
院生自治会の皆様へ
本日の会合において、5月より開催する「全学生・副学長ミーティング」についての大まかな合意が得られ、有意義であったと思います。ただし、会合の基本的意義についての合意はともかく、ご提出のメモの細部に関しては、後から読み直すと意味不明の個所もあり、再度こちらの見解と方針をお伝えしておくべきと考えます。なお、以下は学生委員会の見解でもあります。
1について、会合の名称は「全学生・副学長ミーティング」とします。
2について、三者構成自治の理念の三者のうち一者は「学生」と認められますが、全学生の代表が自治会でしかないことは、現況においては認められません。全学生の代表を志向する有志団体というべきでしょう。この認識により、4にあるように「ミーティング」は全学生に出席と発言の場を提供するものなのです。
3について、「ミーティング」は1~2ヶ月に一回の予定で行う。
5はよろしいと思います。これも自治会を全学生の代表を志向する団体と当方は認めるからです。
6について、全学生との対話である「ミーティング」の実施方法は基本的に主催者側が決めます。その際、できる限り自治会の都合は尊重します。
7について、回答する必要のあるものに誠実に答えるのは当然ですが、「ミーティング」で出されるすべての要望や意見に回答する必要はありません。
今日の会合ですべてを明確にお伝えできず、誤解が生じるのではという危惧が残りましたので、今一度こちらの所見を正しく理解していただきたく、文章とした次第です。
以上
坂内徳明
2008・04・09
<資料3>
学生委員会への質問状
院生自治会 理事会
理事長
突然のことで恐縮ですが、正確なところを確認したく、本状をお送りします。院生自治会と学部自治会は、月一回、第2水曜日(教授会のある時間)に、学生担当副学長や学生担当職員との会合の場をもっています。これは、3者構成自治における重要な慣例としておこなわれているものですが、今年2月、坂内副学長より、この会合のあり方を変えたい旨、口頭で伝えられました。自治会としては、口頭ではよくわからないので文章にして欲しい旨を伝え、3月16日の副学長会合で、「学部・院生自治会への提案とお願い」という文書の提示を受けました。そこでは、「学生支援」を強化したい旨が述べられた上で、具体的な変更点として、会合の場所を副学長室から他の教室に移すこと、これまでの参加者に加えて、副学長補佐や学生委員が参加すること、全学生に参加を呼びかけること、議事進行等については自治会と相談すること、話し合われた事項について大学ホームページに掲載すること、などが述べられています。
これに対して、4月9日に行なわれた副学長会合において、院生自治会からは、いくつかの条件を提示した上で話し合い、以下の7点について、基本的に合意したものと考えていました。
1、会合の名称を「全学副学長(教育・学生担当)会合(仮)」とする。
2、会合は、三者構成自治の理念に基づいたものであり、自治会に、三者のうち学生の代表権があることを確認する。
3、開催の頻度は、月一回とする。
4、全学生に、出席と発言の権利があることを確認する。
5、司会は、大学と相談の上、自治会が行う。
6、会合のあり方を変更する場合は、大学と自治会との合意を必要とすることを確認する。
7、会合の場で出された要望や意見については、副学長は誠実に責任をもって回答する。
口頭ではありますが、以上の合意が得られたことで、自治会としては、5月からの会合のあり方の変更に、同意しました。また、細部については今後つめることとし、この合意内容について、なんらかの文書で確認することも、検討していくことになっていました。しかし、翌日になって院生自治会に、上記の合意を根本的に覆す内容の文書が、教務課を通じて副学長から伝達されました。内容は、以下の通りです。
<ここから>
〔資料2と全く同じ文面なので省略する。〕
<ここまで>
ここに至って、我々は困惑しています。特に、自治会に代表権を認めないとする点については、三者構成自治のあり方に重大な変更をもたらすものです。坂内副学長は、2月の会合においては4月から、3月の会合においては5月からの変更を主張されたのですが、なぜ、そんなに急ぐ必要があるのでしょうか。また、そもそも、なぜ今までの形の会合を変更する必要があるのでしょうか。
坂内副学長は、たびたび、この会合のあり方の変更については、学生委員会の承認を受けていると発言しています。また、上記の文章にも、明記されています。そこで、お尋ねしたいのですが、学生委員会としては、これまでの会合のあり方の、どの部分について、どのように変更するということを、承認されたのでしょうか。また、承認するさい、どのような議論をされたのでしょうか。また、5月の会合(16時開始を予定)からは、学生委員も参加するという旨、副学長より聞いていますが、教授会との関係上、責任を持って出席することは可能なのでしょうか。以上3点について、お忙しいところ恐縮ではありますが、大学自治にかかわる重要な問題ですので、お答えいただきたく思います。よろしくお願いいたします。
<資料4>
69年3.1確認書(抜粋)
・・・・・
②学生自治の原則問題に関して
(1)大学は学生の自治を分断、干渉しない。
(2)学生全体にかかわる問題の交渉権は学生の代表機関が有する。学生の代表機関以外の団体は、学生全体にかかわる問題に関する大学との交渉を行うことはできない。(この項は、「二・一二・覚書」の趣旨の再確認である。)
(3)大学は全学的な重要問題については、学内の全階層(教官、職員、院生、学生)に迅速に報告し、全学の意見に基づいてこれを解決していく姿勢をとらなければならない。院生・学生に対する報告は前期自治会執行委員会、後期学生会執行委員会及び大学院生自治会理事会を通ずるものとする。
(4)(イ)全学的問題に関しての評議会との団交は正式代表である各自治会の執行委員会が、各自治会の正式機関で決議された事項に基づき、学生・院生の参加の下に責任をもって行なう。
・・・・・
~5・14副学長ミーティングで抗議の声をあげよう!~(つづき)
<副学長会合問題資料集>
<資料1>
学部・院生自治会への提案とお願い
2008年3月16日
教育・学生担当副学長
坂内徳明
これまで行なわれてきた月例会合の場においては、大学が学生諸君のさまざまな意見・考え方や要望をじかに聞くことができ、一定の成果があったと考えます。この点について、これまでの努力と協力に深く感謝するものです。しかし、以下の状況と理由により、平成20年度から、新たな形態の学生との会合へ発展させたいと考えます。なお、この提案はすでに学生委員会の支持を受けております。
ご承知のとおり、平成16年度4月から全国の国立大学は法人化され、国立大学法人となりました。法人化後の多くの課題が現出する中、特に「学生支援体制をいかに充実するのか」という課題がきわめて大きなものとなったことは、本学だけでなく全旧国立大学が共通に認識していることです。なぜならば、国立大学時代の学生支援とその方向は、一言で言えば国の予算次第であり、一部民間の各種財団からの援助や、幸いなことに本学は同窓会組織の支援があったとはいえ、大学が自らの判断で学生支援のあり方を考えることはほとんどありませんでした。今後は、大学が自らの責任を果たすべく明確に意識された学生支援の方向を模索しなければなりません。そのために、本学は近年、地味ながらもいくつもの試みを行なってきたことは周知のとおりです(学生相談室・キャリア支援室への再編など学生相談体制の充実、教職員・学生へのアンケート・調査報告の「学生支援 現状と課題」、「学生生活実態調査報告書」、意見箱、学長メール、学生モニター会議の開催など)。
このような本学の現状を考えた上で、新たな会合を提案したいと考えます。すなわち、大学と学生との会合は原則的に全学生に開かれたものとし、より多くの学生の声を今後の本学の学生支援に反映し、より公正かつ効果的な支援を強化すべく今回の提案は行なわれるものです。大学はこれまで以上に前向きな姿勢でこの会合に臨むものであり、そのために学生委員会の場で議論をし、理解を得られています。
具体的には、平成20年度5月から「月例ミーティング」(仮称)を本館内の教室を使用して行なう、参加は全学生に呼びかけ、大学側は学生担当副学長、補佐、学生委員会委員数名、関連事務職員が参加、議事進行等については自治会と相談、話し合われた事項については大学ホームページに報告、といった形を考えております。
ご理解ならびにご協力をお願いします。
以上
<資料2>
院生自治会の皆様へ
本日の会合において、5月より開催する「全学生・副学長ミーティング」についての大まかな合意が得られ、有意義であったと思います。ただし、会合の基本的意義についての合意はともかく、ご提出のメモの細部に関しては、後から読み直すと意味不明の個所もあり、再度こちらの見解と方針をお伝えしておくべきと考えます。なお、以下は学生委員会の見解でもあります。
1について、会合の名称は「全学生・副学長ミーティング」とします。
2について、三者構成自治の理念の三者のうち一者は「学生」と認められますが、全学生の代表が自治会でしかないことは、現況においては認められません。全学生の代表を志向する有志団体というべきでしょう。この認識により、4にあるように「ミーティング」は全学生に出席と発言の場を提供するものなのです。
3について、「ミーティング」は1~2ヶ月に一回の予定で行う。
5はよろしいと思います。これも自治会を全学生の代表を志向する団体と当方は認めるからです。
6について、全学生との対話である「ミーティング」の実施方法は基本的に主催者側が決めます。その際、できる限り自治会の都合は尊重します。
7について、回答する必要のあるものに誠実に答えるのは当然ですが、「ミーティング」で出されるすべての要望や意見に回答する必要はありません。
今日の会合ですべてを明確にお伝えできず、誤解が生じるのではという危惧が残りましたので、今一度こちらの所見を正しく理解していただきたく、文章とした次第です。
以上
坂内徳明
2008・04・09
<資料3>
学生委員会への質問状
院生自治会 理事会
理事長
突然のことで恐縮ですが、正確なところを確認したく、本状をお送りします。院生自治会と学部自治会は、月一回、第2水曜日(教授会のある時間)に、学生担当副学長や学生担当職員との会合の場をもっています。これは、3者構成自治における重要な慣例としておこなわれているものですが、今年2月、坂内副学長より、この会合のあり方を変えたい旨、口頭で伝えられました。自治会としては、口頭ではよくわからないので文章にして欲しい旨を伝え、3月16日の副学長会合で、「学部・院生自治会への提案とお願い」という文書の提示を受けました。そこでは、「学生支援」を強化したい旨が述べられた上で、具体的な変更点として、会合の場所を副学長室から他の教室に移すこと、これまでの参加者に加えて、副学長補佐や学生委員が参加すること、全学生に参加を呼びかけること、議事進行等については自治会と相談すること、話し合われた事項について大学ホームページに掲載すること、などが述べられています。
これに対して、4月9日に行なわれた副学長会合において、院生自治会からは、いくつかの条件を提示した上で話し合い、以下の7点について、基本的に合意したものと考えていました。
1、会合の名称を「全学副学長(教育・学生担当)会合(仮)」とする。
2、会合は、三者構成自治の理念に基づいたものであり、自治会に、三者のうち学生の代表権があることを確認する。
3、開催の頻度は、月一回とする。
4、全学生に、出席と発言の権利があることを確認する。
5、司会は、大学と相談の上、自治会が行う。
6、会合のあり方を変更する場合は、大学と自治会との合意を必要とすることを確認する。
7、会合の場で出された要望や意見については、副学長は誠実に責任をもって回答する。
口頭ではありますが、以上の合意が得られたことで、自治会としては、5月からの会合のあり方の変更に、同意しました。また、細部については今後つめることとし、この合意内容について、なんらかの文書で確認することも、検討していくことになっていました。しかし、翌日になって院生自治会に、上記の合意を根本的に覆す内容の文書が、教務課を通じて副学長から伝達されました。内容は、以下の通りです。
<ここから>
〔資料2と全く同じ文面なので省略する。〕
<ここまで>
ここに至って、我々は困惑しています。特に、自治会に代表権を認めないとする点については、三者構成自治のあり方に重大な変更をもたらすものです。坂内副学長は、2月の会合においては4月から、3月の会合においては5月からの変更を主張されたのですが、なぜ、そんなに急ぐ必要があるのでしょうか。また、そもそも、なぜ今までの形の会合を変更する必要があるのでしょうか。
坂内副学長は、たびたび、この会合のあり方の変更については、学生委員会の承認を受けていると発言しています。また、上記の文章にも、明記されています。そこで、お尋ねしたいのですが、学生委員会としては、これまでの会合のあり方の、どの部分について、どのように変更するということを、承認されたのでしょうか。また、承認するさい、どのような議論をされたのでしょうか。また、5月の会合(16時開始を予定)からは、学生委員も参加するという旨、副学長より聞いていますが、教授会との関係上、責任を持って出席することは可能なのでしょうか。以上3点について、お忙しいところ恐縮ではありますが、大学自治にかかわる重要な問題ですので、お答えいただきたく思います。よろしくお願いいたします。
<資料4>
69年3.1確認書(抜粋)
・・・・・
②学生自治の原則問題に関して
(1)大学は学生の自治を分断、干渉しない。
(2)学生全体にかかわる問題の交渉権は学生の代表機関が有する。学生の代表機関以外の団体は、学生全体にかかわる問題に関する大学との交渉を行うことはできない。(この項は、「二・一二・覚書」の趣旨の再確認である。)
(3)大学は全学的な重要問題については、学内の全階層(教官、職員、院生、学生)に迅速に報告し、全学の意見に基づいてこれを解決していく姿勢をとらなければならない。院生・学生に対する報告は前期自治会執行委員会、後期学生会執行委員会及び大学院生自治会理事会を通ずるものとする。
(4)(イ)全学的問題に関しての評議会との団交は正式代表である各自治会の執行委員会が、各自治会の正式機関で決議された事項に基づき、学生・院生の参加の下に責任をもって行なう。
・・・・・