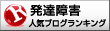母を諦め始めたのはいつ頃だったか、小学生高学年~中学生の頃にははっきり自覚というか、そうだと思わなければやりきれない出来事が多かった気がする。印象に残る出来事は「母に頼まれたレースのお買い物」買い物から帰ってきた私にかけた母の言葉が忘れられない、打ちひしがれ絶望したのだ、母を喜ばせられなかったのだ。
裁縫が得意な母は何かと小物を作成していた。(今でも印象に残るお気に入りは、紺のビロードにオレンジの丸滴型のビーズがちりばめられ、サテンのリボンで縁取りされた巾着袋だ)寒い冬の日、母の裁縫室に二人でいた、珍しく妹はいなかった。母を独り占めでき甘えることができる貴重なタイミングだった、そんな母にお使いを頼まれた、街の裁縫店へ行って「この生地に合う綺麗な白いレースを買って来て欲しい」と。
しかし住んでいた地所はバス停まで歩きで30分はかかる、しかも一日数本だ。自転車で買いに行くにしても片道1時間はかかる、しかも急坂を越えていかなくてはならない。消去法で遠回りだが急坂の無い駅近くの裁縫店に行くことにした、寒くて灰色の空、母とゆっくりしたかったが、期待に応えたかった私は奮起した。向かう道すがら笑顔になった、期待され嬉しかった審美眼を任されたのだ。お店で時間をかけて吟味した、一番綺麗なレースを選ばなくてならないのだ、母の笑顔が見たかった、母に喜ばれ感謝されたかった、期待してくれた母に応えたかったのだ。図鑑で見たお姫様の袖口の飾りのような細やかなレースを選んだ、金額や長さも考慮しなくてはならなかったが、自分としてはベストな選択ができたと満足だった「きっと喜んでくれる」と。
帰り着いた時母は怒っていた、帰宅が遅いとそしてすでに裁縫を終えたと。そうして私が買ってきたレースを見てこう言った、「こんなレース」「お母さんはこんな風に丸くてかわいいレースが欲しかったの」「こんなギザギザのレースを買ってくるなんて、あんたの心はこのレースみたいにギザギザなのね」、そう、母の作成物は出来上がっていた。納得できなかった、時間がかかるのは想定内だろうと。自転車で行って帰ってきても最速で2時間は掛かるのだから、14時なら16時に帰宅になるのは自明の理だ、暗くなるまで出歩いてと言われても、日暮れが早いにこの時期向かわせたのは母だ、私は不服が顔に出た、そんな私に母は「ふてくされた顔をして」と不満を表現したことをも責めた。
喜んでもらえると期待した分失望は深かった。善意や、母への愛情や、審美眼を否定された私はもう何でもよかった。私は母を満足させられないのだと確信したし、最大限の努力をしたつもりだったが母は喜ばないのだから無意味だったのだ、自分が空虚だった。「わぁ素敵なレースだね、寒かったでしょう、わざわざ遠くまで行ってくれてありがとうね、お姉ちゃんは流石だね、役に立つね、お母さんは嬉しいよ」そう言ってほしかった、今でもそう思っている。