指導力不足教員問題に関して、ほぼ同意見を読売の記事に見つけました。記録しておきましょう。
**********
指導力不足教員 まだまだ「氷山の一角」なのでは(読売新聞) - goo ニュース
2007年9月14日(金)01:21
この数字は「氷山の一角」に過ぎないのではないか。
都道府県などの教育委員会から指導力不足と認定された教員の数が、2004年度の566人をピークに2年連続で減少している。05年度は506人、昨年度は450人だった。
文部科学省は「認定制度が04年度までに全国の教委で整備され、その段階で指導力不足教員は、ある程度、出たのではないか」と分析する。
だが、とても楽観はできない。専門家からは「認定されるのは、ほんの一握りの教員だ」という指摘がある。
学校長の中には、教員に問題があっても本人や組合などの反発を恐れ、教委に対する指導力不足の認定申請をためらうケースもあるという。担任から外すなどして急場をしのぎ、他校への異動を待つ。これでは何の解決にもなるまい。
そもそも、「指導力不足」の定義や判定基準などが、教委ごとにまちまちだ。判定委員会の構成員も、弁護士や医師、保護者ら外部委員を入れているところがあれば、教委の関係者だけで固めているところもある。
認定数に偏りが見られるのはそのせいだろう。例えば昨年度、三重県の認定数(19人)は、教員総数が数倍の東京都、神奈川県(各14人)、大阪府(7人)などを上回っている。
文科省は、急ぎ各教委の認定基準の実態調査を始めた。来春までに、統一的な基準を示したガイドラインを作成し、公表するという。
来春から施行される改正教育公務員特例法にも新たな規定が盛り込まれる。指導力不足教員は1年間の改善研修が義務づけられる。指導力不足の認定の際や研修終了時に、専門家や保護者からも意見聴取することも必要とされた。改善不十分の判定なら「免職」となる。
これらに沿って、指導力不足教員の認定を厳密に進めるべきである。
一方で、1年間の「条件付き採用期間」(試用期間)を経て辞めていく新任教員が急増しているのも特徴だ。02年度は102人だったが、05年度209人になり、06年度は295人に達した。
病気を理由に退職を申し出る者が3分の1近くに上る。そのうちの多くは、正式採用を前に、多忙な職場環境や職責の重さに悩み、うつ状態に陥るようなケースだという。
「向いていない」の判断は早い方がいいのではないか。教職以外の道を探す本人のためにも、子どものためにもだ。
教員の質の確保のために、人事管理は厳格に行ってもらいたい。
**********
3人の小中学生の親として、見逃せない問題です。指導力不足教員に振り回された経験も一度や二度ではありません。学校長は毅然とした態度を取って指導してもらいたいのですが、その能力がない校長がいるのも事実です。
教育は、日本の未来を決めるもの。指導力にあふれた魅力ある先生ばかりになる日が来ることを望みたいものです。
**********
指導力不足教員 まだまだ「氷山の一角」なのでは(読売新聞) - goo ニュース
2007年9月14日(金)01:21
この数字は「氷山の一角」に過ぎないのではないか。
都道府県などの教育委員会から指導力不足と認定された教員の数が、2004年度の566人をピークに2年連続で減少している。05年度は506人、昨年度は450人だった。
文部科学省は「認定制度が04年度までに全国の教委で整備され、その段階で指導力不足教員は、ある程度、出たのではないか」と分析する。
だが、とても楽観はできない。専門家からは「認定されるのは、ほんの一握りの教員だ」という指摘がある。
学校長の中には、教員に問題があっても本人や組合などの反発を恐れ、教委に対する指導力不足の認定申請をためらうケースもあるという。担任から外すなどして急場をしのぎ、他校への異動を待つ。これでは何の解決にもなるまい。
そもそも、「指導力不足」の定義や判定基準などが、教委ごとにまちまちだ。判定委員会の構成員も、弁護士や医師、保護者ら外部委員を入れているところがあれば、教委の関係者だけで固めているところもある。
認定数に偏りが見られるのはそのせいだろう。例えば昨年度、三重県の認定数(19人)は、教員総数が数倍の東京都、神奈川県(各14人)、大阪府(7人)などを上回っている。
文科省は、急ぎ各教委の認定基準の実態調査を始めた。来春までに、統一的な基準を示したガイドラインを作成し、公表するという。
来春から施行される改正教育公務員特例法にも新たな規定が盛り込まれる。指導力不足教員は1年間の改善研修が義務づけられる。指導力不足の認定の際や研修終了時に、専門家や保護者からも意見聴取することも必要とされた。改善不十分の判定なら「免職」となる。
これらに沿って、指導力不足教員の認定を厳密に進めるべきである。
一方で、1年間の「条件付き採用期間」(試用期間)を経て辞めていく新任教員が急増しているのも特徴だ。02年度は102人だったが、05年度209人になり、06年度は295人に達した。
病気を理由に退職を申し出る者が3分の1近くに上る。そのうちの多くは、正式採用を前に、多忙な職場環境や職責の重さに悩み、うつ状態に陥るようなケースだという。
「向いていない」の判断は早い方がいいのではないか。教職以外の道を探す本人のためにも、子どものためにもだ。
教員の質の確保のために、人事管理は厳格に行ってもらいたい。
**********
3人の小中学生の親として、見逃せない問題です。指導力不足教員に振り回された経験も一度や二度ではありません。学校長は毅然とした態度を取って指導してもらいたいのですが、その能力がない校長がいるのも事実です。
教育は、日本の未来を決めるもの。指導力にあふれた魅力ある先生ばかりになる日が来ることを望みたいものです。













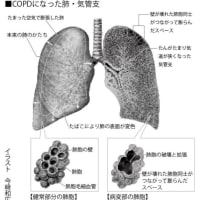
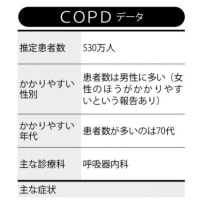




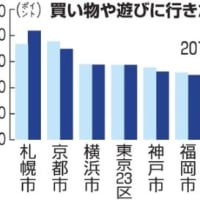





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます