全国最大級の一辺約70メートルの巨大方墳と確認 640年ごろ築造か 「舒明天皇の初葬墓の可能性強まる」樫考研
(産経新聞)
舒明(じょめい)天皇の初葬墓「滑谷岡(なめはざまのおか)陵」とされる奈良県明日香村の小山田(こやまだ)古墳(方墳、7世紀中頃)の南端部で横穴式石室の羨道(せんどう)が見つかり1日、橿原考古学研究所が発表した。これまでの調査結果と合わせ、一辺約70メートルという全国最大級の巨大方墳と判明。築造も舒明天皇崩御(ほうぎょ)の時期(641年)に近い640年ごろとわかり、橿考研は「舒明天皇の初葬墓である可能性が強まった」とみている。
羨道は古墳の南入口から石棺を置いた玄室(げんしつ)に通じる墓道で、今回見つかった羨道は幅約2・6メートル。羨道側石の基底石の抜き取り穴や、石組みの排水溝(幅約20センチ)などが確認された。
小山田古墳では平成27年1月、榛原石(はいばらいし)と呼ばれる切石で装飾された墳丘北側の基底部と、長さ約48メートル幅約7メートルの濠(ほり)跡が出土。今回の調査で古墳の南北規模が約70メートルと判明した。東西も同規模とみられるという。龍角寺(りゅうかくじ)岩屋古墳(千葉県栄町、一辺約80メートル)には及ばないが、蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳(奈良県明日香村、一辺約50メートル)や、宮内庁が管理する用明天皇陵(大阪府太子町、東西66メートル南北60メートル)などを上回り、全国最大級となる。
見つかった土器や瓦片から、橿考研は築造時期を640年ごろと推定。石舞台古墳石室(全長約19メートル)を上回る全長30メートルクラスの大石室がつくられていた可能性もある。
日本書紀によると、舒明天皇は641年に崩御。翌年、飛鳥の「滑谷岡」に埋葬され、崩御から2年後に現在の押坂陵(おしさかのみささぎ)(段ノ塚古墳、奈良県桜井市)に改葬された。菅谷文則・橿考研所長は「今回の調査で、築造年代や墳丘規模など『舒明天皇の初葬墓』説を補強する新たな材料がたくさん出てきた。舒明天皇の初葬墓であるという考えはゆるぎないものになったと思う」としている。
橿考研はこれまで「小山田遺跡」の名称を使っていたが、横穴式石室の羨道が見つかったことで古墳と断定、「小山田古墳」に改称した。遺構はすでに埋め戻されており、現地説明会は行われない。
【小山田古墳は巨大方墳】「舒明天皇初葬墓」か「蘇我蝦夷の大陵」か 研究者を二分する論争に
(産経新聞)
全国最大級の一辺約70メートルの巨大方墳と判明し、橿原考古学研究所が「舒明(じょめい)天皇の初葬墓の可能性が強まった」と発表した奈良県明日香村の小山田古墳(7世紀中頃)。ただ、当時天皇家に匹敵する力を誇った蘇我氏の根拠地だった甘樫丘(あまかしのおか)に近いため、日本書紀に登場する「蘇我蝦夷(えみし)の大陵(おおみささぎ)では」とみる研究者も依然多く、考古学者を二分する大論争になっている。橿考研は今後、石室の中心で石棺を置いた玄室の調査を進める方針で、被葬者の推定につながるか期待される。
奈良文化財研究所の職員として飛鳥・藤原宮跡の発掘調査を担当した木下正史・東京学芸大名誉教授は今回の調査を受け「舒明天皇の初葬墓」説を支持。「飛鳥最大の古墳で、推古天皇陵などより大きい。舒明天皇は、国家仏教の出発点といえる百済大寺を造営するなど、新しい政治を行った権力者。小山田古墳はそうした力を示すもので、蘇我氏がつくれる規模ではない」とする。
今尾文昭・元橿考研調査課長も「周辺では西側の谷を埋めて高い盛り土をするなどすごい造成工事をして築造している。大王家(天皇家)の力をみせようと、飛鳥の目立つ場所に造った大古墳だ」とみる。
一方、猪熊兼勝・京都橘大名誉教授は濠(ほり)の遺構が見つかった平成27年には「被葬者の第1候補は舒明天皇」としていたが、「蝦夷の大陵の可能性の方が大きい」と見解を変更。今回、蘇我氏ゆかりの豊浦(とゆら)寺(明日香村)出土の瓦と同タイプの瓦が見つかったことなどを理由にあげた。「石室は全長30メートルぐらいの規模だろう」と推理する。
白石太一郎・大阪府立近つ飛鳥博物館長は「7世紀の中ごろに飛鳥のど真ん中に墓をつくることができるのは蘇我氏の族長以外に考えられず、被葬者は蝦夷とみるのが常識的な理解」とし、「舒明天皇の初葬墓は、埋葬翌年に改葬している。あんな立派なものを造ってすぐに改葬したと考えるのは無理がある」と語る。
一貫して「蝦夷の大陵」説を唱える泉森皎・元橿考研副所長は「日本書紀が『大陵』と伝えるにふさわしい大きさだ。当時使われていた高麗尺(こまじゃく)で考えると、一辺は約200尺。ピラミッドのような段築(だんちく)構造の方墳だったと思う」としている。
蝦夷と入鹿を埋葬?
小山田古墳が「蝦夷の大陵」なら、双墓(ならびのはか)として造られた「入鹿の小陵(こみささぎ)」の有力候補は、西約150メートルに位置する菖蒲池(しょうぶいけ)古墳(方墳、一辺30メートル)。精巧で特異な石棺が2つあり、乙巳(いっし)の変(645年)で死亡した蝦夷と入鹿の2人が一緒に埋葬されたとの見方がある。
日本書紀皇極元(642)年の条には「(蝦夷が)生前に双墓を造る。一つを大陵で蝦夷の墓、一つを小陵で入鹿の墓とした」と記され、双墓がどこかは長年の議論だった。
菖蒲池古墳の横穴式石室(長さ約7メートル)には、ほぼ同じ形の2つの家形石棺が置かれている。表面に突起があり、内部に漆が塗られた特異なタイプ。蝦夷らが特別につくらせた石棺とも考えられる。
明日香村教委の相原嘉之文化財課長は「乙巳の変後、巨大すぎる蝦夷の大陵は壊され、政変で死亡した蝦夷、入鹿の2人は小陵に埋葬されたと考えられる」とする。猪熊名誉教授も「乙巳の変後は蘇我氏にとって厳しい時期で、蝦夷の墓として、あの巨大方墳は『許されない大きさ』だ」と指摘。「菖蒲池古墳石室内の奥の石棺が蝦夷、手前が入鹿だろう」とみている。
飛鳥時代最大級の方墳と判明した小山田古墳。一辺約70メートルという破格の大きさに研究者は驚きを隠さない。被葬者は初の官寺建設や遣唐使派遣などで知られる舒明(じょめい)天皇か、それとも天皇をしのぐ権勢を振るった豪族・蘇我蝦夷(そがのえみし)なのか。
飛鳥時代の大型方墳は、推古天皇陵とされる山田高塚古墳(大阪府太子町、長辺約60メートル)、石舞台古墳(明日香村、一辺約50メートル)などがある。当時の権力中枢からは離れるが、千葉県・龍角寺岩屋古墳は一辺78メートルある。
奈良県立橿原考古学研究所(橿考研)が新たに発見した石室通路(羨道(せんどう))の幅は約2・6メートルあり、石舞台古墳(2・1〜2・6メートル)に匹敵する。小山田古墳が築かれたとみられる7世紀前半について、菅谷文則所長は「他の古墳が縮小していく時代に巨大な方墳を造れたのは天皇しかいない」と指摘し、舒明天皇の初葬地説を取る。木下正史・東京学芸大名誉教授(考古学)も「大寺を造るなど国家形成の歴史の中で画期となる人物」と指摘。今尾文昭・関西大非常勤講師(同)は石室通路の石を抜き取った跡に着目して「抜き取り穴が丁寧に埋められている。改葬後にも公的管理が続いた印象がある」とし、討たれた蝦夷の墓とは考えにくいとみる。
一方、前園実知雄・奈良芸術短大教授(同)は「舒明天皇は火災で飛鳥岡本宮から別の宮へ移った後、二度と飛鳥に戻らなかった。飛鳥の中心地に墓を造るとは考えにくい」と反論し、蝦夷説を推す。日本書紀は、蝦夷が642年に自分と息子入鹿の「双墓(ならびばか)」を造り、「大陵小陵」と称したと記している。
白石太一郎・大阪府立近つ飛鳥博物館長(同)は、小山田古墳は蝦夷、入鹿父子が邸宅を建てた甘樫丘(あまかしのおか)から南方に延びる丘陵にあることを指摘。「一帯は蘇我氏の根拠地。大王墓より大きな墓となれば、7世紀の政治史を解き明かす大きなヒントになる」とする。塚口義信・堺女子短大名誉学長(日本古代史)は、古墳の盛り土から見つかった瓦の破片が、蝦夷・入鹿の邸宅と関連があるとされる甘樫丘東麓(とうろく)遺跡の出土品と同型である点に注目する。「蘇我氏に有利な資料。西隣の菖蒲池(しょうぶいけ)古墳と併せて大陵小陵と考えたい」と話す。【矢追健介、皆木成実】
…………………………
◇小山田古墳築造前後の出来事
592年推古天皇が即位
626年蘇我馬子死去
628年推古天皇死去
629年蘇我蝦夷らの後押しで舒明天皇が即位
630年舒明天皇が初の遣唐使送る
639年舒明天皇が初の官寺、百済大寺建設を命じる
641年舒明天皇死去
642年皇極天皇が即位
〃 舒明天皇を滑谷岡に葬る
〃 蝦夷が息子入鹿との双墓を造る
643年舒明天皇を押坂陵に改葬する
〃 入鹿が聖徳太子の子の山背大兄王を自害させる
644年蝦夷と入鹿が甘樫丘に邸宅を建設
645年乙巳の変で蝦夷、入鹿が滅ぶ













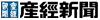


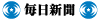




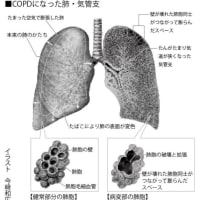
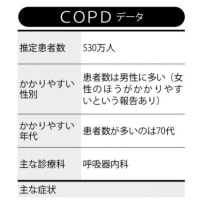




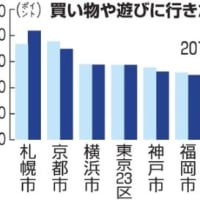





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます