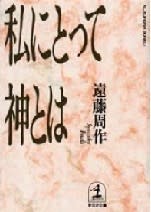『イエスの生涯』 遠藤周作著 昭和48年10月15日発行 新潮社
p105~
ナザレを去って荒涼たる丘陵地帯をイエスと残り少ない弟子は附近の村から村へと歩きつづけた。弟子たちは疲れ果て、希望を失いかけている。イエスは神をよびつづけられた。幾度も「主よ、主よ、なんぞ我を見棄てたまうや」という悲しみの声を叫ばれたが、同時に耳の底で神が自分だけに呼びかけている一つの声を聞きはじめていた。彼はその声を聞くことがどんなに辛いものかを既に感じていた。だが弟子たちは師の内面的苦闘にまだ何も気づいていなかった。
これらわずかに残った弟子の数が何人だったかは我々にはよくわからない。だがそれが福音書に記載されている12人より多少は多かったことは推理できる。なぜなら周知のようにやがてエルサレムではイスカリオテのユダが脱落するようになるし、エルサレムまでの間脱落したのはユダだけではないと思われるからだ。更にこの弟子たちの名もすべてわからない。わかっている名はペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネ。マタイ(レビ)とトマス。ピリポとバルトロマイ。アルパヨの子ヤコブとタダイ。シモンとイスカリオテのユダで、以上はマタイ福音書とマルコ福音書によるものだが、ルカ福音書ではタダイのかわりに「ヤコブの子ユダ」(イエスをやがて裏切るイスカリオテのユダとは別人)を入れている。(略)
p106~
イエスのうしろから疲れ果てた足どりで黙々と歩くこれら十数人の弟子の姿をナザレから北方に向かう淋しい丘陵地帯に思い描く時、私たちはある謎を感じる。
既にのべたようにこれらの弟子たちはユダヤの祭司階級に属する者たちでもなければ、律法学者のように学問のある人間でもなかった。またティベリヤの富裕階級にも属していなかった。イエスを知るまで彼等はイスカリオテのユダを除いてはガリラヤ湖畔の町や村に住む収税人や漁師というような中産階級の下層にある連中であって、その点、二十数年後になってポーロがコリントの原始キリスト教団について「人間的には智慧のある者は少なく、権力ある者も多くなく、身分高い者も少ない」と書いた言葉がそのまま当てはまるのである。
彼らがイエスの愛の思想を理解してその弟子になったと考えるのは間違いである。繰りかえして書いたように彼等の大部分はガリラヤ湖畔の群衆がイエスに接した時と同じような動機で弟子団に加わったにすぎぬ。素朴であるゆえに純粋なユダヤ教徒としての正義感や個人的野心や虚栄心がこの弟子たちの心になかったとは誰も言えぬ。彼らが勇気や強い意志に欠けていたことも聖書作家たちは遂にかくすことができなかった。彼等は後になって逮捕されたイエスを見棄てただけでなく、衆議会に助命を乞うて身の安全を計ったと思われるからである。その意味で彼等は私たちと同じような俗人であり、弱虫だったのだ。
彼等はイエスを誤解していた。イエスを誤解していただけではなく、彼を「神の子」と考え(p107~)てもいなかった。その彼等が多くの脱落者が出たあとも、なお、このみじめな師のあとを足をひきずりながら従いていったのはおそらくイエスの眼にいいようのない純粋さと悲しさがあったからかもしれぬ。(略)
だがそんな感情をもった彼等もやがては師を裏切るようになる。(裏切りはイスカリオテのユダだけがやったのではなく、残った弟子のすべてが行ったのだが、その点については後の章で詳述したい)いわば彼等は結局は私たちと同じように弱虫で卑怯者で駄目な連中だったのである。
その彼等がイエスの死後、突然、目覚めるのである。弱虫で卑怯者だった彼等はもう死も怖れない。肉体の恐怖に尻ごみもしない。イエスのためにひたすら苦渋の旅を忍び、ひたすら迫害に耐える。ペトロはほぼ61年頃、ローマで殉教し、アンデレはギリシャのパトラスの町で飢餓死の刑を受ける。熱心党員だったシモンもスアニルの町でイエスを説いて殺され、バルトロマイもアルバナの町で生きたまま皮をはがれ十字架にかけられたと言う。
ふしぎなこの転換と変わりようは一体、どこから来たのか。「無力なる男」イエスの彼等に与えた痕跡がそうさせたというのだろうか。私たちがもし聖書をイエス中心という普通の読みかた(p108~)をせず、弟子たちを主人公にして読むと、そのテーマはただ一つ----弱虫、卑怯者、駄目人間がどのようにして強い信仰の人たりえたかということになるのだ。そしてまた、そのふしぎな弟子たちの変りかたの原因こそ、聖書が私たちに課するテーマであり、謎とも言えるであろう。
とまれ、この年の秋、イエスと彼等とは文字通り「枕するところ」もなく南部ガリラヤ(ルカ、7の11)やツロとシドンの地方(マルコ、7の24、31)に流浪の旅を続けられたようである。彼等が旅した地名もさだかではないのはおそらくこの時期の記憶が聖書作家たちの語り部だった生存弟子たちにとって、悲しい思い出だったからであろう。イエスの内面の苦闘は弟子たちにも理解しがたかったものだろうし、イエス自身も人々に自分が知られるのを避けておられたからである(マルコ、7の36、8の26)。そして数少ない弟子たちから今日一人、明日一人と毎日、去っていったことは容易に推理できるからでもある。
p177~
この間、寝しずまった弟子たちから、「石を投げて届く」ほど離れた場所でイエスは死の不安と闘っておられた。永遠に人間の同伴者となるため、愛の神の存在証明をするために自分がもっとも惨めな形で死なねばならなかった。人間の味わうすべての悲しみと苦しみを味わわねばならなかった。もしそうでなければ、彼は人間の悲しみや苦しみをわかち合うことができぬからである。人間に向かって、ごらん、わたしがそばにいる、わたしもあなたと同じように、
(p178~)
いや、あなた以上に苦しんだのだ、と言えぬからである。人間に向かって、あなたの悲しみはわたしにはわかる、なぜならわたしもそれを味わったからと言えぬからである。
イエスは死の不安のため「汗、血のごとくしたたる」ほど苦しまれた。弟子たちに起きてくれと言いたかった。彼は一度、ペトロを起こされたが、ペトロはまた眠りこけてしまった。彼が遂に「父よ。思し召しならばこの杯を我より取り除き給え。さりながら我が心の儘にはあらずとも、思し召しのごとく成れかし」という祈りを唱えられた時、その眼に城壁にそってこちらに向かってくる炬火(※)の黙々たる火の列を見られたにちがいない。
オリーブ林のなかに侵入してきた「おびただしき人」(マルコ、14の43)のなかから、イスカリオテのユダがあらわれた。
「師(ラビ)よ。安かれ」
ユダはイエスの肩に手をかけて接吻をした。それはユダヤ人たちの挨拶のやりかただが同時に合図でもあった。人々はイエスにおどりかかった。
このイエス捕縛の場面はそれを目撃した弟子たちの記憶に生々しく残っていたにちがいないから、この記憶を基にして書かれたマルコ福音書の記述は非常にリアリティがある。弟子の一人(ヨハネ福音書ではペトロ)が剣をぬき、神殿警備員の一人の耳を切り落としたがイエスはそれを声をあげてとめられた。弟子たちは恐怖のあまり、オリーブ林のなかを逃走し、一番年下の弟子は肌にまとっていた広布を投げすてて裸のまま逃げたという。
p179~
イエスは神殿警備員たちにこう言われた。「私は毎日、神殿であなたたちに見られながら、話をしていた。だがあの時、あなたたちは私を捕えなかった」
イエスは知っておられた。衆議会が一昨日や昨日は彼を放っておいたのに、今夜、捕縛にのりだしたのは、バラバの身代わりが必要であるからだと知っておられたのである。と同時に自分がそういう事情で逮捕された以上、どんな理由をつけても有罪にされるだろう。イエスはこの瞬間から、やがて開かれる裁判の公正も信じなかったし、自分が死刑を免れるとは思われなかったのである。
炬火をかざした男たちはイエスを囲んでふたたび黒々と夜空にそびえる城壁にむかって戻っていった。あっけないほどの逮捕だった。誰一人として男たちに囲まれたイエスを助けにくる者はいなかった。天幕をはった巡礼客たちはもう眠りこけており、このゲッセマネの騒ぎに気づかなかったようである。気づいたとしても彼等はもう自分たちの期待を裏切ったこの痩せた、くたびれた男を助けようなどは思わなかったであろう。
オリーブ林のなかを四散した弟子たちはまだ恐怖にかられていた。彼等はイエスが何も手を出さず、従順に引かれていったのにも驚いたが、それよりも自分たちが今危険な状態にあることに気づき、恐怖のあまり、どうしてよいかわからなかった。夜があければ衆議会は自分たちをイエスの一味として探しまわるにちがいない。彼等はそれが怖ろしかったのである。
こうしたイエス捕縛後の弟子の心理を考えると、我々は有名なカヤパ官邸でのペトロの否認(p180~)の話は事実をふくみながら、実はもっと別の背景があることに気づかざるをえない。
その点については後でまた詳述する。ここでは四散した弟子たちが協議した結果、ペトロが代表者となって、大祭司カヤパを知っている者を仲介人として自分たちの助命を願い出たのだと言っておこう。もちろん、これは私だけの仮定だが、しかしこの弟子たちの心理とその後の彼等の行動をみて、彼等が衆議会から「追求されなかった」ことは疑いない。そこに弟子たちと衆議会のある取引のあったことが想像できるのである。
だからペトロたちはイエスを見棄てただけではない。はっきり言えば、ユダと同様に裏切ったのである。イエスを否定し、イエスとは今後関係しないことを衆議会の議長であり大祭司であるカヤパに約束したのである。その約束のかわり、弟子たちは逮捕をまぬがれた。それが私の考えである。
弟子たちはそのような弱虫だった。弱虫だったからこそ、彼等はこの取引をしたあと自責と屈辱のため、烈しく泣いた。ペトロがカヤパの官邸でイエスを否認して、烈しく泣いたという話は、弟子全体のこの時の自責感を象徴しているのだ。(このイエスの否認の場面は福音書のなかで最も古いマルコ福音書が一番なまなましく描いている。他の福音書はマルコ福音書以後に書かれたため、ペトロの指導者としての権威を重んじるべく、なまなましい記述は避けるに至った)
ぐうたらな弟子たち、弱虫の弟子たち。我々と同じように卑怯で卑劣だった弟子たち。(p181~)しかしその弟子たちがやがて殉教も辞さぬ強固なグループと変わっていく。それはなぜだったのか。聖書のテーマの一つはそこにあるのだ。
※ 炬火(きょか)=たいまつ。かがり火。トーチ。
p249~
だが、我々はふたたび謎に捕らえられる。私が先に書いたような弟子たちの後悔、自分たちをゆるしてくれたイエスへの感動と思慕、そういう心理だけでは、彼等といえどもその後半生の生涯をささげあらゆる苦難にうちかって布教に努めることはできなかった筈である。弟子たちのような弱者はこうした心理を持っていても、それをいつまでも持続できなかったであろう。時間は往々にして我々の感動を色褪せさせ、はじめの決意を忘れさせるものだ。イエスの死から生じた感動、驚愕、思慕だけでは彼等の生涯はあれほど支配されなかったと考えるほうがより正確である。
と、するならば彼等には別の次元から何か筆舌では言えぬ衝撃的な出来事が起こったと考えるより仕方がない。それでなければ、彼等は「無力なるイエス」をたんに有徳の人、愛の人と思いつづけるだけで「神の子(キリスト)」という形で神格化しなかった筈だからだ。他の預言者たちや教団の指導者たちはそれぞれ、その死後もその弟子に慕われてはいるが、イエスのように神格化はされなかった。クムラン教団の信徒たちはエルサレム主流派に迫害を受けた自分たちの大いなる師「義の教師」の再来を信じてはいたが、義の教師を神格化はしなかった。ヨハネ教団の(p250~)弟子たちはヘロデ・アンテパスに殺害された洗礼者ヨハネをいつまでも崇めたが、その復活を信じなかった。人々はむしろ生きているイエスに洗礼者ヨハネの姿を見つけたのである。
すると何故、イエスのみ原始キリスト教団のなかで神格化されたのか。たしかにイエスは現代の多くの聖書学者の言うようにその死後、弟子たちの信仰(ケリユグマ)によって神格化されたのは事実だが、問題はそこにあるのではなく「何故弟子たちはイエスを神の子として信仰するようになったのか」にあるのである。
復活について書いた最も古い証言は聖書ではなく聖ポーロの書簡であるが、しかしそれだからと言って聖書の記述がポーロのものより事実がうすいとは言えない。我々はむしろポーロやこの聖書に書かれたイエス復活についてのみなぎるような自信のほうに、まず圧倒されるのだ。イエス生涯の奇蹟については聖書は復活よりも弱々しい記述をしている。それは聖書作家たちが各地に生じたイエス奇蹟物語の民話を集めておりこんだにすぎぬからである。だが復活についてはちがう。最もふるいマルコの筆致はその薄気味悪さをリアリティをもって記述しているし、他の福音書は自信をこめてそれを強調しているのである。
「ところでキリストは死者の中から甦られとのべ伝えられているのに、死者の復活はないとあなた方の中に言っている人がいるのはどうしてなのか。・・・・キリストが甦らなかったとすれば、われわれの宣教も空しく、あなたがたの信仰も空しいであろう。さらにわれわれは神についての偽証人となるであろう。・・・・われわれは神はキリストを甦らせたと神に逆らって証言し(p251~)たことになる」(コリント前書、15)
この絶対的な自信、動くことのない確信は何よりも私たちを圧倒してしまう。どこからこの自信と確信は生まれたのか。もしそれが事実でないとするならば・・・
p252~
(略)
空虚の墓の事件が仮に創作だとしても、我々はさきほど言及した謎を考える時、この事件と同程度のショックが別の形で弟子たちに加えられたことを認めざるをえない。少なくともそれによって弟子たちの心に「無力なるイエス」が「力あるイエス」に変わるような出来事があったと推理せざるをえない。そしてその出来事ゆえにイエスの復活が事実として弟子たちに掴めたと思わざるをえない。
* 遠藤周作著『私にとって神とは』---聖書はイエスの生涯をありのまま、忠実に書いているわけではない---原始キリスト教団(書き手)によって素材を変容させ創作した