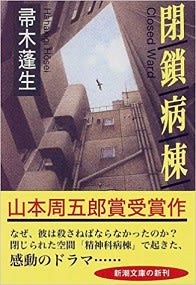
『閉鎖病棟』帚木 蓬生 (著)
とある精神科病棟。重い過去を引きずり、家族や世間から疎まれ遠ざけられながらも、明るく生きようとする患者たち。その日常を破ったのは、ある殺人事件だった……。彼を犯行へと駆り立てたものは何か? その理由を知る者たちは――。現役精神科医の作者が、病院の内部を患者の視点から描く。淡々としつつ優しさに溢れる語り口、感涙を誘う結末が絶賛を浴びた。山本周五郎賞受賞作。
帚木蓬生著『閉鎖病棟』新潮文庫
平成 9年(1997年)5月 1日 発行
平成29年(2017年)6月20日 69刷
p100~
「ほんにここにこげんやって居(お)るのが夢のごたる。本来なら、あたしはこげんなことを楽しめる身の上じゃなかとに」
秀丸さんがしみじみ梅の枝を見上げて口走る。
「みんな、ありがとう」
秀丸さんはぺこりとお辞儀をし、もう一度梅の花を見回した。目が赤かった。島崎さんが秀丸さんの横顔をじっと見守る。秀丸さんの言った言葉の意味が摑めないのだ。秀丸さんが昔刑務所にいたことは聞いているが、てんかんのもうろう状態のなかで、母親を含めて4人を殺したことはまだ知らない。
秀丸さんが板前をしていた21か2の頃で、そのため死刑の判決を受けた。拘置所に15年とどめおかれ死刑を執行された。しかしよほど首筋が頑丈だったのか停止位置が低すぎたのか、絶命をせずに息を吹き返した。そのあと風呂敷包みひとつで拘置所の門から放り出された。死刑は2度執行することはできないという理由からだ。
「戸籍上、もう梶木秀丸という人間はこの世に存在しないものだからな」と、刑務官は言った。
---吹き抜けのがらんとした部屋で目隠しばされ、頭を輪の中に入れたとたん、時間の進むのが遅くなってしもうた。足許の床が開いて落ちていく途中でおふくろの姿(p101~)ば見たと。呼んだのは子供の頃の自分で、母親は麦畑で身体(からだ)を半分おこしてこっちば眺めとる。陽よけの帽子と手ぬぐいで顔ばおおい、白い歯が見えとった。青々とした麦畑じゃった。そんとき、身体がひきちぎられるような音がして意識がなくなったと。
気がついたのは医務室のベッドで、顔見知りの医師が真っ青な顔をしてのぞきこんでいた。
首から下の感覚が薄く、手足が棒のように重かった。
「助かったよ」
医師はうわずった調子で告げ、ぶつぶつひとり言をいいながら書類に何か書き込み、刑務官に渡した。秀丸さんが拘置所を出たのはそれから3時間後だ。
塀の外には刑務官たちの官舎が並び、松林の向こうは海だった。秀丸さんは、松の根っこに腰かけてこれから先どうするかを考えた。何かの間違いのような気がした。とりあえず、痺れた身体を休めるために、風呂敷包みを枕にして仰向けになった。
36歳で突如としてこの世に生まれてきたも同然だった。死刑囚として毎朝覚悟の上で生きていた頃は、死を絆にしてまがりなりにも世間と繋がっていた。世間が自分を見張り、こちらもいつ襲いかかられてもいいように身構えていた。いま、あれだけ悔いた過去も死刑執行で帳消しになった。新たに自分の名前をどうつけようと勝手(p102~)だった。正真正銘の自由だ。急におかしさがこみあげてきて秀丸さんは声を出して笑った。しかし笑ったあと気持が凍りついた。自由とはいえ、自分は名も知らない草木の1本、地面を這う虫に等しかった。
秀丸さんは駅で残飯をあさって何日間かしのいだ。新しく出来た浮浪者仲間に誘われて土建屋の下で働くようになった。ところが3ヵ月もしないうちに工事現場で何度も倒れた。てんかん発作は20歳からの持病で、拘置所にいるときも欠かさず医務官から薬を貰っていた。秀丸さんは発作の再発で監督者からやっかい者扱いにされ、自分でもすっかり自身をなくした。また風呂敷包みひとつでたこ部屋を出、以前通っていた病院を訪ねて行った。病院は2代目が跡を継いでいたが、70過ぎの先代院長は秀丸さんを覚えてくれていただけでなく、犯行も判決も知っていた。
秀丸さんは車庫横の小使い部屋に住まわせてもらった。院長の車を洗ったり庭木を剪定したり、台風で吹き飛んだ屋根を修理したり、何でも屋の働き者だった。しかし5年後、梯子が倒れて6メートルの高さから落ち腰骨を折った。手術は1回で済まなかった。長年服用していた薬の副作用で骨がもろくなっており、もと通りにはならない。半年で整形外科医院から帰ってきたときは、杖をついて歩くのがやっとこさになっていた。以来、入院患者としてチューさんたちの仲間入りをしたのだ。
................
〈来栖の独白 2019.2.17 Sun〉
帚木蓬生さんの『閉鎖病棟』を読むようになって、今日で何日目だろうか。私の裡で深い満足と懐かしさがある。満足とは精神科医の書く小説の確かさであり、懐かしさとは加賀乙彦さんの『宣告』以来、実に数十年を経て読む死刑囚関連の内容である。無論、『閉鎖病棟』は精神病院に入院している人たちを描いたものであり、死刑囚(だったの)は秀丸さん一人にすぎない。
秀丸さんは死刑囚だったが、死刑執行が未遂に終り、解放されて社会へ出てきた。
日本で死刑執行が完遂されなかった場合、この秀丸さんのように解放されるのかどうか、私には分からない。大塚公子著『死刑執行人の苦悩』には、以下のような顛末が綴られている。
通常ならば、平均14分あまりで心音が停止し執行終了ということになる。けれどもこのときは大いにちがっていた。
死刑囚がもがき苦しみつづける。ロープが正しく首を絞めていないのだ。革の部分から頬を伝って、後頭部の中央あたりに鉄かんが至っている。これでは吊るされた瞬間に失神するというわけにはいかない。意識を失うことなく、地獄の痛苦に身もだえすることになる。止むなく死刑囚の体を床に下ろし、24、5貫もある屈強な刑務官が柔道の絞め技でとどめをさして執行を終わらせた。
死んでこそ死刑囚という考え方があるそうだが、殺してこそ執行官とでもいうところだろうか。
秀丸さんの場合と違い、何としても死刑を完遂しなければならないとの鉄則の下、刑務官が死刑囚の首を絞めて殺している。
――――――――――――――――――――――――
◇ 《死刑とは何か~刑場の周縁から》 加賀乙彦著『宣告』『死刑囚の記録』 大塚公子著『死刑執行人の苦悩』
-----------------
◇ 加賀乙彦著『宣告』1979年2月20日発行 新潮社
--------------
◇ 桜ばな いのちいっぱいに咲くからに いのちをかけて わが眺めたり / 『宣告』 / 『勝田清孝の真実』
..........











