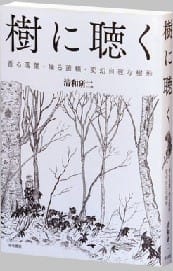
【書く人】
人間の思慮の浅さ『樹に聴く香る落ち葉・操る菌類・変幻自在な樹形』 東北大大学院教授・清和(せいわ)研二さん(65)
2020年1月5日 中日新聞朝刊

北海道の原生的な森や東北の奥山を歩き、樹木の生態や森の仕組みを調べる研究者が、「木がもし言葉を話したら今、何を言いたいのだろう」という気持ちで書いた。
ケヤキ、カツラ、ブナ、コナラ…、日本全国の落葉広葉樹林で見られる十二種の植物が、どうやって子孫をつないでいるか、その「生活史」をまず記す。
種の散布が巧妙だ。ネズミなどの動物に運んでもらったり、風で飛ばされたり。川辺に多いサワグルミは種に翼がついていて、川に落下し水で遠くへ運ばれる。著者らの調査では、雪解けによる増水で土手の高い所に押し上げられるほど、よく発芽し成長していた。
また、発芽は種の大きさによって光か温度か、どちらに促されるかが変わる。芽が小ぶりな小さな種は土中の浅い所に届いた光に、地中深くから芽を伸ばせる大きな種は温度に反応する。良い条件が整わなければ、種は地中で眠っている。「すべて親が種に仕込んだこと。うまく子が育てば親もほっとするだろう」と、木を人のように語る。
森でさまざまな種類の木々が共存する仕組みにも触れた。特に近年の研究の中でも関心の高い、地中で植物の成長を助ける「菌根菌(きんこんきん)」という菌の働きも解説した。
「それぞれの木は、子どもを大きく育てようと結構利己的。けれども、森林全体で見ると、そうしたセルフィッシュな面を抑えるシステムがあるように思う」と見る。「一種だけがはびこらず、他の種に譲ったり、台風や大水、洪水、山火事といった大きな自然の営為によってリセットされたり。地中には病原菌も菌根菌もいる。いろんなかかわりがあって森はやっとできあがっている」
森や木のことをよく知ってほしいと、観察した樹形や枝、葉などを精緻に描いたイラストも盛り込んだ。
ふだんは森に通い、苔(こけ)むした大きな倒木があると、思わず寝転がって眠ってしまい、学生に起こされることもあるそうだ。最近の気掛かりは、相次ぐ大規模なバイオマス発電所の建設。山の木が燃料にねらわれている。
「奇跡のような確率で育った巨木をいとも簡単に切ってきた過去を、また繰り返そうとしている。なんと思慮が浅いことか。森で老木を見ていると、『おまえ、ちゃんと言えよ』と言われている気分になるんです」。築地書館・二六四〇円。 (鈴木久美子)
◎上記事は[中日新聞]からの書き写し(=来栖)
................
〈来栖の独白 2020.1.5 Sun〉
>相次ぐ大規模なバイオマス発電所の建設。山の木が燃料にねらわれている。
>奇跡のような確率で育った巨木をいとも簡単に切ってきた過去を、また繰り返そうとしている。なんと思慮が浅いことか。
人類の浅慮が、尊い地球を滅ぼそうとしている。酸素をくれる樹木。地球存続のためには、人類の絶滅しかない。人類がいなくなれば、地上の樹木も罪のない生きものも、生存できる。
――――――
* アマゾンで起きている大規模火災の根源にある問題は森林伐採だ 2019/8/28

-------------------
* 「地球の肺」に最悪危機=アマゾン熱帯雨林で大火災-ブラジル 2019/8/25

--------
* ETV特集「巨樹の声が聴きたい 倉本聰と千年の命」 NHK 2019.11.2









