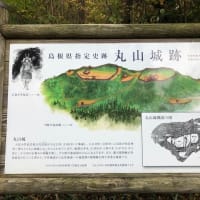57.石見の戦国時代の幕開け(続き)
57.3.邑智郡の形勢
57.3.1.高橋氏
康安元年/正平16年(1361年)、高橋貞光(師光の子)は出羽実祐の拠る二つ山城(邑智郡邑南町鱒渕)を攻略した。
と、「足利直冬その後」の項で、邑智郡阿須那に地盤を築いた高橋師光について述べた。

その後、貞光の孫久光は出羽本城に移居し、ここを根拠地として、四方に勢力を拡大していった。
既述したが、文明9年(1477年)頃に京極持清から尼子清定に送った書状が有る
今度國之時儀無注進候之間、無心元之由候、去八日狀到來候、委細令披見候、仍合戰之時儀忠節無極候、別紙ニ進狀候、隨而面々威狀事、任注文遣候、能々可有保美候、猶々當城事可然樣可有成敗候、佐波高橋御暇申時分候、風度下向候者可被申談候、憐國奉公方々可有力之由被成御奉書候、定不可有如在候、返々在庄之時儀心安候、一向憑入候、恐々謹言、
五月廿二日 生 觀 花押
尼子形部少輔殿
今度国の儀注進無く候ひし間、心もとなき由に候ひしが、去る八日状到来候ひて委細披見せしめ候、仍ち合戦の時儀忠節極まりなく候、別紙に状進らせ候に随って面々感状のこと、注文に任せ遣はし候、よくよく褒美あるべく候、猶々当城の事然るべきよう成敗あるべく候、佐波・高橋御暇申す時分に候、きっと下向候はば申談せらるべく候、隣国奉公の方々、あるべきの由御教書なされ候、全く加在あるべからず候、返すがえす在庄の時儀心安く候、一向に憑み入り候
この書状で
「佐波・高橋も京都勤務が終るので帰国したら、よく 相談して万事手落ちのないよう領国を固めてくれ」
と書いている。
これは、当時佐波・高橋の所領が出雲にあったことを示しており、なをかつ京極・尼子氏の信頼を受けていたことを示している。
高橋氏の勢力が格段に伸張したのは、この久光の時代であるある。
久光の妻は小笠原長直の娘であり、伯母は吉見頼弘に嫁しており、子の清光の嫁は安芸三人(広島市安佐北区可部町)の高松城主熊谷膳直の娘である。
ことに久光が、公方より屋形号を賜はっていることは、高橋氏にとって重要なことである。
室町時代には大名屋形の称号がないと、家臣に烏帽子・直垂・ 素袍を着せることができなかったので、諸豪族は争ってこれを望んだという。
高橋系図の乏しい記録の中に屋形を賜わったことを書き残しているだけに、それは高橋氏の名誉として語り伝えられたものであり、久光一代の政治的地位の拡大と、富力の豊かさを築き上げた事実を証するものである。
かくて、久光は応仁の乱を機に出羽の本城に拠って、安芸・備後・石見・出雲に散在する広範な領地に一族郎党を配置するに至った。
従って応仁の乱における出征軍は、安芸・備後・石見 出雲の各地域から責任者に軍兵を添えて東上させていたはずであり、久光自身は出羽本城にあってそれぞれ指令を発するとともに、上記の各地域ごとに自領の防衛と中央の勝元党からの指令に応じての活動を続けていたのである。
57.3.2.犬伏山の大蛇
広島県安芸高田市美土里町に犬伏山がある。
昔から「妖怪多き恐ろしき山」という秘めた伝説も残され、北面にある犬伏福王寺を取りまく伝説や、蛇切谷伝説、鰻沼伝説、妖怪変化伝説などがある。
この山に住んでいた大蛇を高橋氏の家来が討ち取った、という伝説が邑智郡美郷町にある。
討ち取ったのは、都賀西にあった丁城(よぼろじょう)の城主高橋肥前守の小姓である松原千代坊師という若者である、という話である。
伝説では城主は高橋備前守と伝わっているが、石見高橋氏の系図で、備前守の称号をもった人物は見当たらない。
ただ前述の高橋久光の称号は備中守であり、ひょっとしたら称号が間違って伝わっており、当時の城主は前述の高橋久光(1460~1521年)だったのかもしれない、と思うのである。
高橋氏は観応元年/正平5年(1350年)の青杉城(邑智郡美郷町)の攻防で佐波顕連を討った恩賞で、邑智郡阿須那三千貫を与えられ、備中から邑智郡阿須那に居住している。

大蛇退治の千代坊(島根県口碑伝説集より)
昔邑智郡都賀西よほろ城主高橋備前守の小姓、三十六人のうちに、 松原千代坊師と云ふものがあつた。
當時犬伏山に大蛇が住んで居て、人を害すること屢(しばしば)であつた。
或時小姓の連中が、控室で雑談中、談話はいつしか此問題となった。
「誰か行きて退治するものは無いか」と云ふ事になったが、偖(さ)ていざとなると、誰も返事するものが無い、千代坊師は其時十八歳であつたが、「大蛇龍神と雖も万物の霊長たる人間に敵すべきことあらんや、不肖なから馳向つて大蛇の患害を除きませう」と云つた。
三十五人の面々は、冷笑を面に浮めた。
「首尾よく大蛇を征伐したら我々の大刀を残らず進呈しやう」と云つた。
直ちに用意して、只一人犬伏山に向った。
山の向合と云ふ所に老人が夫婦居た。
立寄って水を一杯下さいと云った。
老人夫婦は、千代坊師が「これから犬伏山へ越すのである」と云ふを聞いて、愕然たる色を示した。
「これから 一里ばかり奥に、椿の木があります、其上に大蛇が住んで居て、夜な夜な笹原を谷へ落ちて来る、其跡は大船を引いたやうになつて居るといひます、是迄夜分をかけて通り越さうとしたものは、何れも行え不明となりました。悪いことは申しませぬ、是非思ひ止まりなされ」と云った。
千代坊師は勿論覺悟の前である。今更引返すべくもない、彼れは奮然として山深く分け入った。
老人の言つた如く、果して椿の大木があつた。彼れは件の木に寄つて、じっと待って居た。
夜半頃に至ると、果して峰の方から、鹿笛を吹くやうな聲がすると一面の熊笹原を大木を曳くやうに、大蛇が落ちて来た。
千代坊師は二尺三寸の大業物を抜き放って真二つに斬った、そして用意の煉薬を腰筒の水で呑み、氣力を整へた。
暫くすると、また再び大なる震動と共に更に大蛇が落ちて来た。
これは曩(さき)に斬った大蛇の配遇なる、雌蛇であつたのである。
千代坊師は勇を振って再び、之を斬殺した。
しかしながら彼れは全く一身ぐだぐだになった。
大樹のもとに横はつて困臥するばかりであつた。
さて夜が明けて、山麓の老人は其安否を気遣つて、山に登って来た。
そして、此様子を見て、殆んど自らを失はんとした、やゝあつて、千代坊師を背負って山を下り、茶粥など薦めて懇に介抱した。
直ちに都賀西よほろ城へ此事を注進した。
城主は大に驚き、多人数乗物を遣し城へ連れて帰った。
城主は三十五人を残らす閉門仰付けて、大小は悉く千代坊師へ渡された。
それより千代坊師は暇を乞ひ、都賀東金東寺で剃髪し、法名を教雲と改め、三尊の彌陀に給仕して、心を澄まして 簗瀬村に来り、神田に住居した。禅宗妻帯で、代々血脈を相承した。
(以上邑智郡吾郷村簗瀬尾原徳三郎氏系譜より抜粋す)
千代坊の妻某がある時、石室内で子を抱き休憩中、小さな蛇が来た。
之を捕へて紙に包み噛殺して後ろの竹藪に捨てた。依つて之を蛇捨藪を云つた。
翌朝見ると大きな蛇の死體が藪に横はってて居た。
之を背負うて江川へ捨てた。
流れて少し下の瀬にかゝつた、江川を舟で上下するものは、之を見て唾を吐いた。
依つて此瀬を唾が瀬と云った。
蛇捨藪は最早開墾して、桑畑となったけれども、唾が瀬は今尚つばきと云って現存して居る。
( 吾郷村乙原尋常小學校報)
57.3.3.小笠原氏と佐波氏の戦い
当時、邇摩郡には福屋氏の一族が拡がっていた。
兼継を祖とする福光氏、兼綱を祖とする横道氏、兼保を祖とする井田氏などである。
安濃郡の鳥井は福屋兼広の所領である。
その他吉河・小笠原・佐波・周布・出羽の諸氏の領地が錯綜していた。
南北朝時代から著しくなった分家が本家から独立する傾向は応仁の乱からいっそう激しくなってくるのである。
出羽氏一族の所領は邑智郡の君谷・祖式・高原・出羽の一部、邇摩郡の湯里、安濃郡の波根・富山などに拡っていたが、すでにかなり一族各家の独立が進んでおり、出羽氏の惣領は君谷を中心に出羽の一部に縮少していたようである。
出羽氏にとってより重大な問題は、小笠原・佐波両氏の江川周辺での抗争の渦中に入ったことである。
小笠原は蒙古襲来以後、 邑智郡村の郷に来住、南北朝時代にかけて都賀・都賀行方面、川本方面、高原方面に領地を拡大、川本温湯城に移ってから井原・日和・長谷方面、川下・三谷・三原 ・祖式・君谷から摩郡宅野方面に勢力の伸張を図っていた。
他方、佐波氏は最初の来住地矢飼ヶ城時代に吾郷・粕渕・浜原・都賀行・谷方面に地歩を固め、青杉城時代に沢谷・赤名・来島方面に進出するとともに君谷から安濃・邇摩両郡へ勢力圏を拡大、祖式・三谷・川下方面へも食指を動かしていた。
しかし、正平五年の青杉落城を契機に佐波氏の勢力は大きく後退した。
また、康安元年/正平16年(1361年)、高橋貞光により二つ山が落城させられてから、出羽氏も弱体化し後退した。
この両氏が、弱体化した分小笠原氏が伸張して来ていたのである。
古来江川沿岸は対外貿易という特殊な利益を得られ交通の要路としても重要な地域であった。
ところが、川越の田津は土屋氏に、君谷の湊は出羽氏に掌握されていた。
一方永享年間(1429〜1441年)に銅が丸の鉱山(邑智郡美郷町乙原)が開発されたことによって、佐波・小笠原両氏の領境争奪は熾烈となっていった。
応仁の乱が勃発すると佐波・出羽氏は東軍に属し、小笠原氏は西軍に党することになった。
そのため、京都の争乱が地方に拡大されることによって佐波・小笠原の領境争奪に都合のよい理由が与えられたのである。
それが文明8年(1476年)の衝突となり、出羽は佐波に協力することとなったのである。
今度、石州に於いて河本下総守御敵同意の輩を引卒し佐波兵部少輔秀連と合戦に及びし処、秀連に合力致せし旨注進到来、尤も神妙、弥忠節致さるべきの由仰せ下さるる所なり、仍って執件の如し、
文明八・三・一八、加賀守・美濃守より出羽掃部助へ

河本下総守とは小笠原長正のことである。
この時期の小笠原家当主は第9代小笠原長弘であり、長正は第10代当主である。
史料によると、佐波氏と小笠原氏は三度戦っている。
文明2年(1470年)、文明8年(1476年)、明応9年(1500年)であり、戦場は君谷・竹の周辺としている。
伝えられるこの、君谷合戦・竹合戦の話は、両者の抗争が多年にわたったものであり、佐波の失地回復を目的とする攻撃と、これを迎え撃つ小笠原の防衛といったものであった。
そして佐波の失地回復は目的を達せず、出羽氏とともに後退を余儀なくされ、君谷・吾郷は小笠原の確保するところとなったようである。
<続く>