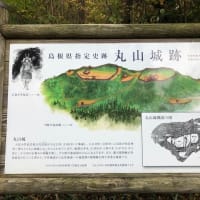戦国の石見−4(続き−3)
61.3.広瀬富田城攻め(続き)
61.3.5.毛利元就の帰陣
一方毛利元就は吉田の本拠郡山城に、様々な困難に遭い帰陣している。
元就父子は5月7日、八幡山宮尾の陣を徹し、星上山の峠を越えて岩坂道、熊野路を経て大庭に向った。
しかし尼子勢の追撃は激しく数名の部将を失い、やっと虎口を脱した。
元就はこの撤退戦に奮戦して軍功あり、として井上興右衛門、赤川又五郎、井上大蔵左衛門尉、三戸五郎左衛門尉、内藤六郎右衛門等に感状を出している。
毛利家等の資料によると
元就たちは、8日、古志後浜(出雲神門町)を経て石見に入り降露坂(大田市温泉津町)に着くと、尼子方の追撃はますます急激となった。
ここでも数名の部将を失い、渡辺太郎左衛門は元就の甲冑を着けて身代りとなって討死し、元就は その隙に遁れ、九死に一生を得て、 波根(大田市)まで引返えし満蓮社(長福寺)に数日滞在し、波根泰連の支援を得て邑智郡三原に出て、小笠原長徳のもてなしを受け、無事吉田に帰り得た。
降露坂の戦いの年代疑義
降露坂に戦いは天文12年と記されているが、これは永禄3年(1560年)の間違いと言う人も
いる。
毛利家資料によると、元就は安芸の吉田郡山城へ帰るとき降露坂で尼子方から攻撃を受けて、およそ20Km近く後戻りして波根に行ったことになる。
しかし、吉田に帰る経路は、波根ー大森ー水上ー祖式ー三原ー川本と行くのが普通である。
そして、険しい山々が連なる降露坂を経て祖式ー三原と行くと20Kmちかくの迂回路となる。
だから、あり得ないのではないことというのである。
そして降露坂の戦は永禄3年(1560年)に毛利元就が山吹き城を攻めた時に起こった戦いであるという。
この話は、後述する。
陰徳太平記
陰徳太平では、降露坂についての言及はないが、広瀬からの退却時に波根の満連社に45日間逗留したと記述している。
元就は羽根の満連社に四五日逗留して落散たれし軍勢を待揃給けるに、彼住職元就を生末は中国の大将に成給へきと見たりけん。
矢違の守り数代持伝えたりとて進らせければ、元就老僧の志の程を感悦し給禄など賜りけり。
又波根、小笠原なども、道中の兵糧など送りけるとかや。
さて諸士其追々集りければ、やがて江の川を渡り、芸州吉田に至て帰り給う。
<毛利元就 退却経路>

三休上人
前述の陰徳太平記のいう僧侶は三休上人だった。
隠匿太平記では老僧と書いているが、当時三休上人は26歳で、元就は47歳であった。
三休上人は幼名を乙寿丸といい、永正15年(1518年)4月15日に、波根の旭山城の城内で生まれた。
7歳のとき旭山城で開かれた5月5日の菖蒲の礼式の日に、そのころのしきたりで、長兄の長保が上座に坐り、乙寿丸ははるかな末座に坐った。
乙寿丸は介添えの家臣に「なぜ自分は下の方に坐るのか、どうしたら兄のように上座に坐れるようになるだろうか」
と矢つぎ早やに問いかけた。
返事に困った家臣は「学業を深め、出家になれば、自分たちの一門どころか、天下の武将の上座に坐ることができましょう」と教えた。
乙寿丸はこのとき以来、仏門に入ろうと考えはじめたという。
父の元保に仏門に入りたいと懇願を続け、元保の紹介で京へのぼることになり、母の橘は、ひきとめたが、旅立ちした。
このとき乙寿丸は15歳だった。
そのころ知られた高僧、京都の清浄華院26世、寿光上人のカミソリで頭を丸めた。
修行のかいがあって23歳のとき、寺院建立の資格を許す天皇の綸旨をうけることができた。
おそらくこのときから三休と名乗るようになったと思われる。
三休という名には、どんな意味がひそんでいるだろうか。
仏の教えでは三つの休みとは、心を休め、身体を休め、そして死んだのちに永劫の休息を得るということをいうが、これを意識して名付けたかどうか分からない。
あるいは天・地・人の安らぎという創造の意味をあらわしたものか。
三休上人の母、橘は、上人が綸旨をもらう一年前に38歳の若さで死ぬが、母の死が望郷の思いをかりたてたのだろう、故郷の波根に帰り、満蓮社と呼ぶ小庵を建てて住むようになった。
天文12年5月8日に、元就と三休はここ満蓮社で出会ったのである。
三休上人の卓見
石見の辺地の漁村に、新しい京文化とすぐれた宗教的 識見をもつ若い僧がいるのに、元就は驚かされる。 元就 は自分より二十歳も若い三休上人の下座に坐り「老僧」と敬称で呼んだ。
元就は自分の武運について祈願してもらった。
そして、三休上人は「あなたは中国路の総大将になられる方だ」とも予言した。
また戦場で敵の矢が当たらない、武運長久の「矢違いのお守り」を贈ったという。
元就は満蓮社で三休上人の励ましをうけ、勇気づけられ、兵をまとめて江の川をさかのぼり安芸・吉田郡山城へ引揚げたという。
その後、三休上人は永禄元年(1558年)41歳で、 清浄華院、第二十八世の候補となり、紫衣をうけ、翌年清浄華院の住職になった。
<清浄華院(京都市上京区)>

永禄8年3月、富永山城守は、禅寺だった長福寺を、浄土宗に改め、本堂などを建て、寺領として十石を贈り、三休上人の帰郷を促した。
翌年の8月、三休上人は清浄華院を隠居して波根に帰り、無住だった長福寺の開山となった。
その後、尼子を破った毛利元就は永禄10年、出雲大社に参拝のあと、3月26日に長福寺に立ちよって、24年ぶりに上人と再会をする。
ときに元就は71歳、上人は50歳であった。
元就は「上人の啓示と、それに対する心構えのアドバイスで、 現在の私がある。矢違いのお守りで、たびたびの戦いでも難を免れることができたし、私はただただ驚いている」 と感謝し、寺領として八町四方と自分の着ていた陣羽織をぬいで贈ったという。
61.3.6.尼子の挽回と石見の形勢
天文12年大内軍撤退は中国の形勢を転換せしめ再び尼子氏の勢力を振張するに至った。
陰徳太平記の巻14「尼子晴久石州発向之事」に
去る程に大内義朝臣、雲州富田表の合戦勝利を失ひて敗北し給ひけれは、尼子晴久を始め一族家人諸士百姓迄勇み悅ふこと限りなし。
やがて晴久より今度大内一味の儀を変して尼子へ帰服したる吉川、三澤、三刀屋、宮、杉原、本庄等の人々へ義隆敗走せられし事、偏へに各味方に興みせられしに依る所と共功の大なる事を慇懃に礼謝せられて馬太刀等種々の引出物なと贈られけり。
其後晴久、尼子紀伊守、同式部太輔、同左衛門太夫、同孫四郎、其外亀井、牛尾、 佐世、卯山、川副の者共を召し集め、今度大内勢敗軍せこと各々身命を軽んし忠孝を被励し故也。
然れは今勝に乗りて石見、備後、両国へ出張し、降る者をは人質堅く取って、重ねて志を変せざる行をなし戦ふ者をは城を陥れ頭を刎ね、愛和を先にし威刑を後にせは、両国の武士は云ふに及はず、士民等に至る迄悉く靡き従ふ可し。
石備事なく切り随へなば、其れより復た芸州へ押入りて、一年利を失ひつる鬱憤を散し、会稽の恥を雪(そそ)ぐ可しと思は若何にと有りけれは、各々異議に及はす尤もとそ同しける。
とあり、近来萎縮退嬰の境にある尼子氏をして俄に起ちて旗鼓堂々藝備石伯作攻略の師(軍)を起さしめ其の勢力を振起せしめた。
石見の攻略 青杉城攻め、銀山を手中
天文12年7月3日晴久は二万余を以って石見に入った。
14日、秋上三郎左衛門、立原備前守、森脇長門守等一千余騎にて先鋒となり民家を焼き久利城に迫った。
城主の久利清六兵衛、同左馬之助のひきいる三百崎が必死に戦ったが、援軍もなく、力を失い大内氏を頼って落ちのびた。
尼子晴久はさんざん久利城を破壊して、次に邑智郡に入り佐波隆連が守る木積の青杉城(三高城)に迫った。
青杉城は標高410mの急峻な山城で、 邑智郡浜原にある。
北・東・西は江川が大きくUターンし、南側は矢飼城山や石見山のつくるくぼ地で谷がつくられている天然の要害地である。

かつて佐和氏は南北朝のころに一族は後醍醐天皇に味方して戦ったという気骨のある家系である。
尼子軍は江川を隔てて1ヵ月余りもにらみあった。
川幅80mの江川は左右の見通しがよく行動が相手に筒抜けになる。
また川岸は直角の鋭い岩山が迫っていて、大軍を一度に渡すことができないため尼子軍にとって不利な状況であった。
尼子晴久は、ここで空しく滞陣しているより銀山を治める方が先決だと考えた。
そこで、晴久は、 軍をかえして大内氏が領する銀山に向かい、銀山を手にいれ帰国した。

かかる形勢なるを以て石見では益田、吉見、福屋、佐波の以外は皆尼子氏の麾下に従属した。
さらに転じて攻撃の手を東にまわし天文13年には伯耆に攻め入り、備後に進んだ。
晴久の勢威は大いにあがった。
<続く>