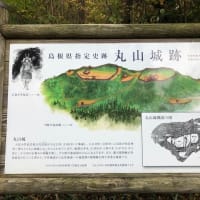30.3.元弘の乱
30.3.7.後醍醐帝の隠岐行在所
現在、後醍醐帝の隠岐の行在所については二つの説がある。
一つは、隠岐の島町(島後島)にある国分寺説である。
もう一つは、西ノ島にある黒木御所説である。
島根懸史(大正十年発行)では、行在所は国分寺跡にあったと、主張している。
二つの説を取り上げ、論評しており、なかなか面白い。
次にその要約を示す。

30.3.7.1. 島根懸史から
1)国分寺説

懸史では
国分寺説は、①古文書②史跡古記③考古学的研究④地名上及び付設の四項から、この説を論定したいと述べて論を展開している。
以下主だった点を抜き出して示す。
①古文書
古文書の一つが、元徳4年/元弘2年(1332年)8月19日に後醍醐帝が出雲の鰐淵寺(がくえんじ)に与えた文章である。
この文章は元徳4年/元弘2年、後醍醐天皇が隠岐に流された際、鰐淵寺の頼源大師が御所に伺候し、宸筆の願文(倒幕の所願を遂げたら薬師堂を造営するというもの)を賜った、とされている。
この願文は現存し、重要文化財に指定されている。

頼源は貞治5年/正平20年(1366年)自分が受け取った、御宸翰、綸旨、令旨等の文書19通を後任の淨達上人に譲る時に、19通の文章の来歴を文章に注記した。
これによると前記の願文は次のように注記されている。
後酉酉皇帝(後醍醐帝)
一通先朝御願書 元弘二年八月十九日於隠岐國國分寺御所被下之
上卿千種宰相中将忠顕卿、干時六條少将二候
②史跡古記
史跡古記の例としては、
<増鏡(久米の佐良山)>
ⅰ)海づらよりは少し入りたる国分寺といふ寺を、よろしきさまにとり拂ひて、おはしまし所に定む。
(海岸より少し入った所にある国分寺と申す寺を、御所に定めた)
これについて、島根懸史では、現在の西郷港から行けば、国分寺までは1里ほど隔たり、海も見えないと思うけど、鎌倉から建武期に亘っては、西郷湾の東部東郷(現隠岐水産高校辺り)の入海沿岸宮田が要津(要の港)だった。
ここからなら2Km行けば、国分寺に達するを以って「海つらより少し入りたる」とある所以である。
ⅱ)徒然に思さるる折々は、廊(らう)めく所に立ち出でさせ給ひて、遙かに浦の方を御覧じ遣るに、海士(あま)の釣舟ほのかに見えて、秋の木の葉の浮かべる心地するも、あはれに、「いづくを指してか」と思さる。
心ざす 方を問はばや 浪の上に 浮きてただよふ あまの釣舟
(わたしの思いを例えるならば、あの浪の上に浮いてただよう漁師の釣舟のようにはかないものではないのか)
国分寺行在所からは、海が見えないという人もいるが、廊の構造は不明だが、当時三重塔が存在した事をもって、搭上から海は見ることができる。
また海上展望の叙景文は雅文に普通なる書きぶりであって左程重きをなすものではない。
殊に増鏡の著者は実地を踏査して書いておらず、帝の感慨無量なる御心中を察して書いたものである。
<太平記(巻第四 備後三郎高徳事附呉越軍事)>
佐々木隠岐判官貞清、国府島云所に、黒木の御所を作て皇居とす。
国府の島すなわち島後島を示している。
この「黒木の御所」というのは「割らざる丸木で造られた御殿」という意味で粗末なる御所をいい、「黒木御所」という実名詞とは大きな差異がある。
余話として
承久3年(1221年)の承久の乱により順徳上皇は佐渡に配流されている。
この順徳上皇の行在所は樹皮つきのままの木材で造営された粗末な宮で黒木御所と呼ばれていた。
③考古学的研究④地名上及び付設
懸史では、古文書・史跡古記より、後醍醐帝の隠岐における行宮は国分寺であることは、動かしようもない史実であるとして、その国分寺について論及が続く。
ⅰ)国分寺御所とは島後の国分寺のことであり、この寺は設立以来移転したことがない。
ⅱ)現国分寺跡から発見された、瓦の残片は奈良時代のものと研究されている。
上記のことから、前述した鰐淵寺の頼源文書の国分寺御所の存在と位置が確定でき、後醍醐帝の行宮は、島後の国分寺であったことが立証できる、と述べている。
また、色々な古記・古文書に、島後の「国分寺村」という村の記述が出てきている、ことも付け加えている。
<続く>