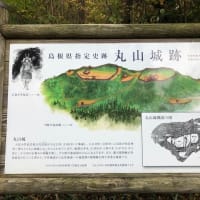42.足利直冬(2)
42.3.足利直冬の上洛
42.3.3.神南合戦
近江に奔った足利尊氏には土岐、佐々木道誉、仁木義長の軍勢、畠山の東国勢が集合した。
また、播磨の鵤(いかるが)の庄(兵庫県揖保郡太子町)に滞陣していた足利義詮軍に、細川頼之らの四国、西国の馳せ参じた。
尊氏と義詮は使者を走らせて、京の直冬を挟み撃ちする、予ての計画を実行することにした。
2 月4日、足利尊氏は東坂本に着き、足利義詮は山崎の西、神南(神内)の北の山の上に陣を張る。
義詮の陣は、山に布陣しているとは言え、木々が生い茂っている険しい状態では敵の動向がつかめず、どこから攻めて来られるかわからないため西の峯、南の峯、北の峯の三方に分かれて陣を張った。
一方足利直冬軍は、第1陣として足利直冬を大将にして斯波高経、桃井直常、赤松氏範らが東寺を拠点にして、七条、九条に布陣した。
第2陣は山名時氏を大将として、淀・鳥羽 ・赤井・大渡一帯に分散して陣を張り、淀川南岸に四条隆俊らが男山八幡山の下に布陣した。
戦は山名軍が仕掛けることにより開戦の火蓋が切られた。
「さすがに、この険しい谷を登っては来れまい」と油断している北朝軍に向かって、山名父子率いる2000余騎が攻め上り、またたく間に西の峯と南の峯が破られた。
最初は虚をつかれ劣勢に陥った北朝軍だったが、態勢を立て直し交戦する。
険しい谷を登る側とこれを防ぐ側での戦いは、上に居る方が有利である。
さすがの山名軍でも敵に押されると、疲れ切った兵士は次から次へと谷になだれ落ちてしまった。
この神南の戦は山名軍の敗走で終結した。
神南の戦いの次は京都の市街戦と続く。
市街戦は三月まで続くことになる。
42.3.4.京戦
神南の戦いで義詮が勝利したことが尊氏に伝わると、尊氏は比叡山を下りて東山に陣を張った。
仁木頼章(義長の兄)も、丹後、丹波勢を率いて上洛、嵐山の上に陣を取った。
その結果、京都南方の淀、鳥羽、赤井(伏見区)、八幡一帯は、南朝軍側の陣となり、東山、西山、山崎、西岡一帯は全て、尊氏側の陣となった。
双方の陣の区域内においては、ありとあらゆる神社仏閣が破壊され、その材木を、武士たちの詰め所の防御壁とした。
また陣中の薪や櫓建設用の建材を得るために、あたり一帯の木々や竹は、残らず切り倒されてしまった。
そして「敵軍が横合いに懸かってきた時には、見通しが良い方が戦いやすいから」という事で、尊氏側は、東山から日々夜々、京都中心部へ寄せてきては、家々を焼き払っていったという。
一方、東寺に駐留している足利直冬側は、「敵陣付近の建物を残らず焼き払ってしまおう、そうすれば、敵は雨露をしのぐ事もできないようになってしまうから、そのうち、人馬共に疲れきってしまうだろう」と、白河区域一帯を攻めては放火を繰り返した。
両軍の手がかからないままに、今も無事に残っている所は、といえば、もはや、皇族、妃、里内裏、大臣、公卿らの館のみである。
それらの建物もみな、門戸を閉ざし、その中には人の気配も無く、野狐の住処と成り果てて、棘が扉を被いつくしてしまっている。
京都中心部での戦は数日に及び、形勢も日々逆転、勝敗は、全く予断を許さない状態であった。
しかし、足利直冬勢は山陰道を仁木頼章の軍勢に塞がれ、山陽道は足利義詮に囲まれ、東、北陸の二つの道は足利尊氏の大軍に塞がれて、わずかに河内路より他に空いている方角はなかったので、兵糧を運ぶ道もなくなっていた。
直冬に味方する軍勢には、これらの道を塞ぐ敵兵を攻め兵糧を運び入れるような助けの兵も出てこなかった。
合戦はこれまで互角だったけれども、尊氏の軍勢が日に日に増えていった。
これでは結局は叶わないだろうということで、3月13日の夜に入って、直冬と諸国の大将とは一斉に東寺、淀、鳥羽の陣を引いて、八幡、住吉、天王寺、堺の港へと逃げて行ったのだった。
八幡御託宣

陣を引き払って撤退してきた足利直冬陣営側の兵力は、ざっと5万余騎であった。
さらに伊賀、伊勢、和泉、紀伊国の軍勢たちが、また馳せ参じるだろうと伝えられていた。
そのため、しばらくこの軍勢を解かないで、もう一戦するべきではないかとの意見も各武将のなかでも上がってきた。
しかし、直冬は、
「許否凡慮の及ぶ処に非ず。八幡の御宝前にして御神楽を奏し、託宣の言に付て軍の吉凶を知べし。」
といって、八幡に参拝した。
直冬たちは、さまざまの奉幣を献上し、お供え物をして神のお告げを待った。
託宣を告げる巫女は神々への言葉を巧みに連ねてさまざまなことを申し上げた。
そして
たらちねの親を守りの神なれば
この手向けをば受くるものかは
「我は親を守る神である この供物を受け取るわけにはいかない」
と、一首の神託の歌を繰り返し繰り返し二、三遍詠じると、巫女は倒れ伏し、神霊は巫女から離脱した、という。

尊氏は直冬の親である、八幡大神は親である尊氏を守る神であり、直冬は尊氏と戦う限りいつまで経っても勝てないということである。
諸大将はこれを聞いて、「それでは、この兵衛佐殿(直冬)を大将にして将軍(尊氏)と戦うことは、今後はもうないだろう」といった。
彼らは、東山道、北陸道の軍勢は、駒に鞭を打って自分の国へ下って行き、山陰、西海の兵は舟に帆を揚げて去って行った。
そして直冬は、堺より海路で西国に向かった。
「太平記」より
誠に征罰の法、合戦の体は士卒に有といへ共、雌雄は大将に依る者也。
されば周の武王は木主を作て殷の世を傾け、漢高祖は、義帝を尊て秦の国を滅せし事、旧記の所載誰か是を不知。
直冬是何人ぞや、子として父を攻んに、天豈許す事あらんや。
始め遊和軒の朴翁が天竺・震旦の例を引て、今度の軍に宮方勝事を難得と、眉を顰て申しを、げにも理なりけりとは、今社思ひ知れたれ。
東寺落て翌の日、東寺の門にたつ。
兔に角に取立にける石堂も九重よりして又落にけり
深き海高き山名と頼なよ昔もさりし人とこそきけ
唐橋や塩の小路の焼しこそ桃井殿は鬼味噌をすれ
「まったく、戦いの法則は厳然としてある。
戦闘を行うのは兵卒であるとは言っても、勝敗は大将によって決まるものである。
ゆえに、周の武王は父文王の位牌を作り、これを持って戦場に望み、殷王朝を倒した。
漢の高祖は義帝を尊んで、その命のもとに秦の国を滅ぼした。
これらのことは、古本に書き残されているところであり、誰も知らない者はない。
直冬はそもそも何者であるか。
子が父を攻める行為を、天がどうして許すことがあろうか。
かつて、遊和軒朴翁が天竺と、古代中国の例を引いて、この度の戦に宮方が勝つことは難しいと眉をひそめて申したことを、全く当然だったと、今まさに思い知らされた。
東寺から直冬の陣が退いた翌日、東寺の門に落書きが立った。
とにかくに取り立てにける石塔も九重よりしてまた落ちにけり
(直冬を大将にとりたてた石塔頼房の野望も、空しくなってしまった)
深き海高き山名と頼むなよ昔もさりし人とこそきけ
(山名時氏は深い梅、高い山のように本当に頼りになる人ではない。深く信頼してはならない。山名は以前にも、京都に攻め込みながら結局、撤退してしまった)
唐橋や塩の小路の焼けしこそ桃井殿は鬼味噌をすれ
(合戦で焼けたのは桃井直常殿が焼味噌を作ったからだ。唐は辛にかけ、味噌に辛味と塩を加えて焼くのが鬼味噌)」
<続く>