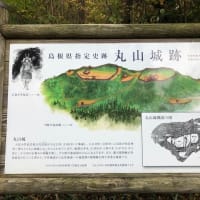36.南北朝動乱・石見編
36.4.戦線の拡大
36.4.6. 石見に来た新田の武将たち
前節で新田義氏は他の武将と共に、海路で石見の南朝方を頼ってやって来た、と書いたが、この他の武将の名前は殆どの史料に載っていない。
唯一名前を記載しているのは、「南北朝石見軍記」である。
これによると、やって来たのは、畑六郎時能、瓜生源林、渡利新左衛門忠景、奥野弾正景秀らの部将である。
南北朝石見軍記
この軍記については、前にも説明したが、再掲する
「南北朝石見軍記」は昭和51年(1976年)12月1日初版発行された軍記である。
著者は山田木母(本名:山田吉太郎)で石見の人である。
山田吉太郎は昭和26年頃から、石見の歴史に取り組み、石見軍記に関する史書や伝説を集めたという。
ところが、昭和40年7月23日の江川大水害の時に、当時川本町にいた山田は屋上冠水に遭い、多くの資料が流出し、この軍記をまとめ上げるに当たり、資料的に十分でないことを悔やんでいる。
この軍記は、歴史小説で南北朝動乱期の石見での合戦模様を記述している。
資料は、石見6郡の市町村史や地元の伝説が主体であるという。
「南北朝石見軍記」では、一緒に来た武士たちとは、畑六郎時能、瓜生源林、渡利新左衛門忠景、奥野弾正景秀らの部将である、としている。
また、これらの武将は、分和2年/正平7年(1353年)に石見を去っていった、と記述している。
ただ、この軍記に書かれていることは、他の資料で確認出来ないことも多く、また他の資料とは明らかに違っていることも書かれている。
この本は石見に残る伝説を基に物語を作り上げており、幻想的或いは架空と思われることも、書かれているのは当然のことかもしれない。
以下、義氏に従って岩見に来たと云われる4人の武将について触れておく。
36.4.6.1.畑六郎時能
畑六郎左衛門時能は、篠塚伊賀守・粟生左衛門・亘理新左衛門と並んで新田義貞四天王の一人に数えられる武将である。

畑六郎に関する話は、その周りのことから始めたい。
暦応2年/延元4年(1339年)後醍醐天皇崩御(52歳)した。
同じ年11月15日、南朝の群臣は皆で相談して先帝に追号を送った。
在位の間執政に多く延喜の御代を手本としており、もっともその縁が深いということで、後醍醐天皇と諡(おくりな)が決まった。
ここに、後醍醐天皇の名前が歴史に登場する。
(今までは便宜上、諡で名前を表していた)
同じく12月、北国の各地を転戦していた脇屋刑部卿義助朝臣の所へ朝廷から綸旨が出された。
故義貞の場合と変わらず、官軍の恩賞などのことを図って天皇に申し出るように命じられたのである。
義助は、遺詔で他の者と異なる言葉があった恐れ多さに、忠義の心をますます心に銘じた。
義助は、一旦大きく勢力を盛り返すが、京から大軍が派遣されて追い詰められ、義助自身は美濃に逃れた。
義助は尾張から伊勢・伊賀を経由して吉野に入り後村上天皇に拝謁する。
その後、四国に出兵し、そこで死亡している。
義助に従って転戦していた、畑六郎は暦応4年/興国2年年(1341年)7月鷹巣城(福井市高須町)に追い詰められていた。
畑六郎は僅か27人で籠もり抵抗していた。
10月、鷹巣城から伊地知山(福井県勝山市)へ移動しても抵抗姿勢を続ける。
畑六郎については、「太平記」でもかなり長文でエピソードを記述している。
「太平記」
彼畑六郎左衛門と申は、武蔵国の住人にて有けるが、歳十六の時より好相撲取けるが、坂東八箇国に更に勝者無りけり、腕の力筋太して股の村肉厚ければ、彼薩摩の氏長も角やと覚て夥し。
其後信濃国に移住して、生涯山野江海猟漁を業として、年久く有しかば、馬に乗て悪所岩石を落す事、恰も神変を得るが如し。
唯造父が御を取て千里に不疲しも、是には不過とぞ覚へたる。水練は又憑夷が道を得たれば、驪龍頷下の珠をも自可奪。
弓は養由が迹を追しかば、弦を鳴して遥なる樹頭の栖猿をも落しつべし。
謀巧にして人を眤、気健にして心不撓しかば、戦場に臨むごとに敵を靡け堅に当る事、樊噲・周勃が不得道をも得たり。
*樊噲・周勃:中国の武将、漢の高祖に従っていた。
されば物は以類聚る習ひなれば、彼が甥に所大夫房快舜とて、少しも不劣悪僧あり。
又中間に悪八郎とて、欠脣なる大力あり。
又犬獅子と名を付たる不思議の犬一疋有けり。
此三人の者共、闇にだになれば、或帽子甲に鎖を著て、足軽に出立時もあり。
或は大鎧に七物持時もあり。様々質を替て敵の向城に忍入。
先件の犬を先立て城の用心の様を伺ふに、敵の用心密て難伺隙時は、此犬一吠々走出、敵の寝入、夜廻も止時は、走出て主に向て尾を振て告ける間、三人共に此犬を案内者にて、屏をのり越、城の中へ打入て、叫喚で縦横無碍に切て廻りける間、数千の敵軍驚騒で、城を被落ぬは無りけり。
「夫犬は以守禦養人。」
「その畑六郎左衛門というのは、武蔵国の住人であったが、十六歳の時から相撲を好んで取っていたが、板東八ヶ国に全く勝つ者がなかったのだった。
腕の筋肉が太くて、腿の盛り上がった肉が厚かったのであの薩摩の氏長もこのようだったかと思われて、大変なものだった。
その後信濃国に移住して、ずっと山野、海川の狩りや漁を生業として長年過ごしていたところ、馬に乗って難所や岩場を駆け下りることはまるで神業のようだった。
まったく造父が馬を操って千里も疲れなかったというのも、これ以上ではあるまいと思われた。
水泳はまた水神憑夷(ひょうい)の術を心得ていたので黒龍の顎の下の玉も自分で取ることができそうだった。
弓は養由の術を受け継いだようで、弦を鳴らして遠くの木の上に住み着いた猿を落とすほどだった。
策略も巧みで人をてなづけ、気持ちはまっすぐで心が強かったので、戦場に臨む度に敵を降伏させ難敵に立ち向かうことでは、樊噲(はんかい)や周勃(しゅうぼつ)も叶わないほどだった。
そこで類は友を呼ぶということだから、彼の甥に所大夫房快舜といって、少しも劣らない剛勇の僧がいた。
また中間に悪八郎といって、みつくちの力持ちがいた。
また犬獅子と名付けた不思議な犬が一匹いた。
この三人の者たちは、闇夜にさえなると、ある時は帽子兜に鎖帷子を着て身軽に出かける時もある。
ある時は大鎧に七つ道具を持つ時もある。
様々に手立てを変えて敵の城に忍び込む。
まず例の犬を先に立てて、城の警備の様子を窺わせ、敵の注意が厳しくて隙が見いだせない時はこの犬が一声吠えて走り出し、敵が寝入って夜回りもない時は走り出て主人に尾を振って伝えたので、三人ともこの犬を先導者にして塀を乗り越え城の中に入って、喚き叫んで縦横無尽に切って回るので、数千の敵軍は驚いて、城を落とされないことがなかった。
「そもそも犬は警備をすることで人に養われる」と言う。」
畑六郎が飼っている犬獅子という犬はとても利口であった。
闇夜にまぎれ城を抜け出した犬は敵陣に潜り込み、警備が厳しいと一吠え、寝込んでいると尻尾を振り畑時能に合図した。
これで、畑時能は毎夜、夜襲を仕掛け敵を悩まし続けた。

この、畑六郎は暦応4年/興国2年(1341年)10月22日の合戦で肩に矢を受け、三日後の10月25日に苦しんで絶命した、とされている。
「太平記」に畑六郎の死に様がかかれている。
「・・・・
戦いが終わった後、畑が帷幕の中に帰ってその兵を集めると、五騎は討たれ九人は重傷を負っていた。
畑も脛当ての外れや小手の脇など切られていないところがなかった。
首筋の鎧の板の隙間から肩先へ射込まれた白羽の矢一本を何とかして抜いたけれども、鏃(やじり)が全く抜けなかったので、三日間苦痛に責められ、終に吠(ほ)へ死んでいった。
畑という男は、悪逆無道にして、罪障を不恐のみならず、無用なるに僧法師を殺し、仏閣社壇を焼壊ち、修善の心は露許もなく、作悪業事如山重しかば、勇士智謀の其芸有しか共、遂に天の為にや被罰けん、流矢に被侵て死にけるこそ無慙なれ。」
この畑六郎は、脇屋の黒丸城攻略に至る緒戦(この戦いの記述は省略)では「八百余人の首を切り、女子供も三歳の嬰児まで残らずこれを刺し殺した」という乱暴ぶりだったので、悶死もやむを得なかったという「太平記」の作者の思いである。
以上、エピソードを交えて記述したが、畑六郎時能は、伊知地(福井県勝山市)で亡くなっており、石見を訪れていないのは確かであろう。
次に説明する「渡利新左衛門忠勝」は江津市桜江町川越に一時居を構えていたと云われている。
<続く>