●安倍政権の成果...領土教育は充実へ
今年発表された小学校の教科書検定でも、小学5年社会で、竹島・北方領土・尖閣諸島について全社が「固有の領土」と記述した。竹島・北方領土についても全社が「不法占拠」と記述するようになった。これ自体は前回の検定からである。
安倍政権時の学習指導要領改訂によって「竹島や北方領土、尖閣諸島が我が国の固有の領土であることに触れること」が明記された結果といえよう。
今回の検定では、さらに微修正が加えられ、一部を除き、「領土教育」が確立したといえる。
●「朝鮮学校の教科書に「拉致問題」を書け」も日本の教科書がこの有様では...拉致問題を書かない教科書の問題
しかし、課題もある。未だに、北朝鮮が多数の日本人を詐欺・暴行・脅迫などの不法な手段を使って強引に北朝鮮本土に連れ去った拉致問題については、小6の教科書(領土問題とは分野が違うので学年も違う。)では注釈やコラム程度の扱いであり、その書き方も「解決すべき問題」とはしているものの、主権や人権、安全保障をめぐる重大な問題であるとはされていない。
驚くべきことに、小3から小6までの全ての社会科教科書の単元本文に拉致問題は登場していないのである。学校でも、コラムが教えられるはずもなく、拉致問題について教えられることはない。憂慮(ゆうりょ)すべき事態である。
中学校の歴史教科書でも、公民教科書でも、単元本文で拉致問題が登場する教科書は少ない。基本的に実際の授業で全く使われないコラムなどを設けて記述してるように見せかけているだけである。
しかも、人権問題、主権問題、安全保障問題という位置付けはほとんどの教科書で行われていない。拉致問題の背景が書かれることもない。
高校ともなると、さらに事態は悪化し、執筆者が調べた限りでは、単元本文で拉致問題を書く教科書は存在しない。コラムで書く教科書がわずかに存在するだけである。
そのような状況だから、当然、人権問題、主権問題、安全保障問題という位置付けがされるはずもない。
日本の教科書は、拉致問題を完全に無視しているのである。覚えておきたいのは、自由社や育鵬社などの教科書を変えていこうという立場の教科書でさえ、この問題については、さすがに無視はしないものの、大コラムで書いた気になっているだけである。
しかも、そのコラムの中でも安全保障問題的な位置付けをする(明言はしていない)のは、自由社だけである。一応、拉致問題の背景などは、自由社も育鵬社もコラムで書いている。
ぜひとも次回からは単元本文で書いてもらいたい。
●学習指導要領の一部改訂で拉致問題教育の充実を
中学校の教科書検定もある。前々回(平成22年)の学習指導要領前の検定では、小学校で「固有の領土」が徹底されなかったことなどを背景に、指導要領解説が改訂され、「領土教育」の充実が謳われた。
今回も、小学校教科書の検定結果を受けて、学習指導要領や学習指導要領を一部改訂し、拉致問題に関する内容を充実させるべきではないか。
●主権・人権・安全保障の問題解決意識の低い日本社会
日本社会では、長年、主権や人権、安全保障に対する意識自体はあっても、主権や人権、安全保障をめぐる実際問題を解決しようという意識が低かった。それどころか、戦後一貫して主権や人権、安全保障に対する意識さえも低下してきた実態がある。
すなわち、日本社会が主権や人権、安全保障をめぐる問題に対して実質的に黙認の姿勢をとっていたのである。
だが、主権や、人権、安全保障をめぐる問題を解決しようとすることは国家の役割に照らせば当然に行われなければならないはずである。
国家には、決まった範囲の領土(りょうど)があって、その周りに領海(りょうかい)を持ち、それらの上に領空(りょうくう)を持つ。これが国家の領域(りょういき)である。
領域の中にはそこで生活する人々がおり、この人々が国家を運営する主体となる。これが国民(こくみん)である。
国家が、領域や国民を支配する権利を、統治権(とうちけん)といい、これが対外的に独立し、どの国の干渉も受けないようになると、国家主権(こっかしゅけん)となり、主権を持つ主権国家(独立国)となる。
この主権、領域、国民が国家の三要素(こっかのさんようそ)である。領域や国民がなければ、国家が成立しないのは分かるだろう。では、主権はどうだろうか。
主権を持たない国家は、どこかの国に属するか、他国の影響を強く受ける傀儡国家(かいらいこっか)になるしか、選択肢がない。このような場合、当然、現地の国民の意思や利益が尊重されるわけがなく、現代の国家は、この主権を持ち、かつ独立し、主権と独立を守ることが重要である。
このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられている。
これらの役割を担うのが、国会や、内閣、裁判所などの国の機関である。例えば、防衛省や自衛隊は、このうちの防衛を担っている。警察は国内の秩序の維持を担っている。裁判所は、国内の秩序の維持と国民の自由と権利を守る役割を担っている。
国家は、これらの役割を限られた時間で果たすために、できるかぎり合意に努める。これが政治である。ただし、限られた時間で対立を解消しきれず、合意に達しない場合は、権力による強制も避けられない。この権力が、政治権力である。
政治権力は、一見すると、国家による一方的な強制力のようにも見えるが、実は国民がその政治権力を承認しているから成立しているのである。国民の承認がない政治権力は、歴史上いくつか存在してきたが、例外なく、その国家は消滅している。国民の承認がなければ、政治権力を維持することは不可能なのである。
国民、すなわち日本社会は、日本国家の政治権力を承認する立場であり、政治権力の行使について助言する権利や義務があるといえる。
日本社会全体が、国家の構成員であるとの自覚をもち、主権や人権、安全保障をめぐる問題について主体的に解決しようとする必要があるだろう。
人権については改善されているものの、主権や安全保障については、現状を見るにほとんど改善されていないというのが現実である。
教科書でも、単なる人権問題は多く取り上げられるが、同じ人権問題であっても、拉致問題のように主権や安全保障をめぐる問題は全く取り上げられない。
つまり、教科書上では、単に主権や安全保障に対する意識が低いだけでなく、主権や安全保障をめぐる問題をあえて避けてきた側面があるのである。異常事態である。
拉致問題と同じく主権や安全保障に関わる「領土教育」は、学習指導要領改訂後に限界まで充実した。安倍政権の成果である。
北朝鮮による日本人拉致問題についても、小学校や中学校・高校において歴史の戦後史の部分で『日中国交正常化』(日本国政府による台湾との国交の一方的な破棄)などと一緒に「北朝鮮による日本人拉致問題についても触れること。」などの規定で、歴史的事象の一つとして触れるべきではないか。
また、中学・高校の公民については、国際社会編の規定を改正し、「「国家主権」については,我が国が,北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて努力していることなども取り上げること。」と明記するべきではないか。
これからの社会科教育改革のキーワードは「拉致問題教育」ではないだろうか。











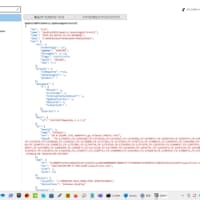


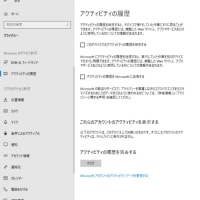





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます