
ベニモンアオリンガ。
黄色~緑色の地色に、ピンクの紋がある美しい小型の蛾。
ツツジの害虫として知られます。

分類:
チョウ目コブガ科ワタリンガ亜科
翅を広げた長さ:
17~23mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
平地~丘陵
成虫の見られる時期:
4~9月(年2~3化)
蛹で冬越し
エサ:
成虫・・・不明
幼虫・・・ツツジ、サツキ、シャクナゲなどツツジ類の新芽、花芽
その他:
前翅は黄色~深緑色で、前翅中央に紅色の紋がある。
斑紋は変異が大きく、ほとんど認められない個体もある。
前翅外縁は紫色。
前翅前縁基部は地色で、後翅はくすんだ灰色。
(同属のアカマエアオリンガは、前翅前縁基部は紅色に色づき(地色の個体もある)、後翅は白色。)
前脚のふ節は黒と白の縞模様。
触角は♂が繊毛状、♀は糸状。
広葉樹を中心とする樹林と林縁、公園、果樹園、人家の庭などで見られる。
普通種で個体数も多い。
夜行性で、灯火に飛来することも多い。
幼虫の頭部は黒色で、体色は赤褐色。
背面中央に淡色部がある。
4月、6月、8月頃、見られる。
夏の幼虫(主に若齢)は、ツツジ類の翌年開花する花芽に穿孔して内部を食べるため、害虫とされる。
夜行性で、一夜で50芽を摂食するとも。
ツツジ類もち病の菌えいと、その表面に生じた子実層を摂食することもあり(えい食性、菌食性)、飼育下ではそれのみで全ステージを完了できる。
別名シンクイムシ。
終齢幼虫の体長は約15mm。
小枝に灰白色の繭を作って蛹化する。
卵~産卵までの1サイクルは約2か月。
参考:
みんなで作る日本産蛾類図鑑V2
かたつむりの自然観撮記
虫ナビ
ガーデニング花図鑑
J-STAGE
堺市都市緑化センター
東京昆虫館ほか
黄色~緑色の地色に、ピンクの紋がある美しい小型の蛾。
ツツジの害虫として知られます。

分類:
チョウ目コブガ科ワタリンガ亜科
翅を広げた長さ:
17~23mm
分布:
北海道、本州、四国、九州
平地~丘陵
成虫の見られる時期:
4~9月(年2~3化)
蛹で冬越し
エサ:
成虫・・・不明
幼虫・・・ツツジ、サツキ、シャクナゲなどツツジ類の新芽、花芽
その他:
前翅は黄色~深緑色で、前翅中央に紅色の紋がある。
斑紋は変異が大きく、ほとんど認められない個体もある。
前翅外縁は紫色。
前翅前縁基部は地色で、後翅はくすんだ灰色。
(同属のアカマエアオリンガは、前翅前縁基部は紅色に色づき(地色の個体もある)、後翅は白色。)
前脚のふ節は黒と白の縞模様。
触角は♂が繊毛状、♀は糸状。
広葉樹を中心とする樹林と林縁、公園、果樹園、人家の庭などで見られる。
普通種で個体数も多い。
夜行性で、灯火に飛来することも多い。
幼虫の頭部は黒色で、体色は赤褐色。
背面中央に淡色部がある。
4月、6月、8月頃、見られる。
夏の幼虫(主に若齢)は、ツツジ類の翌年開花する花芽に穿孔して内部を食べるため、害虫とされる。
夜行性で、一夜で50芽を摂食するとも。
ツツジ類もち病の菌えいと、その表面に生じた子実層を摂食することもあり(えい食性、菌食性)、飼育下ではそれのみで全ステージを完了できる。
別名シンクイムシ。
終齢幼虫の体長は約15mm。
小枝に灰白色の繭を作って蛹化する。
卵~産卵までの1サイクルは約2か月。
参考:
みんなで作る日本産蛾類図鑑V2
かたつむりの自然観撮記
虫ナビ
ガーデニング花図鑑
J-STAGE
堺市都市緑化センター
東京昆虫館ほか










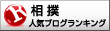

















それほど珍しいものではないですよね。
害虫なんですけど、キレイなので、見つけると撮ってしまいますね(笑)