
セアカオサムシ。
居たのは・・・

施設の廊下です!
初め、セアカヒラタゴミムシ辺りかな?と思って。
約2㎝と小さかったし、暗かったので。
「キレイに撮れたかな?」
と、拡大して確かめてみたら・・・

前翅にコブ状突起の列!
小さいけど、れっきとしたオサムシ亜科!
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)によると、セアカオサムシ。
茨城県の準絶滅危惧種じゃないですか!
準絶滅危惧種が廊下を徘徊してる施設って・・・(笑)
戻ってみたけど、すでに姿はなし。
誰かに踏まれるなよ。

分類:コウチュウ目オサムシ科オサムシ亜科
体長:16~22mm
分布:北海道、本州、四国、九州(北海道を除いて生息地は局地的)
平地~山地
成虫の見られる時期:4月下旬~10月初旬
成虫で冬越し
エサ:成虫・・・チョウ目幼虫やその他昆虫、ミミズ等
幼虫・・・?
その他:茨城県準絶滅危惧種。
オサムシ亜科としては小型。
頭部・前胸部は赤銅色。
上翅は黒色または暗赤銅色で、側縁部は赤銅色で縁どられる。
また、卵型のコブ状突起の列(3列)と細い隆起線が交互に走る。
後翅は非常に短く退化していて飛べない。
♂の前脚のふ節は、♀に比べて大きく広がる。
草原などの環境を好むため、開発によって草原環境が失われたり、野焼きなど人為的な管理の放棄によって森林に遷移することで、生息が脅かされる。
また、「愛好者」による乱獲も懸念材料となりうる。
主に夜間活動する。
少ない。
春に繁殖し、8月中旬~10月頃に新成虫が現われる。
苔の下、土中や石の下などで越冬する。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
とある虫屋のむし写し
里山のゴミムシ
関東を中心とした地表徘徊性甲虫
茨城県RDB?
京都府RDB2015
精霊の庵-無名の絶滅危惧昆虫
RDBとちぎ
北海道生物図鑑
居たのは・・・

施設の廊下です!
初め、セアカヒラタゴミムシ辺りかな?と思って。
約2㎝と小さかったし、暗かったので。
「キレイに撮れたかな?」
と、拡大して確かめてみたら・・・

前翅にコブ状突起の列!
小さいけど、れっきとしたオサムシ亜科!
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)によると、セアカオサムシ。
茨城県の準絶滅危惧種じゃないですか!
準絶滅危惧種が廊下を徘徊してる施設って・・・(笑)
戻ってみたけど、すでに姿はなし。
誰かに踏まれるなよ。

分類:コウチュウ目オサムシ科オサムシ亜科
体長:16~22mm
分布:北海道、本州、四国、九州(北海道を除いて生息地は局地的)
平地~山地
成虫の見られる時期:4月下旬~10月初旬
成虫で冬越し
エサ:成虫・・・チョウ目幼虫やその他昆虫、ミミズ等
幼虫・・・?
その他:茨城県準絶滅危惧種。
オサムシ亜科としては小型。
頭部・前胸部は赤銅色。
上翅は黒色または暗赤銅色で、側縁部は赤銅色で縁どられる。
また、卵型のコブ状突起の列(3列)と細い隆起線が交互に走る。
後翅は非常に短く退化していて飛べない。
♂の前脚のふ節は、♀に比べて大きく広がる。
草原などの環境を好むため、開発によって草原環境が失われたり、野焼きなど人為的な管理の放棄によって森林に遷移することで、生息が脅かされる。
また、「愛好者」による乱獲も懸念材料となりうる。
主に夜間活動する。
少ない。
春に繁殖し、8月中旬~10月頃に新成虫が現われる。
苔の下、土中や石の下などで越冬する。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
とある虫屋のむし写し
里山のゴミムシ
関東を中心とした地表徘徊性甲虫
茨城県RDB?
京都府RDB2015
精霊の庵-無名の絶滅危惧昆虫
RDBとちぎ
北海道生物図鑑










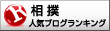


















それとも遺存種のように地質時代の影響を受けているのでしょうか?
局地的な生息域で、それぞれ独自の分化はしていないのでしょうか?
なんて、いろんな不思議を感じました。
オサムシではオオマルガタゴミムシを写しています。似た虫にも出会うのですが撮らせてくれません。
「局地的」には色々原因があるでしょうが・・・。
草原は、放っておけば森林に遷移してしまうので。
川の氾濫で常に草原環境が維持されたり。
野焼きや定期的な草刈りなど、人の手で管理されたり。
そういう場所であることが条件の一つであるようです。
勿論、開発されてしまえば、一発アウト!です。
飛べないので、独自分化はあり得るでしょうね。
ただ、見つけること自体が難しいので、研究が進まない、というのが現状だと思います。
手塚治虫さんも魅了されたオサムシ、やっぱりカッコイイですよね!
オサムシ類は素早いので、なかなかマトモに撮らせてくれませんね(笑)
どうしてもブレた写真が多くなります。
淡水魚の希少タナゴ類と似た状況なんですね。
ときおり起きる環境の攪乱で維持されることや各地に残されてる局地的な生息地、研究でさえも生存への圧力になりうることなど、いい勉強になります。
感謝します。
自然との共存は、難しいですね。