
アオマダラタマムシのメス。
残念ながら死んでます。
まだ生きている個体には遇ったことがありません。
次は是非是非、生きている個体を観てみたい!

大きさは2㎝位かな?
この種としては、小振りです。
まるで螺鈿細工のようですね。
「茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)」によると・・・
茨城県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類
「上翅は縦隆条が細長く強調され、

特徴的な2対の丸型陥没紋を有し、

側縁の鋸歯状が目立つ。」
とある。

腹側。
腹の末端の形から、メスだと思われる。

オスならこの辺に(赤で示したように)V字の切れ込みがある。
→参考
これは、ヤマトタマムシでも同様の特徴が見られる。

茨城県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類
分類:コウチュウ目タマムシ科ルリタマムシ亜科
体長:16~29mm
分布:本州(関東以西)、四国、九州(西日本に多く、北関東では局所的)
丘陵~山地
成虫の見られる時期:5月下旬~8月中旬
幼虫・成虫で冬越し
エサ:成虫・・・サクラなどの葉?
幼虫・・・アオハダ、クロガネモチ、オガタマノキ、ツゲなどの立ち枯れ・衰弱木
その他:タマムシ、ウバタマムシに次ぐ大きさ。
体色は金緑色で、橙色、赤色を帯びる個体もある。
上翅には細長い縦隆条が強く現れ、二対の丸い陥没紋がある。
上翅の縁は、ギザギザに切れ込みがある。
オスは腹端にV字型の切れ込みがある(ヤマトタマムシと同様)。
個体数は少ない。
主に西日本に分布し、北関東では少なく、里山林や寺社林などに局所的に分布する。
幼虫の食樹の立ち枯れ・衰弱木に集まり、交尾・産卵する。
幼虫の期間は2年ほど。
ヤマトタマムシでは蛹の期間が1年以上あるので、あるいはこのタマムシも、蛹の期間が長いかも知れない。
晩夏から初秋にかけて羽化し、翌年の春まで蛹室内で過ごす。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400②(文一総合出版)
かたつむりの自然観撮記
採集好きの虫部屋ほか
残念ながら死んでます。
まだ生きている個体には遇ったことがありません。
次は是非是非、生きている個体を観てみたい!

大きさは2㎝位かな?
この種としては、小振りです。
まるで螺鈿細工のようですね。
「茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)」によると・・・
茨城県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類
「上翅は縦隆条が細長く強調され、

特徴的な2対の丸型陥没紋を有し、

側縁の鋸歯状が目立つ。」
とある。

腹側。
腹の末端の形から、メスだと思われる。

オスならこの辺に(赤で示したように)V字の切れ込みがある。
→参考
これは、ヤマトタマムシでも同様の特徴が見られる。

茨城県レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類
分類:コウチュウ目タマムシ科ルリタマムシ亜科
体長:16~29mm
分布:本州(関東以西)、四国、九州(西日本に多く、北関東では局所的)
丘陵~山地
成虫の見られる時期:5月下旬~8月中旬
幼虫・成虫で冬越し
エサ:成虫・・・サクラなどの葉?
幼虫・・・アオハダ、クロガネモチ、オガタマノキ、ツゲなどの立ち枯れ・衰弱木
その他:タマムシ、ウバタマムシに次ぐ大きさ。
体色は金緑色で、橙色、赤色を帯びる個体もある。
上翅には細長い縦隆条が強く現れ、二対の丸い陥没紋がある。
上翅の縁は、ギザギザに切れ込みがある。
オスは腹端にV字型の切れ込みがある(ヤマトタマムシと同様)。
個体数は少ない。
主に西日本に分布し、北関東では少なく、里山林や寺社林などに局所的に分布する。
幼虫の食樹の立ち枯れ・衰弱木に集まり、交尾・産卵する。
幼虫の期間は2年ほど。
ヤマトタマムシでは蛹の期間が1年以上あるので、あるいはこのタマムシも、蛹の期間が長いかも知れない。
晩夏から初秋にかけて羽化し、翌年の春まで蛹室内で過ごす。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400②(文一総合出版)
かたつむりの自然観撮記
採集好きの虫部屋ほか










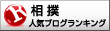


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます