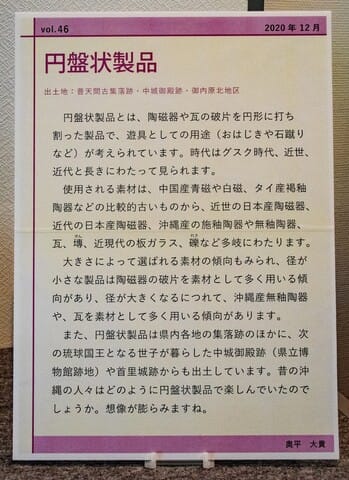危険な坂を下って!




目的地を間違えてしまい着いた所がここでした。
第二尚氏王統第三代国王尚真王の長女、佐司笠按司加那志(サシカサアジカナシ)が、福木の大木にいつも白鷺(しらさぎ)がとまる様子を見て、「水鳥が集まるこの地に湧き水があるのでは?」と掘り当てた樋川(フィージャー)で、別名、鷺泉(ろせん)とも呼ばれていました。
尚順男爵はこの樋川から号名をとって「鷺泉」と号していました。
厳しい干ばつでも枯渇することなく、今でも水が湧き出ており人々の暮らしを支え続けています。
うっそうとした樹々や琉球石灰岩の石垣に囲まれた樋川周辺では、神秘的な雰囲気を味わうことができます。