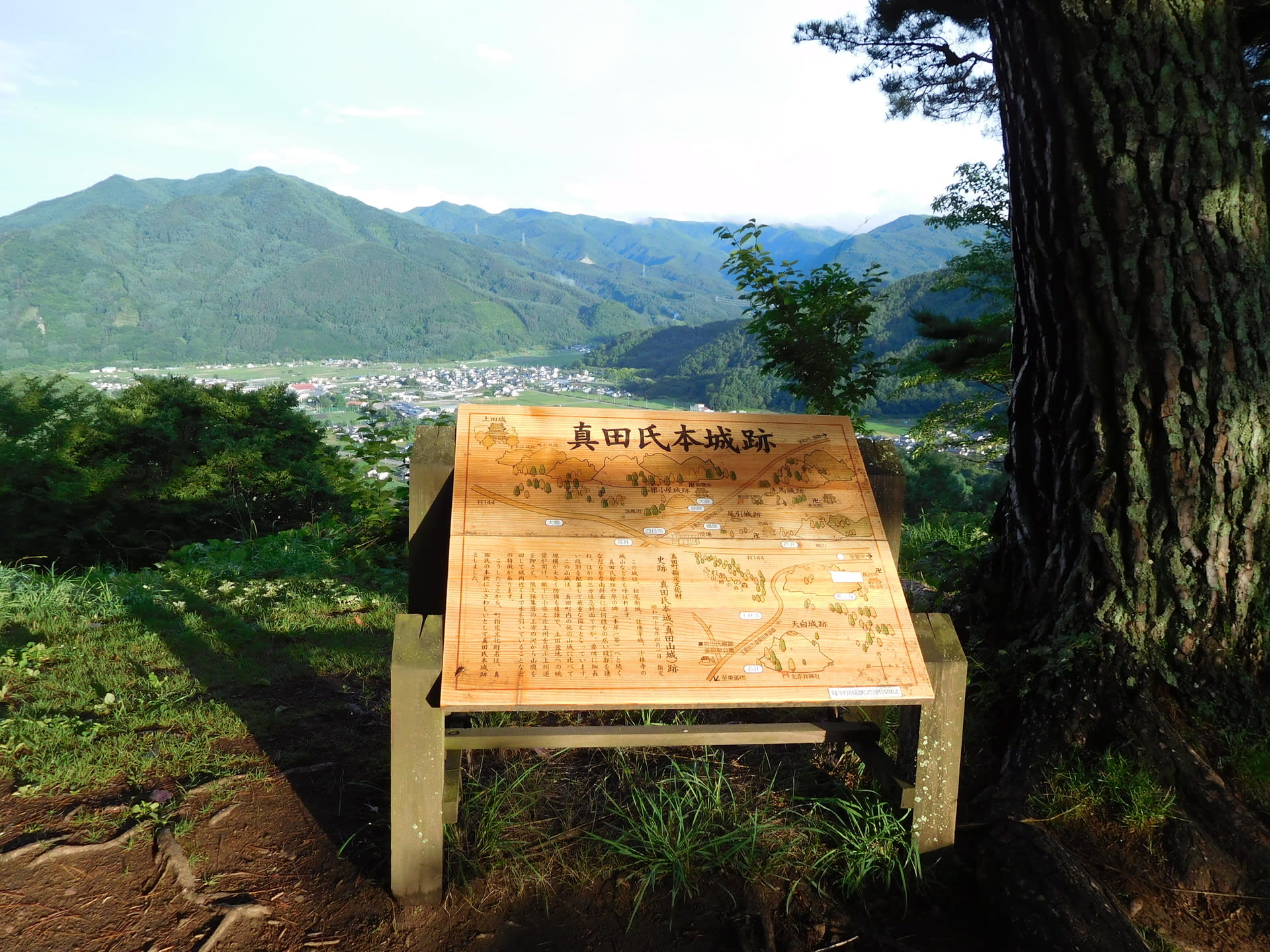【秋田城】あきたじょう
【別名】最北の古代城柵官衙遺跡
【構造】古代城柵
【築城者】大和朝廷
【築城年代】733年(天平5年)
【指定史跡】国指定史跡
【場所】秋田市寺内大畑 地図
地図
【スタンプ設置場所】秋田市立秋田城歴史資料館・史跡公園管理棟
【城郭検定】出題あり

秋田城は出羽国秋田にあった日本の古代城柵であり、奈良時代に庄内地方の出羽柵が秋田村高清水に移転したことで後に秋田城と改称されました。
朝廷によって設置された城柵としては城柵の中では最北に位置するもので、外交の拠点として重要な位置にありました。
出羽国秋田にあった日本の古代城柵。
現在は「高清水公園」となっています。
外郭築地

門の横に続いている土壁は築地とよばれています。
土を人の手でつき固めながら積み上げる版築という古代と同じ工法で造られています。
復元した築地の端は途中で切れていますが、実際は秋田城の回りを囲んでいました。
城柵の基本構造は築地塀で覆われた外郭と政庁を囲む内郭との二重構造から出来ています。
鵜ノ木地区
古代沼

平安時代の井戸


今でも水が湧き出ている。
古代水洗厠舎跡

水洗トイレ
個室の床下の便槽に溜まった汚物を木樋を通して沼に排水する仕組みになっている。

木製トイレットペーパーや寄生虫卵などが出土されている。
この日は早朝に訪れたためか扉が開いておらず、中を見学することが出来ませんでした。残念…。
住居跡

掘立式の建物が東西、南北に整然と並び井戸も造られていた。
天平の井戸

この井戸は、加工した厚い杉材を円形に組み合わせて造られています。
奈良時代の733年頃に造られたものと考えられます。
かまど跡

こちらからは煮炊き用のカマドや食器類が見つかりました。

政庁第一期模型

733年~770年頃 「出羽柵」創建
大規模な盛り土による整地を行い、政庁内の正殿は白壁で床には塼(古代の煉瓦)が敷き詰められていて、政庁を囲っていた築地塀の屋根には煉瓦が葺かれていました。
政庁第二期模型

770年~800年頃
降雪や凍結など厳しい冬の気象条件により崩壊した第一期の築地塀(北半分)を築き直し、屋根は煉瓦から板葺に変えました。
南半分の築地塀は布堀と呼ばれる溝状の堀込みの中に、木材を隙間なく立て並べた木材列塀に変えました。
政庁第三期模型

800年~830年頃
政庁域全体を再度整地、全面的に改修を行った。
主要建物の規模も構造も変わり、区画施設も北側の築地塀をやめて南側の材木列塀とともに等間隔に柱を立て並べ、横材でふさぐ一本柱列塀に変えました。
政庁東門

これより先は秋田城跡で最も重要な政庁内となります。
正殿跡

定期的に貢物を持って訪れる蝦夷の人々を迎え、味方に引き入れる目的で位階や布などを与えたり、宴を催したりしていました。
外国からの使節を迎えての儀式も行われていたと考えられています。
駐車場とトイレ

外郭東門沿いの道路反対側にあります。
駐車場付近

現在も発掘調査はつづく。
平成28年7月17日登城
【別名】最北の古代城柵官衙遺跡
【構造】古代城柵
【築城者】大和朝廷
【築城年代】733年(天平5年)
【指定史跡】国指定史跡
【場所】秋田市寺内大畑
 地図
地図【スタンプ設置場所】秋田市立秋田城歴史資料館・史跡公園管理棟
【城郭検定】出題あり

秋田城は出羽国秋田にあった日本の古代城柵であり、奈良時代に庄内地方の出羽柵が秋田村高清水に移転したことで後に秋田城と改称されました。
朝廷によって設置された城柵としては城柵の中では最北に位置するもので、外交の拠点として重要な位置にありました。
出羽国秋田にあった日本の古代城柵。
現在は「高清水公園」となっています。
外郭築地

門の横に続いている土壁は築地とよばれています。
土を人の手でつき固めながら積み上げる版築という古代と同じ工法で造られています。
復元した築地の端は途中で切れていますが、実際は秋田城の回りを囲んでいました。
城柵の基本構造は築地塀で覆われた外郭と政庁を囲む内郭との二重構造から出来ています。
鵜ノ木地区
古代沼

平安時代の井戸


今でも水が湧き出ている。
古代水洗厠舎跡

水洗トイレ
個室の床下の便槽に溜まった汚物を木樋を通して沼に排水する仕組みになっている。

木製トイレットペーパーや寄生虫卵などが出土されている。
この日は早朝に訪れたためか扉が開いておらず、中を見学することが出来ませんでした。残念…。
住居跡

掘立式の建物が東西、南北に整然と並び井戸も造られていた。
天平の井戸

この井戸は、加工した厚い杉材を円形に組み合わせて造られています。
奈良時代の733年頃に造られたものと考えられます。
かまど跡

こちらからは煮炊き用のカマドや食器類が見つかりました。

政庁第一期模型

733年~770年頃 「出羽柵」創建
大規模な盛り土による整地を行い、政庁内の正殿は白壁で床には塼(古代の煉瓦)が敷き詰められていて、政庁を囲っていた築地塀の屋根には煉瓦が葺かれていました。
政庁第二期模型

770年~800年頃
降雪や凍結など厳しい冬の気象条件により崩壊した第一期の築地塀(北半分)を築き直し、屋根は煉瓦から板葺に変えました。
南半分の築地塀は布堀と呼ばれる溝状の堀込みの中に、木材を隙間なく立て並べた木材列塀に変えました。
政庁第三期模型

800年~830年頃
政庁域全体を再度整地、全面的に改修を行った。
主要建物の規模も構造も変わり、区画施設も北側の築地塀をやめて南側の材木列塀とともに等間隔に柱を立て並べ、横材でふさぐ一本柱列塀に変えました。
政庁東門

これより先は秋田城跡で最も重要な政庁内となります。
正殿跡

定期的に貢物を持って訪れる蝦夷の人々を迎え、味方に引き入れる目的で位階や布などを与えたり、宴を催したりしていました。
外国からの使節を迎えての儀式も行われていたと考えられています。
駐車場とトイレ

外郭東門沿いの道路反対側にあります。
駐車場付近

現在も発掘調査はつづく。
平成28年7月17日登城
 | 続日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ特別編集) |
| 公益財団法人 日本城郭協会 | |
| 学研プラス |