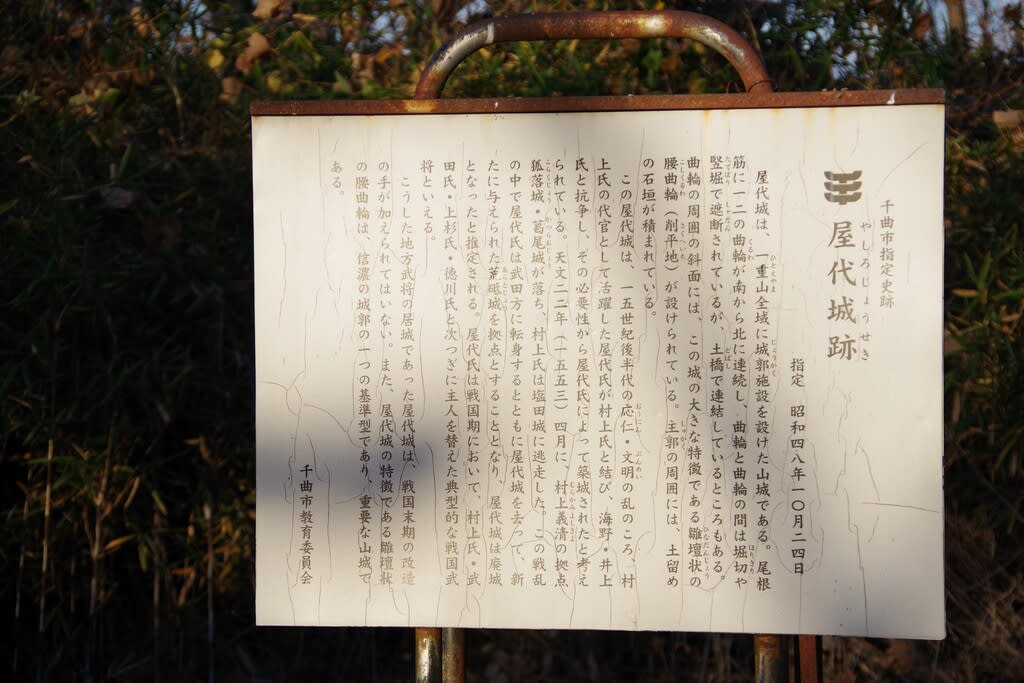【七里の渡し】しちりのわたし
【別名】熱田の渡し・宮の渡し・間遠の渡し
【構造】海上路
【年代】1616年(元和2年)
【指定史跡】県指定史跡
【場所】 地図
地図

東海道の熱田・宮の渡しから海上七里を3~4時間船に乗り、桑名の渡しに到着し、
このことから「七里の渡」と呼ばれ、東海道の42番目の宿場町として大賑わっていました。
ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています。
東海道

ここは東海道五十三次で知られる桑名宿の渡船場です。
伊勢国の東の玄関口として位置付けられています。
防波堤

ここから外は揖斐川で船着き場にもなっています。
蟠龍櫓

蟠龍櫓の2階展望室が無料開放されており、桑名城のことや蟠龍櫓、水門の管理など、知ることが出来ます。
そこに居る係員さんが、尾張との境ある揖斐川・長良川・木曽川の「木曽三川」とここから見える山々の話や、
桑名は関西弁ですが、川の向こうの名古屋は名古屋弁で言葉の文化が大きく異なっているという
話をしてくださいました。
そして、屋根の上には蟠龍瓦(七里の渡し廻船の航海安全の守護神)が載っているので見つけてみて下さい。
水門

ここから見える揖斐川の水門の管理もここでされているとのことです。
川の水量の調整や管理をされているそうです。
ちなみにこの櫓は、観光用の建物ではなく国土交通省水門統合管理所(1階)なのです。
本多忠勝像

隣接する九華公園には、桑名城と桑名城下町を建設した本多忠勝の銅像があります。

水堀を使って場内にも通じていました。
当時の石垣も残っています。
令和2年7月25日訪問
【別名】熱田の渡し・宮の渡し・間遠の渡し
【構造】海上路
【年代】1616年(元和2年)
【指定史跡】県指定史跡
【場所】
 地図
地図
東海道の熱田・宮の渡しから海上七里を3~4時間船に乗り、桑名の渡しに到着し、
このことから「七里の渡」と呼ばれ、東海道の42番目の宿場町として大賑わっていました。
ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています。
東海道

ここは東海道五十三次で知られる桑名宿の渡船場です。
伊勢国の東の玄関口として位置付けられています。
防波堤

ここから外は揖斐川で船着き場にもなっています。
蟠龍櫓

蟠龍櫓の2階展望室が無料開放されており、桑名城のことや蟠龍櫓、水門の管理など、知ることが出来ます。
そこに居る係員さんが、尾張との境ある揖斐川・長良川・木曽川の「木曽三川」とここから見える山々の話や、
桑名は関西弁ですが、川の向こうの名古屋は名古屋弁で言葉の文化が大きく異なっているという
話をしてくださいました。
そして、屋根の上には蟠龍瓦(七里の渡し廻船の航海安全の守護神)が載っているので見つけてみて下さい。
水門

ここから見える揖斐川の水門の管理もここでされているとのことです。
川の水量の調整や管理をされているそうです。
ちなみにこの櫓は、観光用の建物ではなく国土交通省水門統合管理所(1階)なのです。
本多忠勝像

隣接する九華公園には、桑名城と桑名城下町を建設した本多忠勝の銅像があります。

水堀を使って場内にも通じていました。
当時の石垣も残っています。
令和2年7月25日訪問