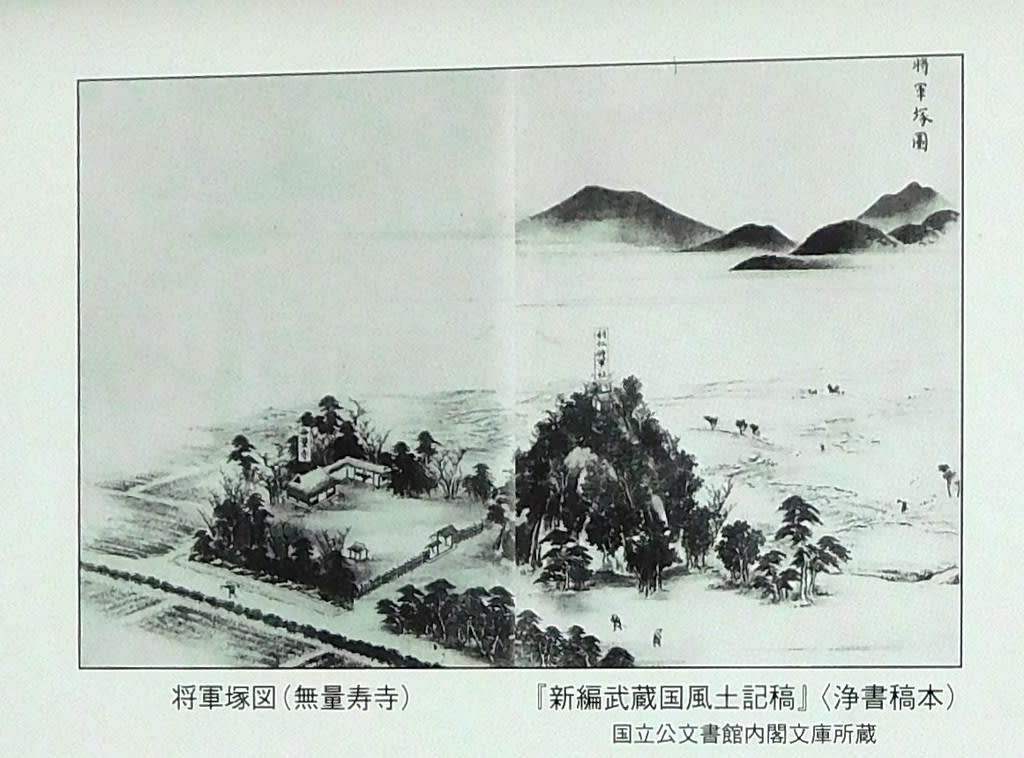【 新発田城 】しばたじょう
【 別名 】菖蒲城・舟形城・狐尾曳ノ城
【 構造 】平城
【 築城者 】新発田氏
【 築城年代 】鎌倉初期
【 指定史跡 】国重要文化財
【 場所 】発田市大手町6 地図
地図
【 スタンプ設置場所 】新発田城表門・新発田市役所本庁舎1階受付(12~3月)土、日、祝日、年末年始は警備員室
【城郭検定】出題あり

三方入母屋の丁字形の屋根に3匹の鯱を載せた御三階櫓が特徴の新発田城。
現在は陸上自衛隊駐屯地になっているため内部に入ることは出来ないのですが
2004年に辰巳櫓と同時に木造で再建され、本丸表門と旧二の丸隅櫓が現存として
残されています。
旧二の丸跡

旧二の丸跡に駐車場とトイレが完備されています。
前回、今回ともにこちらの駐車場を利用して散策しました。
日本百名城碑

ここが新発田城の代表的な撮影ポイントとなる場所です。
日本百名城選定を記念して立てられた碑と新発田城祉碑が並び御三階櫓と一緒に
撮影出来るスポットとなっています。
御三階櫓

新発田城だけに見られる丁字の屋根に3匹の鯱。
海鼠壁の壁面は寒冷地では耐久性があるため採用されています。
見た目にも美しい。
T字の屋根と3匹の鯱

丁字型の屋根に3匹の鯱が載る特徴的な櫓で、攻め入った敵を鯱の位置で方向を惑わす役割があったとされます。
真ん中の後ろを向いているのがメスの鯱で左右の2匹はオスの鯱です。
二ノ丸隅櫓

こちらも海鼠壁の壁面で、白と黒のコントラストが目を惹きます。
土橋門跡

ここにはかつて土橋門があり、その先は帯曲輪に入り本丸表門へ。
番所も置かれていました。
堀部安兵衛像

帯曲輪内にある忠臣蔵で有名な堀部安兵衛の銅像。
堀部安兵衛は新発田の生れで新発田藩士の中山安兵衛の息子です。
母方の祖母は藩祖溝口秀勝の娘であったこともありここに銅像が建てられています。
本丸表門

前回訪れた時と変わらぬ佇まいです。
そして変わらぬ堀の水の色は濃い緑…^^;
スタンプ設置場所

本丸表門のガイドさんの常駐する場所に日本100名城のスタンプが設置されています。
こちらでパンフレットをいただき、新発田城に関してのお話しもしてくれました。
脇に置かれた鯱は御三階櫓に載っているものと同じもので、駐屯地敷地内に入れないので
近くで見ることができないため、こちらで見られるように同じものを展示しているとのことです。

ここから柱を見ると修理をしたことがはっきりわかります。
下は修理した部分で上の柱や梁は江戸時代の頃のままの柱です。

最初に城を築いたのは新発田氏であり時期はよくわかっていないのですが鎌倉時代のようです。
御館の乱の論功行賞で恩賞が与えられなかったことに不満であった新発田重家は
上杉景勝に対して反乱を起こし、景勝方の攻勢により新発田城は落城したという話を
暑い中、この場所で受付の方が熱弁してくださいました。

本丸表門の内部も見学できるようになっているので覗いてみましょう!
本丸表門内部

現存らしい歳月を経た木材から重みを感じます。
石落し

下を通過する人を狙い撃ちしてみたくなるのですが。
展示用にガラスやアクリル板がはまっていたりはしないので、こちらは締切になっています。
溝口秀勝像

初代新発田藩主の溝口秀勝の銅像です。
新発田藩は初代から12代の明治時代まで取り潰されることなく溝口氏が統治しました。
そして、270年間一度も改易や転封もなく続いた数少ない藩の一つです。

辰巳櫓へ。
辰巳櫓

木造の二層二階櫓で、入母屋造りの本瓦葺きです。
一階

展示室になっています。
礎石

ガラス張りの床を覗き込むと礎石が見えます。
ここからは全部で11個の礎石がみつかっていますが、なぜか北西隅にあったであろう
礎石1つがみつかっていません。
全部で12個あったであろう礎石の上には2階まで続く通し柱が建っていたものと思われます。
石落し

新発田城で石落しが設置されている建物は新たに復元されたここと、見学することは出来ないのですが
御三階櫓の他に、現存である本丸表門櫓に設置されていたようです。
辰巳櫓と御三階櫓は石垣を登って来る敵に対しての攻撃用に出来ていて水堀に張り出しています。
階段

急とはいえ、登りやすい階段です。
二階

二階は瓦と棟札の展示がされています。
棟札

棟札には城主として市長の名前が記されています。
その両脇には署名箱が置かれていて、その中には三階櫓と辰巳櫓の復元を願い署名(3万余り)が
収められています。
陸上自衛隊新発田駐屯地

少し高い所に上がると塀の向こうの陸上自衛隊新発田駐屯地の様子が見えます。
明治時代に政府は新潟に歩兵第8大隊を配備することにしたのですが、
部隊を容れられる施設がなかったため、しばらく新発田城を営所としました。
しかし、新潟営所が不適という理由で結局新潟を引き払って群馬県の高崎に移ることになり
その一部である第2中隊が新発田城に入ることになりました。
その後第2中隊は大隊になり敗戦まで続き、今も陸上自衛隊新発田駐屯地として
使用されています。

御三階櫓が陸上自衛隊新発田駐屯地の敷地内に見えます。
いつか三階櫓も見られるようになるといいなあ。
石垣内部構造

辰巳櫓の麓に石垣内部構造の紹介がされています。
新発田城で使われている石垣の石の特徴や積み方が記してあり、表現されています。

旧二の丸隅櫓を見に行ってみましょう。
この場所はかつて本丸鉄砲櫓があった場所です。
もともと二の丸北部にあった隅櫓を昭和34年に解体して翌年この地に
移築したものです。
旧二の丸隅櫓

「なまこ壁」は、平瓦を並べ瓦の継ぎ目に漆喰を盛り付けて塗った壁のことで、
漆喰部分の盛り上がりがなまこに似ていることから「なまこ壁」という名前がつきました。
「なまこ壁」が間近で見られるポイントでもあるので見てみましょう。
一階

移築されたこの櫓は寛文8年の大火後に再建されたもので
江戸時代からの建物として今に残されています。
区切りはわかりずらいですが、柱の外側は武者走りになっています。
二階

解体修理を経て移築されたもので、辰巳櫓の新しい木材とは違い
年期の入った温かみのある材木でああることがわかります。

上の屋根から落ちて来る雪や氷で丸瓦が破損しないように瓦の上に瓦を敷いています。
雪国で見られる屋根の光景です。
辰巳櫓

前回訪れた時にはこちら側からのアングルで撮影してなかったので
周り込んでみました。
旧新発田藩足軽長屋

城郭検定の問題にもなっていた旧新発田藩足軽長屋にも足を延してみました。
かつては100軒ほどあった足軽長屋も、現在はここだけになってしまいました。
とても風情のある通りなので涼しい時期に散歩に訪れるといいなあと思いました。
6年前に訪れたまま、ほとんど何も変わっていませんでした。
現状維持が続いているのですね。
6年も経てば、どこか手入れがされて変化が見られる事のほうが多いのですが
時が止まっていたかのような気分でした。
前回私は建物内に入ってなかったので、今回は門と櫓をしっかりと見て来ることが出来ました。
そして、別の角度から写真に収めたり悔いなく見て回ることが出来ました。
平成24年9月22日登城
平成30年7月21日再登城
【 別名 】菖蒲城・舟形城・狐尾曳ノ城
【 構造 】平城
【 築城者 】新発田氏
【 築城年代 】鎌倉初期
【 指定史跡 】国重要文化財
【 場所 】発田市大手町6
 地図
地図【 スタンプ設置場所 】新発田城表門・新発田市役所本庁舎1階受付(12~3月)土、日、祝日、年末年始は警備員室
【城郭検定】出題あり

三方入母屋の丁字形の屋根に3匹の鯱を載せた御三階櫓が特徴の新発田城。
現在は陸上自衛隊駐屯地になっているため内部に入ることは出来ないのですが
2004年に辰巳櫓と同時に木造で再建され、本丸表門と旧二の丸隅櫓が現存として
残されています。
旧二の丸跡

旧二の丸跡に駐車場とトイレが完備されています。
前回、今回ともにこちらの駐車場を利用して散策しました。
日本百名城碑

ここが新発田城の代表的な撮影ポイントとなる場所です。
日本百名城選定を記念して立てられた碑と新発田城祉碑が並び御三階櫓と一緒に
撮影出来るスポットとなっています。
御三階櫓

新発田城だけに見られる丁字の屋根に3匹の鯱。
海鼠壁の壁面は寒冷地では耐久性があるため採用されています。
見た目にも美しい。
T字の屋根と3匹の鯱

丁字型の屋根に3匹の鯱が載る特徴的な櫓で、攻め入った敵を鯱の位置で方向を惑わす役割があったとされます。
真ん中の後ろを向いているのがメスの鯱で左右の2匹はオスの鯱です。
二ノ丸隅櫓

こちらも海鼠壁の壁面で、白と黒のコントラストが目を惹きます。
土橋門跡

ここにはかつて土橋門があり、その先は帯曲輪に入り本丸表門へ。
番所も置かれていました。
堀部安兵衛像

帯曲輪内にある忠臣蔵で有名な堀部安兵衛の銅像。
堀部安兵衛は新発田の生れで新発田藩士の中山安兵衛の息子です。
母方の祖母は藩祖溝口秀勝の娘であったこともありここに銅像が建てられています。
本丸表門

前回訪れた時と変わらぬ佇まいです。
そして変わらぬ堀の水の色は濃い緑…^^;
スタンプ設置場所

本丸表門のガイドさんの常駐する場所に日本100名城のスタンプが設置されています。
こちらでパンフレットをいただき、新発田城に関してのお話しもしてくれました。
脇に置かれた鯱は御三階櫓に載っているものと同じもので、駐屯地敷地内に入れないので
近くで見ることができないため、こちらで見られるように同じものを展示しているとのことです。

ここから柱を見ると修理をしたことがはっきりわかります。
下は修理した部分で上の柱や梁は江戸時代の頃のままの柱です。

最初に城を築いたのは新発田氏であり時期はよくわかっていないのですが鎌倉時代のようです。
御館の乱の論功行賞で恩賞が与えられなかったことに不満であった新発田重家は
上杉景勝に対して反乱を起こし、景勝方の攻勢により新発田城は落城したという話を
暑い中、この場所で受付の方が熱弁してくださいました。

本丸表門の内部も見学できるようになっているので覗いてみましょう!
本丸表門内部

現存らしい歳月を経た木材から重みを感じます。
石落し

下を通過する人を狙い撃ちしてみたくなるのですが。
展示用にガラスやアクリル板がはまっていたりはしないので、こちらは締切になっています。
溝口秀勝像

初代新発田藩主の溝口秀勝の銅像です。
新発田藩は初代から12代の明治時代まで取り潰されることなく溝口氏が統治しました。
そして、270年間一度も改易や転封もなく続いた数少ない藩の一つです。

辰巳櫓へ。
辰巳櫓

木造の二層二階櫓で、入母屋造りの本瓦葺きです。
一階

展示室になっています。
礎石

ガラス張りの床を覗き込むと礎石が見えます。
ここからは全部で11個の礎石がみつかっていますが、なぜか北西隅にあったであろう
礎石1つがみつかっていません。
全部で12個あったであろう礎石の上には2階まで続く通し柱が建っていたものと思われます。
石落し

新発田城で石落しが設置されている建物は新たに復元されたここと、見学することは出来ないのですが
御三階櫓の他に、現存である本丸表門櫓に設置されていたようです。
辰巳櫓と御三階櫓は石垣を登って来る敵に対しての攻撃用に出来ていて水堀に張り出しています。
階段

急とはいえ、登りやすい階段です。
二階

二階は瓦と棟札の展示がされています。
棟札

棟札には城主として市長の名前が記されています。
その両脇には署名箱が置かれていて、その中には三階櫓と辰巳櫓の復元を願い署名(3万余り)が
収められています。
陸上自衛隊新発田駐屯地

少し高い所に上がると塀の向こうの陸上自衛隊新発田駐屯地の様子が見えます。
明治時代に政府は新潟に歩兵第8大隊を配備することにしたのですが、
部隊を容れられる施設がなかったため、しばらく新発田城を営所としました。
しかし、新潟営所が不適という理由で結局新潟を引き払って群馬県の高崎に移ることになり
その一部である第2中隊が新発田城に入ることになりました。
その後第2中隊は大隊になり敗戦まで続き、今も陸上自衛隊新発田駐屯地として
使用されています。

御三階櫓が陸上自衛隊新発田駐屯地の敷地内に見えます。
いつか三階櫓も見られるようになるといいなあ。
石垣内部構造

辰巳櫓の麓に石垣内部構造の紹介がされています。
新発田城で使われている石垣の石の特徴や積み方が記してあり、表現されています。

旧二の丸隅櫓を見に行ってみましょう。
この場所はかつて本丸鉄砲櫓があった場所です。
もともと二の丸北部にあった隅櫓を昭和34年に解体して翌年この地に
移築したものです。
旧二の丸隅櫓

「なまこ壁」は、平瓦を並べ瓦の継ぎ目に漆喰を盛り付けて塗った壁のことで、
漆喰部分の盛り上がりがなまこに似ていることから「なまこ壁」という名前がつきました。
「なまこ壁」が間近で見られるポイントでもあるので見てみましょう。
一階

移築されたこの櫓は寛文8年の大火後に再建されたもので
江戸時代からの建物として今に残されています。
区切りはわかりずらいですが、柱の外側は武者走りになっています。
二階

解体修理を経て移築されたもので、辰巳櫓の新しい木材とは違い
年期の入った温かみのある材木でああることがわかります。

上の屋根から落ちて来る雪や氷で丸瓦が破損しないように瓦の上に瓦を敷いています。
雪国で見られる屋根の光景です。
辰巳櫓

前回訪れた時にはこちら側からのアングルで撮影してなかったので
周り込んでみました。
旧新発田藩足軽長屋

城郭検定の問題にもなっていた旧新発田藩足軽長屋にも足を延してみました。
かつては100軒ほどあった足軽長屋も、現在はここだけになってしまいました。
とても風情のある通りなので涼しい時期に散歩に訪れるといいなあと思いました。
6年前に訪れたまま、ほとんど何も変わっていませんでした。
現状維持が続いているのですね。
6年も経てば、どこか手入れがされて変化が見られる事のほうが多いのですが
時が止まっていたかのような気分でした。
前回私は建物内に入ってなかったので、今回は門と櫓をしっかりと見て来ることが出来ました。
そして、別の角度から写真に収めたり悔いなく見て回ることが出来ました。
平成24年9月22日登城
平成30年7月21日再登城
 | 日本100名城に行こう 公式スタンプ帳つき |
| 日本城郭協会 | |
| 学研プラス |





















 妙高温泉 石田館妙高ホテル
妙高温泉 石田館妙高ホテル