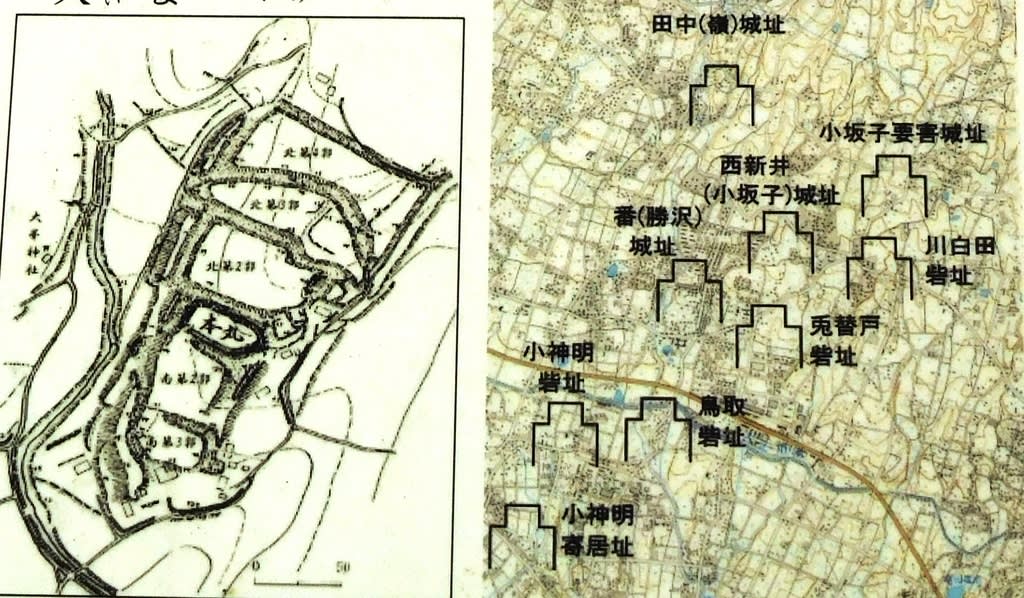山城サミットin佐野
11月25日(土)、26日(日)と山城サミットが開催されました。
そして26日(日)現地見学会だけは絶対に外せまい!と、はりきってやって来ました(*^▽^*)
無料シャトルバス

普段は車でレストハウス前の駐車場まで行けるのですが、この日は自家用車での乗り入れは
出来ないので特設大駐車場から無料シャトルバスにて唐沢山城跡へ。
レストハウス前

事前に申し込みをしていた「千田先生・宮武先生と主郭を歩く」現地見学会の受付時間待ちです。
普段ここは駐車場になっていますがいろいろなお店のテントが建ち並び、とても賑やかです。
現地見学会

出発前に先生方の紹介と唐沢山城についてのお話しです。

この高石垣は、安土桃山時代に築かれた豊臣方の石垣技術を導入して積まれた
関東地方には珍しい石垣です。
やはり、ここに来ると「凄~」と見上げてしまいます。
ここでの宮武先生の話も分かりやすくなるほど~な話が聞けました。
本丸虎口(二の丸側)

とにかく楽しそうに話しています。
きっとしゃべりたり足りなかったことでしょう。(^^;
(私も聞き足りなかったし。)
対談
千田先生、宮武先生による「全国の城を知る識者二人が唐沢山城を語りあう」のテーマで対談。
しかし、この二人の話は漫才のようで面白い。
これだけの人が二の丸に詰めるというのは天正時代以来か…(確かに)
鏡石の話であったり、虎口の本来の構造の話など
面白いだけでなく、ちゃんと「なるほど~」と言わせるだけの内容です。
武者行列

甲冑を持って随分遠くから参陣された方も居るようです。
紅葉

紅葉真っ只中です!
いっぱい写真を撮りたかったのですが、さすがにこの日は人、人、人で
ゆっくり撮影とはいきませんでした。
さのまる

さのまるも山城サミットバージョンでお出迎えです。
猫たち

この賑やかな中、猫ちゃんたちはどこ行ったのかな?と探してみると…
いました、いました(*^-^*)
唐沢山城は猫に会いに来る人もいっぱいいます。
私も今日は我が家の飼い猫まろんちゃんに銀のスプーン(キャットフード)をおすそ分けしてもらい、
持参して来ました!
売店のキャットフードも、1年前に来た時よりもバリエーションが増えてました。
現地見学会出発前に偶然、唐沢山城のARを作られたという方ともお話が出来ました。
(話に聞き入ってしまってうっかりお名前を伺い忘れてしまったのが残念。)
岩村城や高取城のARも手掛けた方だそうで、今度はぜひ岩村城のARも見に行ってみたいと
思います。
二日間とも訪れる予定だった山城サミット。
25日は色々なスケジュールが重なり行く事が出来ませんでした。
パネルディスカッションなども楽しみにしていたのに残念でしたが
次は12月のお城EXPOで山城の話も聞けると思うので我慢して、今度はそちらを楽しみに年末を
迎えたいと思います。
平成29年11月26日登城
11月25日(土)、26日(日)と山城サミットが開催されました。
そして26日(日)現地見学会だけは絶対に外せまい!と、はりきってやって来ました(*^▽^*)
無料シャトルバス

普段は車でレストハウス前の駐車場まで行けるのですが、この日は自家用車での乗り入れは
出来ないので特設大駐車場から無料シャトルバスにて唐沢山城跡へ。
レストハウス前

事前に申し込みをしていた「千田先生・宮武先生と主郭を歩く」現地見学会の受付時間待ちです。
普段ここは駐車場になっていますがいろいろなお店のテントが建ち並び、とても賑やかです。
現地見学会

出発前に先生方の紹介と唐沢山城についてのお話しです。

この高石垣は、安土桃山時代に築かれた豊臣方の石垣技術を導入して積まれた
関東地方には珍しい石垣です。
やはり、ここに来ると「凄~」と見上げてしまいます。
ここでの宮武先生の話も分かりやすくなるほど~な話が聞けました。
本丸虎口(二の丸側)

とにかく楽しそうに話しています。
きっとしゃべりたり足りなかったことでしょう。(^^;
(私も聞き足りなかったし。)
対談

千田先生、宮武先生による「全国の城を知る識者二人が唐沢山城を語りあう」のテーマで対談。
しかし、この二人の話は漫才のようで面白い。
これだけの人が二の丸に詰めるというのは天正時代以来か…(確かに)
鏡石の話であったり、虎口の本来の構造の話など
面白いだけでなく、ちゃんと「なるほど~」と言わせるだけの内容です。
武者行列

甲冑を持って随分遠くから参陣された方も居るようです。
紅葉

紅葉真っ只中です!
いっぱい写真を撮りたかったのですが、さすがにこの日は人、人、人で
ゆっくり撮影とはいきませんでした。
さのまる

さのまるも山城サミットバージョンでお出迎えです。
猫たち

この賑やかな中、猫ちゃんたちはどこ行ったのかな?と探してみると…
いました、いました(*^-^*)
唐沢山城は猫に会いに来る人もいっぱいいます。
私も今日は我が家の飼い猫まろんちゃんに銀のスプーン(キャットフード)をおすそ分けしてもらい、
持参して来ました!
売店のキャットフードも、1年前に来た時よりもバリエーションが増えてました。
現地見学会出発前に偶然、唐沢山城のARを作られたという方ともお話が出来ました。
(話に聞き入ってしまってうっかりお名前を伺い忘れてしまったのが残念。)
岩村城や高取城のARも手掛けた方だそうで、今度はぜひ岩村城のARも見に行ってみたいと
思います。
二日間とも訪れる予定だった山城サミット。
25日は色々なスケジュールが重なり行く事が出来ませんでした。
パネルディスカッションなども楽しみにしていたのに残念でしたが
次は12月のお城EXPOで山城の話も聞けると思うので我慢して、今度はそちらを楽しみに年末を
迎えたいと思います。
平成29年11月26日登城
 | ゆるキャラグランプリ2013年第1位!! さのまる キャンパス地トートバック「足あと」さのまる グッズ |
| クリエーター情報なし | |
| スクープクリエーション |








































 )
)