【舘山城】たてやまじょう
【別名】米沢城
【構造】平山城
【築城者】新田冠者経衡
【築城年代】15世紀頃
【指定史跡】国指定史跡
【場所】米沢市舘山町 地図
地図
【城郭検定】 出題あり

平成28年に国史跡に指定された舘山城で、最初は伊達政宗の父である
輝宗の家臣新田四郎義直の居城でした。
ところが輝宗への謀反を企てたとして新田氏は切腹を命じられ、
以後、舘山城は伊達家の城となりました。
やがて輝宗が政宗に家督を譲り、舘山城を隠居城とし普請を始め完成しましたが、
移り住んだその年の10月に非業の死を遂げています。
その後政宗は、豊臣秀吉の奥羽仕置で宮城県へ移るまで
この城で過ごしていたものと考えられています。
駐車場

東館にある駐車場。
ここには話題の「私有地に付 立ち入り大歓迎」のありがた~い標柱があります。
東館

麓には二つの「御館」があり、こちらは東舘で
北側にも北館があり、東側には更に舘山平城とされる根小屋が広がっていました。
大正9年から稼働している発電所施設が城址に造られています。
井戸

生活の場として多くの井戸跡が残っています。
大手口

ここから本丸を目指すことになるのですが、
入口には登城者に親切な気遣いがされています。
案内小屋

大手口にある案内小屋には案内図などのチラシや休憩用の飲み水など設置されていて
無人ながらも有人並みのおもてなしで迎えています。
手前には山城にはつきもの?の杖も用意されています。
南虎口
道なりに大手道を登って行くとほどなく虎口が見えて来ます。
曲輪Ⅰ

広い曲輪が曲輪Ⅰです。
横に長くなっているので、まずは東の隅まで行ってみようと思います。
東端テラス

東の端、曲輪Ⅰの先端は曲輪Ⅰから1段下がったところに展望台のような役割をする
「曲輪Ⅰ東端テラス」と呼ばれる場所があります。
眼下には館が見渡せる立地となっています。
ちなみに、テラス部分は立ち入り禁止になっているのでご注意ください。
北虎口

北側の登城道があります。
この道を下ると北館に出て、往来するために造られた道になります。
貯水槽(井戸跡)

雨が降った直後のせいか井戸跡の窪みに水が溜っていて
井戸ありましたという主張をしています。

凸凹していてワクワクするようなものが見えて来ました。
かなり複雑な感じです。
枡形

この辺りには石垣が見えますが、破城跡ということで石垣の裏込め石が多く残っています。
大きい石垣の石は他に転用されているものと思われ、下の方の部分が少々残っている程度です。
枡形は綺麗に残っているので、見応えはあります。
石垣

二段程残る石垣は、周囲の裏込め石と想像を重ねると楽しくなってしまいます。
(ここまでくるともはや病気でしょうか^^;)
ちなみに、この辺りの石垣は、調査の結果石の加工の仕方から見て
関ヶ原の戦い以降の上杉景勝の時代に普請されたものと思われます。

この曲輪Ⅰと曲輪Ⅱを分ける堀跡を見ても分かるように、破城後に大量の栗石によって
石垣石も含めて埋められていたことが見えています。
曲輪Ⅱ

現在は浅くなってしまっている堀から、西に見える大きな土塁までが曲輪Ⅱになります。
西からの進入に対しては、大きな堀切と大きな土塁で防御しています。
土塁

土塁を登るのに、まるで山を登るかのようです。
ここから下を見ると急な崖と川が見えて怖いです。
南の川側からはとても攻め入ることは出来そうにありません。
石碑

1819年(文政2年)8月の銘が刻まれた弁財天の石碑がと石祠があります。
土塁は北まで続いていて、土塁上を歩けるようになっていますが、
途中の大きな松の木に蜂の巣があり、危険なので中頃で引き返して来ました。
縦堀
北虎口

こちらが搦め手からの虎口になります。
横堀状帯曲輪

南側は急勾配と川に守られているので、北側の守りは
堀や土塁などで駆使して竪掘、横堀、帯郭を連続させるなどの工夫をしています。
搦手と堀切

曲輪Ⅱと曲輪Ⅲの間の堀切です。
ここの堀切は南に行くほど深く、高く見事な堀切になっています。
導水路

堀切を利用して?造られている導水路は東京電力の管理下にあるので立ち入り禁止です。
登って落ちたら大変なことになりそう
ということで、一応橋も注意しながら慎重に渡りました。
土橋
曲輪Ⅲと廃寺跡との間の堀切を渡る土橋があります。
正面の藪が廃寺跡になり、とてもそちらは入れそうもないので進入断念です。
曲輪Ⅲ

舘山城では小規模な曲輪になっています。
平場の南側にはちょっとこんもりとした塚があります。
塚(修法壇)

中世に営まれた祈祷や修法などのために造られた土壇です。
木製のものであったり、ここでは土を盛って造られたものであったり
するようですが、ここでは土壇だったようですね。
とはいうものの、資料がなければ見てもまったく分からないです^^;

更に登って、物見台を見に行ってみようと思います。
ここを登っていると、大きな堀切と、対岸(曲輪Ⅱ)の土塁が良く見えます。
物見台

舘山城で一番高い所に位置します。
ここには江戸時代の石祠と思われる「山の神」が祀られています。
これにて、下って館跡へ。。。

この先はかつて木橋が架かり、米陽八景のひとつとして
元禄期の絵が残されています。
向い側にも橋が架かっていた跡が残っています。

橋が架かっていたことや、東館に数軒の家屋があったことも描かれています。
北館駐車場

北館へやって来ました。
こちらにも駐車場があり、北館跡と、曲輪Ⅰへ向かう登城路があります。
ここから登城すると前記にあった北虎口に出ます。
北館

土塁もかすかに残っていて、館跡の名残が見てとれます。
到着した時は雨が降っていたので、一旦米沢城を散策して
雨が上がってから出直して登城しました。
国指定史跡になった頃からとても気になっていたので雪が降る前に
行っておかなくちゃ!と秋を狙ってやって来ました。
気軽にアクセス出来て、楽しめる城址です。
保存会の気合の入れ方もすばらしく、訪れる側は感謝です。
今後もぜひ維持してほしいので頑張って!のエールを送りたいと思います。
令和元年10月27日登城
今回の参考本
【別名】米沢城
【構造】平山城
【築城者】新田冠者経衡
【築城年代】15世紀頃
【指定史跡】国指定史跡
【場所】米沢市舘山町
 地図
地図【城郭検定】 出題あり

平成28年に国史跡に指定された舘山城で、最初は伊達政宗の父である
輝宗の家臣新田四郎義直の居城でした。
ところが輝宗への謀反を企てたとして新田氏は切腹を命じられ、
以後、舘山城は伊達家の城となりました。
やがて輝宗が政宗に家督を譲り、舘山城を隠居城とし普請を始め完成しましたが、
移り住んだその年の10月に非業の死を遂げています。
その後政宗は、豊臣秀吉の奥羽仕置で宮城県へ移るまで
この城で過ごしていたものと考えられています。
駐車場

東館にある駐車場。
ここには話題の「私有地に付 立ち入り大歓迎」のありがた~い標柱があります。
東館

麓には二つの「御館」があり、こちらは東舘で
北側にも北館があり、東側には更に舘山平城とされる根小屋が広がっていました。
大正9年から稼働している発電所施設が城址に造られています。
井戸

生活の場として多くの井戸跡が残っています。
大手口

ここから本丸を目指すことになるのですが、
入口には登城者に親切な気遣いがされています。
案内小屋

大手口にある案内小屋には案内図などのチラシや休憩用の飲み水など設置されていて
無人ながらも有人並みのおもてなしで迎えています。
手前には山城にはつきもの?の杖も用意されています。
南虎口

道なりに大手道を登って行くとほどなく虎口が見えて来ます。
曲輪Ⅰ

広い曲輪が曲輪Ⅰです。
横に長くなっているので、まずは東の隅まで行ってみようと思います。
東端テラス

東の端、曲輪Ⅰの先端は曲輪Ⅰから1段下がったところに展望台のような役割をする
「曲輪Ⅰ東端テラス」と呼ばれる場所があります。
眼下には館が見渡せる立地となっています。
ちなみに、テラス部分は立ち入り禁止になっているのでご注意ください。
北虎口

北側の登城道があります。
この道を下ると北館に出て、往来するために造られた道になります。
貯水槽(井戸跡)

雨が降った直後のせいか井戸跡の窪みに水が溜っていて
井戸ありましたという主張をしています。

凸凹していてワクワクするようなものが見えて来ました。
かなり複雑な感じです。
枡形

この辺りには石垣が見えますが、破城跡ということで石垣の裏込め石が多く残っています。
大きい石垣の石は他に転用されているものと思われ、下の方の部分が少々残っている程度です。
枡形は綺麗に残っているので、見応えはあります。
石垣

二段程残る石垣は、周囲の裏込め石と想像を重ねると楽しくなってしまいます。
(ここまでくるともはや病気でしょうか^^;)
ちなみに、この辺りの石垣は、調査の結果石の加工の仕方から見て
関ヶ原の戦い以降の上杉景勝の時代に普請されたものと思われます。

この曲輪Ⅰと曲輪Ⅱを分ける堀跡を見ても分かるように、破城後に大量の栗石によって
石垣石も含めて埋められていたことが見えています。
曲輪Ⅱ

現在は浅くなってしまっている堀から、西に見える大きな土塁までが曲輪Ⅱになります。
西からの進入に対しては、大きな堀切と大きな土塁で防御しています。
土塁

土塁を登るのに、まるで山を登るかのようです。
ここから下を見ると急な崖と川が見えて怖いです。
南の川側からはとても攻め入ることは出来そうにありません。
石碑

1819年(文政2年)8月の銘が刻まれた弁財天の石碑がと石祠があります。
土塁は北まで続いていて、土塁上を歩けるようになっていますが、
途中の大きな松の木に蜂の巣があり、危険なので中頃で引き返して来ました。
縦堀

北虎口

こちらが搦め手からの虎口になります。
横堀状帯曲輪

南側は急勾配と川に守られているので、北側の守りは
堀や土塁などで駆使して竪掘、横堀、帯郭を連続させるなどの工夫をしています。
搦手と堀切

曲輪Ⅱと曲輪Ⅲの間の堀切です。
ここの堀切は南に行くほど深く、高く見事な堀切になっています。
導水路

堀切を利用して?造られている導水路は東京電力の管理下にあるので立ち入り禁止です。
登って落ちたら大変なことになりそう

ということで、一応橋も注意しながら慎重に渡りました。
土橋

曲輪Ⅲと廃寺跡との間の堀切を渡る土橋があります。
正面の藪が廃寺跡になり、とてもそちらは入れそうもないので進入断念です。
曲輪Ⅲ

舘山城では小規模な曲輪になっています。
平場の南側にはちょっとこんもりとした塚があります。
塚(修法壇)

中世に営まれた祈祷や修法などのために造られた土壇です。
木製のものであったり、ここでは土を盛って造られたものであったり
するようですが、ここでは土壇だったようですね。
とはいうものの、資料がなければ見てもまったく分からないです^^;

更に登って、物見台を見に行ってみようと思います。
ここを登っていると、大きな堀切と、対岸(曲輪Ⅱ)の土塁が良く見えます。
物見台

舘山城で一番高い所に位置します。
ここには江戸時代の石祠と思われる「山の神」が祀られています。
これにて、下って館跡へ。。。

この先はかつて木橋が架かり、米陽八景のひとつとして
元禄期の絵が残されています。
向い側にも橋が架かっていた跡が残っています。

橋が架かっていたことや、東館に数軒の家屋があったことも描かれています。
北館駐車場

北館へやって来ました。
こちらにも駐車場があり、北館跡と、曲輪Ⅰへ向かう登城路があります。
ここから登城すると前記にあった北虎口に出ます。
北館

土塁もかすかに残っていて、館跡の名残が見てとれます。
到着した時は雨が降っていたので、一旦米沢城を散策して
雨が上がってから出直して登城しました。
国指定史跡になった頃からとても気になっていたので雪が降る前に
行っておかなくちゃ!と秋を狙ってやって来ました。
気軽にアクセス出来て、楽しめる城址です。
保存会の気合の入れ方もすばらしく、訪れる側は感謝です。
今後もぜひ維持してほしいので頑張って!のエールを送りたいと思います。
令和元年10月27日登城
今回の参考本
 | 東北の名城を歩く 南東北編: 宮城・福島・山形 |
| 飯村 均,室野 秀文 | |
| 吉川弘文館 |





















 というほうが
というほうが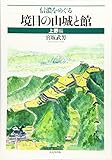

















 」となります。
」となります。































































