
自分の「気付き」の備忘録です。理論的に矛盾が有るやも知れませんがご了承の程を。間違いが見付かったら、今後書き直したり加筆するかもです。

それは、Key of CでトニックのCMaj7でワザとIonianではなくLydianを使って♯11を響かせるのと同じ役割を並行調のトニック・マイナーでも担ってる…という感覚、つまりスケールから考えた結果、本来とは微妙に異なるスケールを使う事で「浮遊している」と感じていたのだと思います。



ちゃんとそれらしき事も書いてました。学生時代からかなり時間も経つので、どの知識を何処で仕入れたか、さっぱり覚えてません。下手したら「俺が思い付いたんだ!オレって天才!」って思い込んでるコンセプトも有るかも(笑)


自分は、こういう発見の為にプロミュージシャンになったんだと思います。大学4年間である程度勉強はしましたが、とても足りない…と思ったので。これが、社会のお役に立てるとは到底思えませんが(笑)、今後も霞を食って生きてる様な研究人生を歩んでいければ…と思います。
先日、久々にコルトレーンの「impressions」を聴いてて、ソロ中に強調してるかの様に聴こえるminorコード上のMaj6thの音がとても明るく聴こえて、自己分析してました。Dminで言うところのB音です。
通常、トニック・マイナーで使うスケールはAeolianかメロディック・マイナーですが、モード曲はコードを指定せず、「D Dorian」という具合に表記し、「基本、スケールもボイシングもドリアン使ってね。」っていう緩い約束事をするのですが、一応、ルートから考えるとDorianの曲はマイナー系となります。僕にとって、その中の6thの音って「浮遊サウンド」ってイメージでした。
通常、トニック・マイナーで使うスケールはAeolianかメロディック・マイナーですが、モード曲はコードを指定せず、「D Dorian」という具合に表記し、「基本、スケールもボイシングもドリアン使ってね。」っていう緩い約束事をするのですが、一応、ルートから考えるとDorianの曲はマイナー系となります。僕にとって、その中の6thの音って「浮遊サウンド」ってイメージでした。
以下、分かりやすくCのキーで書きます。

それは、Key of CでトニックのCMaj7でワザとIonianではなくLydianを使って♯11を響かせるのと同じ役割を並行調のトニック・マイナーでも担ってる…という感覚、つまりスケールから考えた結果、本来とは微妙に異なるスケールを使う事で「浮遊している」と感じていたのだと思います。
それが、クール・ジャズなど、モード以前の音楽を聴きまくった結果、違う風に聴こえた様です。

トニック・マイナーのAm7(注:メロディック・マイナーが使いやすい様に7thは度々外されます)上で、6th音を伸ばすとb7thの音と半音でぶつかる(このキーではF♯とG)ので、バークリーでは「Avoid Note」と習いました。なので、この音が故意に伸ばされてると、なんだか違うコードに聴こえ、結局は明るいBluesでも聴いてる様な感覚になって来ました(笑)。無理矢理コードにすると、D7/A…という事になるでしょうか。
AドリアンをD7と考える…という、この解釈は僕もずっと昔からやっていて、生徒にも教えてますが、あくまで理論的解釈で、「そうやると使える音の可能性が広がる」という、単純に知識からの応用であり、今回の様にサウンドが身に染みて明るく感じたのは初めての経験で驚いてます。

そう言えば、こんな本持ってたな…と紐解くと、、、

ちゃんとそれらしき事も書いてました。学生時代からかなり時間も経つので、どの知識を何処で仕入れたか、さっぱり覚えてません。下手したら「俺が思い付いたんだ!オレって天才!」って思い込んでるコンセプトも有るかも(笑)
で、その流れでTension Noteについて改めて考えてみました。
毎朝、イヤトレやソルフェージュの練習をしてるのですが、自分の耳癖として、倍音(主に5度上の音)ばかり聴き取ってる…というのを、最近つくづく実感しています。特に低音や高音は倍音ばかり聴こえて惑わされます。教会の鐘の音や学校のチャイムなど、倍音ばかり聴こえてまともなメロディーに聴こえなくて吐きそうになる時が有ります。
そのクセ、ジャズではあまり倍音を気にせずやって来ました。が、よくよく考えるとコードやテンションて、倍音から成り立ってるのですよね(今更かよ笑)。

5thはRootの倍音(perfect 5th)、7thは3rdの、Tension9thは5thの、T♯11thは7thの、T13thはT9thの、T♯15thはT♯11thの…とそれぞれが倍音の関係として成立しているし、コードやテンションを弾く事で既に倍音として何となく耳にしているから自然に聴こえるわけです。
ところが、C7の様なコードのテンションは、僕にとってはそう言う風に自然な倍音の響きとして聴こえません。特にC7(♯11)ってのは長年しっくり来ません。ずっと使ってるけど。

ご覧の通り倍音(perfect 5th)の関係ではないので、Blue Noteのb5として捉えた方がしっくり来ます。♯9thってテンションも全く同じで、どちらかと言うとb3rdという感じ。僕のBlue Noteの解釈は、黒人教会で明るい歌で死者を弔ってるのに、泣いちゃって音程がフラットしちゃった…を楽器で再現したものと捉えてます。元々アフリカの民族音楽にBlue Note Scaleに似た音階が有る…など諸説有りますが、なんかそれだとしっくり来ないし。
話は逸れましたが、そんな僕が若い頃大好きだったコードがSus4です。それは、b7thの倍音の4thの音が3rdの代わりにあるから、響きが綺麗なのとパワフルだからだと思います。ま、5度インターバルだけ鳴らせばロックで言うところの「パワー・コード」ですからね。
結構、自分は純粋な「倍音の響き」が好きだったんだなぁ…という事が今更ながら分かり、自身でとても驚いています。まぁ、アドリブはそんな事無視して複雑怪奇な事やるんですけど(笑)
自分は、こういう発見の為にプロミュージシャンになったんだと思います。大学4年間である程度勉強はしましたが、とても足りない…と思ったので。これが、社会のお役に立てるとは到底思えませんが(笑)、今後も霞を食って生きてる様な研究人生を歩んでいければ…と思います。
因みに譜面は、僕の元生徒さんでSEの方が開発した「Blue Notation」というアプリを使いました。PC開いてFinaleで譜面書いて…って超面倒な事せずとも、スマホで寝っ転がってこの記事書けたので、超感謝‼︎










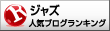

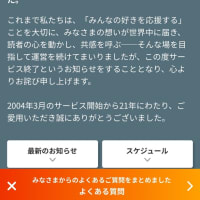







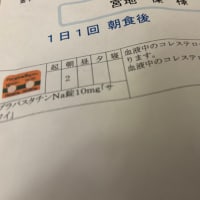







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます