
今、アート・ペッパーの自叙伝「ストレート・ライフ」を読んでいる。
愛情の薄い両親(主に母親)や祖母に育てられた寂しい生い立ちから、楽器との出会いや、ホームタウンでスタートさせたミュージシャン生活など、リアルに情景を思い浮かべながら読む事が出来る。
ホームタウンは白人黒人の区別無く、誰もが気さくで楽しかったとペッパーは懐古している。しかし、それから何年も経ち、久しぶりに初期の雇い主であるベニー・カーターのライブ会場に遊びに行った時、1階席は黒人達で埋まっており、白人は2階席に集められていたと言う(映画「バード」でもそんなシーンが有った。) 。どうしてもかつてのボスに挨拶がしたいと1階席に降りて行くと、黒人達に囲まれて、「何しに来やがった!」などと口々に相当脅されたらしい。
ペッパーの言葉の中に「黒人というだけで、ろくに演奏も出来ない奴が持て囃されるのには我慢ならない。」みたいな言葉が出て来るのには、業界で受けて来た逆差別に対する憤りが滲み出ているのを強く感じる。
読んでて辛かったのは自分のバンドに率先して黒人を使ってたのに、ライブで客の一人に「おい、バンドの連中がお前の悪口言ってたぞ!」と言われ、メンバーの一人ローレンス・マラブルを問い詰めると、「白人野郎になんかジャズは出来ねぇよ!あんなのはジャズじゃねぇ。俺達がお前らと演るのはお前らを利用してるだけだ。」と言い返されたと言う。涙が出る程とてもショックだったと言っているが、読んでる僕も胸が痛くなった。

(そのメンバー達が演奏している名盤。素晴らしいアルバムなので、その話を読んでガッカリしてしまった。)
一方でスティットやレイ・ブラウンは優しかったし、コルトレーンはとても温かい人間だったと振り返っているので、結局は同じ黒人でも人によるという事だ。因みに、スタン・ゲッツはテクは抜群だけど感動した事が無い…とある。この本の中ではゲッツの評価はかなり低い。
このクダリを読んで、自分のアメリカ生活を思い出した。僕は幸運にも、あまり差別を受けた事が無かったけど、それは周りに善良な人達が多かったからなんだと今は思える。
バークリーの学生時代に、ボストン郊外のボーリング場の駐車場で黒人の若者達に「おい、チンク(chink=中国人の蔑称)、とっとと失せろ!」と言われて、「俺達は日本人だ、馬鹿野郎!」と言い返したくらいの小さなイザコザは何度か有った。
当時(90年代初頭)のジャズ界もブラック・パワーに溢れていて、ウィントン・マルサリスが「元々ジャズは黒人の物だ。」と発言した事で、その影響を受けた若い黒人ミュージシャン達が黒人だけでバンドを組むのが流行ったし、それに憧れる日本人を始め非黒人ミュージシャンも多かったと思う。キース・ジャレットがそういうムーブメントを作ってるウィントンはレイシストだ…と批判したという情報も有った。(そう言えば、ウィントン一派のマーカス・ロバーツがキースを批判してた事も有ったっけな。) 僕がボストンで大変お世話になったタイガー大越氏も、尊敬するルイ・アームストロング・トリビュートのアルバムを制作する為に彼に助言求めると、「日本人がそんなアルバムを作らなくて良い。」と言われたそうだ。
僕の師匠のジェリー・バーガンジは、ピアノのマルグリュー・ミラーと素晴らしいライブ・アルバムを作ったのだが、マルグリューのマネージメントとは、先方の権利の主張や、数々の厳しい条件や制限等の話し合いでほとほと疲れ果て、「もう黒人ミュージシャンと演るのはうんざりだ…」と愚痴っていた。恐らく黒人同士で演るなら、そんな厳しい条件は出さなかったと思われる。
60年代のキング牧師やマルコムXの公民権運動ほどではないにしろ、90年代もそういうある種緊迫した空気感が有った。時代は流れ、今やウィントンも、すっかり気の良いオジサンって感じになり、人種の垣根など取っ払って才能さえ有れば、自分のプロジェクトにどんどん採用する様になった。恐らく、ブラックパワーにこだわる事がビジネス的にも人脈的にも最早何も利益をもたらさないって事に気が付いたのではないだろうか。それで、僕も漸く彼の演奏を素直に聴ける様になったのだ。あぁ、あの頃は若くてツッパってたのね…って感じで(笑) だから、何もここで蒸し返す必要も無いのだが、若かった僕にこれらの事象が物凄い影響をもたらした事は事実だ。
僕がバークリーを卒業して、NYに出る決心をした時、タイガーさんに言われた事で印象に残っている事が有る。「ジャズ・ミュージシャンが売れるのにはプライオリティーが有り、ダントツ1位は黒人の男、2位は白人の女…アジア人のフロント楽器なんて最下位も良いとこで中々売れないからね。」という言葉。僕はその後、それを実際に体験するわけだが、それでも売れた、そのタイガーさん、その前の穐吉さんや日野さんをはじめ、現在もアメリカで活躍している日本人は相当凄いって事だ。そういう肌の色のプライオリティーを押し除けて這い上がった訳だから。タイガーさんも相当苦労したからこそ出た言葉だったのだろうと思う。
僕が体験したあからさまな差別はストリート・ギグでだった。エブリン・ブレイキー(vo)のバンドに所属していたのだが、メンバーは殆ど黒人だったけど皆んなとても良い人達で、厳しかったけど僕に色々教えてくれた。ただ、たまに来る黒人のギターリストで、演奏は上手かったんだけど、嫌な奴がいた。挨拶しても無視するし、僕のソロでは一切バッキングもしない。見かねたドラマーが、「おい、気に入らない事が有るんなら、このブラザーに教えてやれよ!」と言うと、「コイツはブラザーなんかじゃねぇよ。」と言い返した。僕の目の前で言い合いになったので、エブリンに「頼むから、このギターをブックする時は俺をブックしない様にしてよ。それでいいだろ?」と言うしか無かった。
でも、それを除けば良い思い出ばかりだ。そのドラマーの人は当時50代半ばだったと思うけど、僕が良いプレイをしたら、演奏後駆け寄って来て、自分の腕と僕の腕を比べて「お前は、もうすっかりブラザーだよ。肌の色も随分近付いて来たんじゃないのか?」なんて笑いながら言ってくれてとても嬉しかった。バンドで人種的なことを言われた事は一切無い。有難い音楽的なお説教のみだ。
でも、バンド以外でも稼がなきゃならなかったので、ビレッジボイスの求人欄でサックス募集と有れば片っ端から電話した。オーディションまで辿り着けるとラッキーだけど、中々そうも行かず、ちょっとNYでもヤバい地域の電話番号にも勇気を持って掛けてみた。そしたら、明らかに黒人のディープな低い声で「お前、何人だ?あー?日本人?日本人は要らねーよ。」とガチャっと切られた。めっちゃ怖かった(笑)
多様性が当たり前の今の中堅や若手にこういう話をしても、どうやらピンと来ないみたいだ。僕がNYを後にしてから、マーク・ターナーの様な、黒人なのに白人のウォーン・マーシュに影響を受けた…と公言するミュージシャンが現れ、それが世界を席捲するスタイリストとなるなんて、僕には想像も出来なかった。少なくとも、僕がアメリカにいた頃の彼はまだそんなスタイルではなかったと思うし、当時、クールジャズの影響を強く感じるプレイヤーはライブやジャムセッションでお目に掛かった事は無かった。
いずれにせよ、今はそういう人種を意識した考えがかなり薄れて来たというのは大変良い事だと思うし、日本人にとっても働きやすく生活もしやすくなったのは喜ばしい事だ。でも、先人達が苦労してその状態にまで持って来たという事を忘れないで欲しいし、NY以外の田舎などでは、まだ人種に偏りが有るので、決して差別は無くならないだろうし、NYでさえ、いつ、以前の様な状態に戻るかも分かったもんじゃない。ここ最近では、コロナ禍のせいでアジア人差別が始まり、ピアニストをはじめ色んなアジア系の人達がアタックされるなど被害を受けている。
少なくとも音楽を演る上で差別は有って欲しくない。特にジャズは自由な音楽なのだから。「ジャズは黒人のものか?」というのを『Mo Better Blues』という映画でトランペッター役のデンゼル・ワシントンとサックス奏者役のウェズリー・シュナイプスが議論するシーンが確か有った様な気がする。現地で英語で観たのでよく覚えてないのだが…
ウォーン・マーシュのスロー・ブルースを僕はトランスクライブしたけど、それは、彼の演奏が本当に「真っ白け」に聴こえたのが面白かったからだ。ローレンス・マラブルの言う様な「あんなのはジャズじゃねぇ。」ってな言葉がマーシュに向けられたものだったとしたら(実際にそういう批判は受けていただろうと思う。)、もし、それにマーシュが負けていたとしたら、今日のマーク・ターナーのスタイルは生まれてなかったのだ。
ジャズを演る上ではブルースは不可欠だ。でも、それぞれのブルースが有れば良いと僕は思っている。白人でも黄色人種でも、何処の国の人でも。
僕がエブリンのバンドに加入した時、もう一人イタリア人の女性のテナー奏者が居た。そこそこ上手で美人な娘だったけど愛想が悪いしとっつきにくい娘だったし、何で2テナーなんだろう?とずっと疑問だったのだけど、ある日突然、エブリンが「これからはスグルをこのバンドのテナーにする。」と言った。実質上のその娘のクビ宣告だった。それを聞いた彼女は「OK、じゃ、私帰るわ。」と憮然とその場を去った。僕は知らないうちにオーディションを受けていた事になる。だから僕には無愛想だったのか…と気付いた。それにもビックリだったけど、自分に自信が有ったわけでも無いので、何故彼女がダメだったのか尋ねてみると、メンバー全員が口を揃えて「彼女にはブルース・フィールが無かった。」と言った。それを聞いて尚更僕は怖くなった。自分に十分なブルース・フィールが有るとはとても思えなかったからだ。
それ以来、襟を正してブルースを演奏する事にしたし、尚更ブルースが難しいと感じる様になった。我々がストリート・ギグで演奏する場所は、時間帯も含め決められてるのだが、僕らが演奏する前の枠で演ってた白人のギタートリオを観て、齢70代半ばになるベテラン・トランペッター、エド・ルイスが僕に囁いた。「アイツらはダメだ。ブルースが全く無い。お前はあぁなっちゃ駄目だからな。」と言われ、その後の演奏がまた怖くなった。
その頃はなるべく黒人に同化しようと努力したけど、NYという街で社会に飛び出し、色んな経験をした事で、日本人という自分のアイデンティティを改めて見つけ出す事が出来たし、例え同化する事が出来なくても、自分自身のブルースさえ有れば人種に関係無く受け入れて貰えると思っている。それにはペッパーやマーシュ並みのハートが必要だと思うけど。
日本に帰国して思ったのは、人種差別が無い(全く無いとは言い難いが)ので仕事を取る上で凄く楽だという事。しかしながら、ジャズのリスナーや、また演奏者でさえもそういうブルース・フィールに無関心な人が意外と多いのが残念だ。いや、もはやアメリカ人でも、更には黒人でさえも無関心なのかも知れない。『コラテラル』という映画で、トム・クルーズ演じる冷血な殺し屋がジャズの話をするのだが、脅されてトムを殺しの現場まで運ばされてる黒人のタクシー・ドライバーのセリフが「俺にはジャズが分からねぇ。」だったので。黒人に敢えてそのセリフを言わせるというのが、今のアメリカの世相を表しているのかも知れない。それでも、僕はブルース・フィールを大切にしたいし、自分自身のブルースを見つけたいと思っている。折角、アメリカで学んだ大切な事なので。そして、ジャズが今後も人種の垣根の無い、自由で闊達な遣り取りの出来る音楽であって欲しい。
冒頭にご紹介したアート・ペッパーの本はまだ読み始めて間もない。引き続きゆっくりと読み進めるつもりだ。










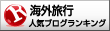

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます