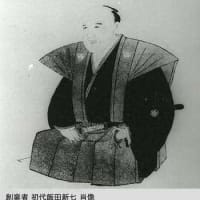蒲生稲寸、滋賀県蒲生郡内の地方豪族・蒲生稲寸氏(いなぎ、地方官・屯倉の長官)の墓群の可能性が高い。
東近江市横山町にある蒲生あかね古墳公園は、滋賀県内でも最大級の古墳時代中期古墳群で、県の指定史跡。9基以上からなり、現在概要の確認できるものは5基。正規の前方後円墳はないが、大形円墳・方墳で構成される。
滋賀県史跡 木村古墳群・「天乞山古墳」(東近江市)
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/d/20191001
滋賀県史跡 木村古墳群・「久保田山古墳」(東近江市)
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/d/20191002
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/d/20191001
滋賀県史跡 木村古墳群・「久保田山古墳」(東近江市)
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/d/20191002
近江国蒲生郡を本拠地とした氏族。『古事記』においては、天照大御神と須佐之男命とのうけい(誓約)によって誕生した天津日子根命の後裔氏族として、凡川内国造ら11氏とともに名が挙げられている。
滋賀県蒲生郡内に所在する「竹田神社」の社伝によれば、蒲生稲寸の支配領域は周辺の郡域を含む広大なものであったとされる。また、欽明~推古期の氏人である蒲生稲寸三麿は、社伝のなかで蒲生稲寸中興の祖として称揚され、同社には三麿を象ったとされる神像が伝えられている。
同様に滋賀県蒲生郡内に所在する馬見岡綿向神社の社伝においても、三麿は山部連羽咋とともに託宣を受け、同社を創建した人物とみなされている。このような伝承が蒲生郡内に残る一方で、『古事記』のほかに史料上から蒲生稲寸の活動を確認することはできず、実際に蒲生郡内で権勢を誇ったのは佐々貴山公であった。ただし、二条大路から出土した木簡には「勘富郡桐原郷□国里・勘富[ ]」と墨書されたものがあり、ここにみえる「勘富某」(カンフはカマフの訛化であるという)が蒲生稲寸の後裔であった可能性は高い。