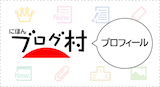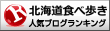何のためにウォーキングをするのか。
「テーマ」(時に「クエスト」とも言う。)を持つと楽しみが増えます。
「ご朱印集め」は代表的なものと言えるでしょう。
私の場合は「風景印集め」。
消印の一種である風景印をもらいに郵便局に出かけます。
配置局は全国で1万局以上。
ガイドブックには載っていない街の名所・名物を知ることもできておすすめです。
「テーマ」(時に「クエスト」とも言う。)を持つと楽しみが増えます。
「ご朱印集め」は代表的なものと言えるでしょう。
私の場合は「風景印集め」。
消印の一種である風景印をもらいに郵便局に出かけます。
配置局は全国で1万局以上。
ガイドブックには載っていない街の名所・名物を知ることもできておすすめです。
JR 函館本線「野幌」駅(北海道江別市)の北口と南口にはレンガオブジェが設置されています。

北口に設置されたオブジェ「登窯」。

南口に設置されたオブジェ「輪環窯(りんかんがま)」。
日本で有数のレンガ産地の江別市らしいオブジェであると思います。
ちなみに北口のものは「登り窯(のぼりがま)」、南口のものは「輪環窯」となっており、それぞれレンガを焼く「窯」を表現しています。
ところで、レンガとは 粘土を天日や火(焼成)で固めた、手で掴める大きさの建築材料でありますが、レンガの発展に「窯」の進歩は、とても重要でありました。

こちらは、登り窯の一種、「両登り窯」。
初期の「窯」は「登り窯」。
効率よく使えましたが、規模が大きいため設備・運営費が多くかかりました。
燃料は初め、薪でしたが、大正元年頃から石炭となりました。
上の写真の模型は「江別市セラミックアートセンター」内にある「れんが資料展示室」のもの。
「れんが資料展示室」は、レンガの歴史や建築物などを記したパネルや各種レンガ、模型などが展示されており、レンガについて学べるようになっています。
こちらの展示物を見ると、「窯」によってレンガの種類も変化していくのが分かります。

「登り窯」が使われていた時代に作られたレンガ。面白い形のものもあるが、シンプルな形のものが多い。

「江別市セラミックアートセンター」所蔵物は、北海道江別市のレンガ関連 遺産として、経済産業省の「近代化産業遺産」に登録されています。
「登り窯」の次に登場したのは、「輪環窯」。
ドイツ人のホフマンが発明しました。

「輪環窯」を配置した工場の模型。
アーチ状の「窯」を環状に連続して配置し、1つの区画で焼き上がると、また次の区画に火を移して調整を繰り返しました。

これにより、連続して大量生産が可能となりました。
しかし、燃料の石炭から出る煙が公害問題となり、昭和後半になると全く利用されなくなりました。

「輪環窯」で作られたレンガ製品。筒状のものが登場している。
次に登場し、現在でも利用されているのが「トンネルキルン」であります。
「トンネルキルン」は文字通り、トンネル状の構造をした「窯」であります。
従来の窯と異なり、火が固定され、焼成されるものが動きながら焼かれていきます。
これにより、多様な製品を作ることが可能になりました。

製品を見ると、その種類の多さに驚く。
燃料は A 重油。
燃料も時代と共に変化していることが分かります。
「れんが資料展示室」は、そんなに大きな展示室ではありませんが、内容がとても充実しており、レンガに興味がなくても、見学後、「とても良い勉強になった」と思えるものになっております。

その「れんが資料展示室」がある「江別市セラミックアートセンター」は、野幌若葉郵便局の風景印にも描かれています。

テーマ:江別特産の小麦、レンガ、江別市のキャラクター「えべチュン」、江別市セラミックアートセンター
「江別市セラミックアートセンター」は他にも展示室があり、「北のやきもの展示室」は、一見の価値があります。

芸術性の非常に高い、美しい焼き物が展示されています。
(特別展もあるかも。)

江別観光の目玉としたい施設であります。
こちらの施設には歩いて行けないこともありませんが、見学には体力がいるため、バスでのアクセスが良いかと思います。
ただし、本数は少なくはありませんが、1時間に1本の時もありますので、予め時刻表を確認することをおススメします。

<参考資料>
- れんが資料展示室パネル
- 江別市セラミックアートセンター・リーフレット
<風景印のもらい方>
- 風景印を配置している郵便局に行き、「郵便」の窓口にて「風景印をお願いします。」と言う。
- 63円以上の切手を貼った台紙やはがきなどを出し、希望の押し方を伝える。
(私の場合は名刺カードに切手を貼り、切手の真下に押してもらうようお願いしています。見本があると分かりやすいです。)
※風景印を配置している郵便局を知るには、「日本郵便」の公式HP(切手>風景印)か、『新・風景スタンプ集』(日本郵趣出版)という本で調べると良いでしょう。
※風景印のもらい方は、直接、郵便局に行くか、郵頼という方法があります。
※風景印のもらい方は、直接、郵便局に行くか、郵頼という方法があります。
 当ブログへの問い合わせについて
当ブログへの問い合わせについて仕事等で当ブログに連絡をしたい場合は、
下記のアドレスまでメールにて
お知らせください。
(コメント、感想用ではありません。)
obenben194@gmail.com