
その7年後(昭和34年)に再び 富士見に訪れた時のことを詠んでいます。
『これは 昭和三十四年三月末に書いた詩である』
悔恨は長く、受苦は尽きない。
ただ輪廻の春風が成敗をこえて吹き過ぎる。
カールフライターク (富士川英郎君に)
自註 富士見高原詩集(尾崎喜八)より
まだ褐色に枯れている高原に
たんぽぽの黄の群落がところどころ、
そよふく風には遠い雪山の感触があるが
現前の日光はまばゆくも暖かい。
かつて私が悔恨を埋めた丘のほとりの
重い樹液にしだれた白樺に
さっきから一羽の小鳥の歌っているのが、
二日の後の古い復活祭を思い出させる。
すべてのきのうが昔になり、
昔の堆積が物言わぬ石となり、岩となる。
そしてそこに生きている追憶の縞や模様が
たまたまの春の光に形成の歌をうたう。
『うるわしの白百合、ささやきぬ昔を・・・・・・』
そのささやきに心ひそめて聴き入るのは誰か。
悔恨は長く、受苦は尽きない。
ただ輪廻の春風が成敗をこえて吹き過ぎる。
(一九五九年三月二十七日 金曜日)
【自註】
これは昭和三十四年の三月末に書いた詩である。
用事があって東京から松本へ行き、帰途 久しぶりに富士見に寄って一泊した。
土地の親しい幾人かが旅館に集まって馳走をしてくれ、昔話に花を咲かせ、私も快く酔って寝たその翌朝が二十七日金曜日、すなわちその二日後が復活祭というキリスト受難の金曜日だった。受難週間に酒を飲んだり馳走を食ったりするのは言わば破戒の行為だったが、それと知りながらも旧知の招宴を辞退するわけにもいかなかった。なぜならば彼らはキリストには無縁の人だったから。そして私にとっても、有縁も有縁、この土地での生活にはいろいろ厄介をかけた人達だったから。
帰京の汽車の時間もあるので、私は早く起きて曾て七年間を住み馴れた分水荘の在る丘のほうへ歩いて行った。そよ吹く風こそまださすがに冷たいが、早春の日光は暖かく、路傍にはところどころタンポポの花さえ吹き出していた。小鳥が一羽、いつまでも続く歌を歌っていた。なじみも深いホオジロだった。私は向うの分水荘の森を見ながら道の岩に腰をかけた。昭和二十七年にあの森の家を引き払ったのだから今年で早くも七年になる。年老いた私にとって七年と言えばもうりっぱな昔である。
それでその昔より更に七年前の昔の或る日、私は自分の芸術を他国と戦っている祖国への愛に捧げ尽くした自責の念にさいなまれ、悔恨の思いを埋めるためにこの高原へ来たのである。その十四年間の思い出の数々が、その堆積が、追憶の模様を描いてこの堅固な岩に象徴されている。明後日の復活祭を私は東京で祝うだろう。妻と共にあの讃美歌を歌い、花を飾り、卵の殻を染めるだろう。
しかし今日はそのキリスト受難の金曜日。
私にとっても過ぎた歳月をあだおろそかには思えない日だ。そう思って静かに腰を上げ、もう一度高原の遠く近くを眺め渡し、さて黙々と駅前の町の宿へ戻ったのである。
*富士川英郎
ふじかわ ひでお(1909年2月16日 - 2003年2月12日)
日本のドイツ文学者、比較文学者。













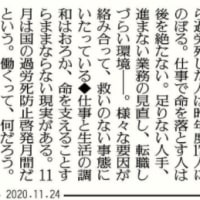
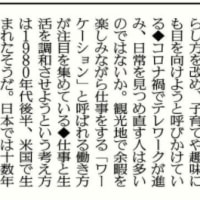

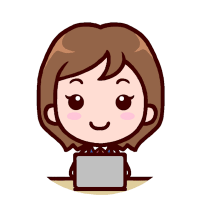
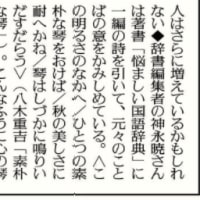
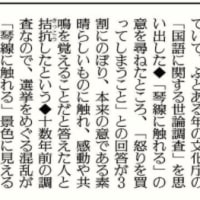


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます