
彼岸はサンスクリット語の「波羅密多」から来ています。
「波羅」は、あちらの岸、「蜜多」は至る、たどり着くという意味です。
煩悩と迷いのこちらの世界「此岸」から、悟りと安心の世界「彼岸」へたどり着くというのがお彼岸です。
この彼岸に「お」をつけた「お彼岸」は、秋分の日の定義でもある「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」となり、祖先を供養する日で墓参りなどを行う日本独自の期間となります。
お盆では先祖がこちらへ帰って来ますが、お彼岸の時は太陽が東から西へまっすぐですから、こちらから先祖を迎えに行くという感覚です。
新潟 夕日の森

⇒上越観光Navi
仏教的には、此岸から彼岸へたどり着くために、実は6つの修行(六波羅蜜)が課せられます。
六波羅蜜(ろくはらみつ)
布施(フセ)・・・・・・・見返りを求めず、人のために何か良いことをする。
持戒(ジカイ)・・・・・・規律を守り、相手のことを考え慎んで生活する。
忍辱(ニンニク)・・・・困難や悲しみに耐え偲ぶこと。
精進(ショウジン)・・たえず向上心を持って努力する。
禅定(ゼンジョウ)・・どんなときにも心を落ち着けること。
智慧(チエ)・・・・・・・真理を見極め、真理を見極める力をつける。
改めて言われると難しく感じますが、考えてみると日常生活の中で行っていることです。
家族や親しい人のために骨を折ることはよくあることですし、長い人生の中では耐え忍ぶ時もあります。
ただ、真理を見極めるという意識は、普段の中で持っているものではありませんが、日常生活の中では人として求められることですし、自ら求めることでもあります。
自身のことを考えると怠けたり我慢できなかったりと逆のことも多いのが実際ですが、あんまり気にしすぎても身体に毒ですし、上がったり下がったりの人生ですから、こうした機会をとらえて少しばかりでも自分を見直してみる、そういう期間なのかもしれません。










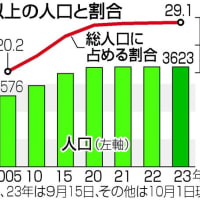















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます