・「高齢者」の社会共通の定義はありません。たとえば法律をみると、それぞれの法律において必要に応じてそれぞれに定義が違います。
・よく使われる前期高齢者や後期高齢者は「高齢者の医療の確保に関する法律」で定義されています。前期高齢者は、「前期高齢者である加入者」について「65歳に達する日の属する月の翌月以後である加入者であって75歳に達する日の属する月以前であるもの」として定義されています(同法32条)し、後期高齢者は「後期高齢者医療の被保険者」について「75歳以上のもの」となっています(同法50条)。なお、これらの定義に当てはまらない方も事情によっては前期高齢者や後期高齢者に含まれます。
・別の法律、たとえば「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、「自ら居住するため住宅を必要とする高齢者」に限って定義されていて60歳以上の方となっていいます(62条)。
・投稿者は、法律のように厳格な定義がないと不都合な場合を除き、高齢者という「区分」を作らない方がよいと思っています。公的な調査でも、「何歳以上を高齢者と考えますか」といった設問がありますが、どのような意図があるのでしょうか。
・人は歳を重ねますが、心身と年齢には直接の関係はありません。十人十色です。もし高齢者という「区分」をたとえば70歳以上の方とすると、70歳以上になったとたんに「高齢者」という言葉の持つニュアンスに自分を重ねてしまうことになりかねません。また、社会からも「高齢者」として区別されることにもなりかねません。
・人生は連続です。「高齢者とは」という区別がない社会(法律などは例外として)が望ましいと思っています。










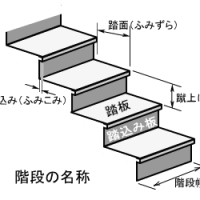
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます