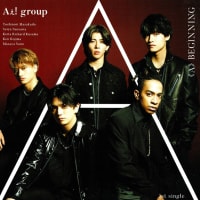「世の中が音楽を必要としなくなり、
もう創作の意欲もなくなった。
死にたいというより、消えてしまいたい」
とても重たい言葉だ。
この言葉は、先日他界した加藤和彦さんの言葉だ。
(詳しくはこちらを参照)
彼の「世の中が音楽を必要としなくなった」、
というのは、僕の感覚ともすごく近い。
日常、日々若者と接する僕だが、
若者たちから「音楽の話題」が本当に消えたと感じる。
バンドマンも減ったし、ヘビーリスナーも減った。
今日も講義の中で、音楽の話題が出たのだが、
平成生まれの彼らは実に音楽を聴いていない、
というより、買っていないし、それほど思い入れも強くない。
70人くらいの講義だったのだが、
普段CDを買っている人が本当にいないのだ。
月に一枚買う人が2,3人程度。
ほとんど買わないという学生が圧倒多数だった。
だが、彼らは音楽を聴いていないわけではない。
ラルクやグレイは多くの若者が聴いているし、
GReeeeNみたいな流行グループの曲はほぼ全員聴いている。
安室ちゃんや浜崎もみんな聴いている。
ただ、聴き方が大きく変わったと思う。
音楽から何かを得ようとは思っていない。
音楽に頼ろうとか、音楽に寄りかかろうとしない。
あくまでも、彼らにとってはBGMなのだ。
あるいは、主題歌、テーマ曲に過ぎないのだ。
だから、好きな曲のグループがいたとしても、
そのグループのライブにわざわざ行こうとは思わない。
また、歌姫もファッション界のトップランナーではなくなった。
今は、モデルや読者モデルがファッションリーダーになっている。
「安室」や「浜崎」から、「モデル」へと興味が移ったのだ。
また、彼らの特徴は、平成世代らしいというか、
なんとも「軽やか」なのである。
音楽にそこまで期待もしていないし、依存してもいない。
今の時代では、「尾崎」や「長渕」といった「代弁者」は出にくい。
「代弁」してくれなくても、ネットなんかで言えることができる。
共感してもらいたければ、ブログでもmixiでもやって、
共感してもらえる。オフ会もあるし、たまり場もある。
音楽に助けられ、音楽に救われた僕としては、
とても複雑な気分ではあるが、仕方ないかなとも思う。
70年代~90年代がたまたま凄すぎただけなのかもしれない。
ビジネス的には、この30年間がピークだったように思う。
だけど、音楽そのものはまだまだその役割を大きくもっている。
BGMになってしまったかもしれないが、
BGMのない世界は、空虚であり、陳腐であり、乾いている。
音楽があって、ひきたつものはたくさんある。
もちろん、今の時代でも「音楽」を死ぬほど愛しているリスナーもいる。
世の中が音楽を必要としなくなっても、
音楽を必要としている人はいる。
うちの学生の中にも、時折V系ファンがいる。
彼らは、昔同様しっかりとファンとしてバンドを愛している。
まさに一体同心となって、バンドを支えている。
音楽が人の心に響く、ということは今でも起こっている。
ただ、「ビジネス」としては、成り立ちにくくなっているのだ。
90年代の象徴とされる「小室」も、00年代に入って厳しくなった。
音楽は、ビジネスモデルから、文化モデルへと変わったのだ。
誰でも絵を描いたり、彫刻したりするように、
音楽は誰でも作れて、誰でも楽しめるようになった。
数ある文化の一つとして、音楽(ポップス)もサブ化したのだ。
サブ化は、われわれの日常により深く浸透した、ということであり、
日常の範囲内で成り立つようになったということを意味する。
これまで音楽をビジネスとして利用し、
大稼ぎしてきた人には厳しいかもしれないが、
音楽そのものは、より身近で、より親しみのあるものになっている。
それ自体は、決して悪いことではないだろう。
加藤さんの死を悼むと共に、
音楽そのものが変貌していることはしっかりと理解したいと思う。
PS
学生たちに、「CDを買わないとなると、いったい何にお金を使っているのか?」
と聴いたところ、多くの人が、「買い物、飲み、食事」と答えてくれた。
遠いアーチストではなく、身近な友だちに友愛を求めているのかもしれない。
それはそれでいいことなのかもしれないが、
遠いアーチストだからこそ、届けてくれるものもあると思うんだよな~~





![BUCK-TICK【スブロサ SUBROSA】 櫻井さん亡き後、1年の沈黙を経て、想定をはるかに超える新世界を提示する![全曲解説]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/36/71/e0c375fec28cd1ba22b13374cc418015.jpg)