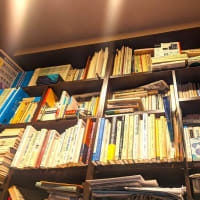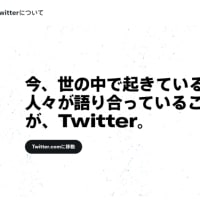僕はブレヒトが大好きだ。
『三文オペラ』は、学生時代に夢中で読んだ傑作(マスターピース)だった。また、翻訳されているのかどうか分からないが、『こぶ』という短編小説は、ドイツの大学のゼミで発表した作品だった。ブレヒトのあの汗臭い感じが大好きで、庶民(上流ではない人)の絶妙な描き方に強く共感したものだった。
そんなブレヒトの作品で欠かせないのが、「コイナー氏」の寓話だ。これは、いつ何度読んでもよく分からない話なのだが、なぜだかひきつけられる。その中で一番好きな作品の一つが、「もしサメが人間だったら」だ。
なんとも言いがたいお話で、なんとも理解しがたい内容なのだが、なぜだかなんとなく分かる気がする、そんな作品なのだ。僕訳で恐縮だけれど、紹介させてもらいたい。人間の根本的な愚かさが描かれているようにも読めるし、人間の知性の尊さをニヒルに賞賛しているようにも読める。
【もしもサメが人間だったなら・・・】 (翻訳、一部省略)
コイナー氏の家主の娘が、コイナー氏に尋ねた。「もしサメが人間だったなら、サメはちいさな小魚にもっとやさしくなるの?」、と。彼は、「もちろん」、と答えた。
「もしサメが人間だったら、サメは、小魚のために海の中に巨大なケースを作ってあげるだろう。そして、そのケースの中に、植物や動物、あらゆる栄養源を入れてやるだろう。サメは、いつもそのケースの中が新鮮な水であるよう、気にかけるだろう。小魚の気持ちが落ち込まないように、ときどき大きな水祭りを行うだろう。楽しい小魚の方が落ち込んでいる魚よりおいしいからね。
もちろんその大きなケースの中には学校もあるだろう。その学校で、小魚は、サメの口の中への泳ぎ方を習うはずだ。主要教科は、当然、小魚の道徳教育であろう。小魚は、「自ら喜んで自分の身を犠牲にすることが最も偉大なことであり、最も素晴らしいことなのだ」、「子魚はすべてサメを信じなければならない。特に素晴らしい未来を世話してやる、とサメに言われた時には、ちゃんとサメを信じなければならない」、と教授されるだろう。そして、従順さ(Gehorsam)を学ばなければ、小魚の未来は保障されない、ということを教わるだろう。
もしサメが人間だったならば、サメは当然また、敵の魚ケースと敵の小魚を手に入れるために、サメ同士で戦うだろう。だが、その戦いは、(サメ自身がするのではなく)自分たちが所有する小魚たちにやらせるだろう。サメは、自分が所有する君たちと他のサメが所有する小魚との間にはものすごい違いがあるのだ、と小魚に教えるだろう。周知のとおり、小魚は無口であるが、完全に異なった言語の中で沈黙しているのだ、だから、お互いに理解し合うこと不可能だ、と。サメは、戦争で、異なった言語をもつ敵地の沈黙の小魚を殺したすべての小魚に、海藻でできた小さな勲章を与えて、英雄の称号を授与するだろう。
もしサメが人間だったならば、当然また彼らには芸術もあろう。豪華に彩られたサメの歯と純粋な楽しいお庭である彼らの口が描かれた素敵な絵があるだろう。海の底の劇場では、英雄的な小魚が夢中になってサメの口に向かって泳ぐ様子が上演されるだろう。また、音楽は、小魚がサメの口に流れ集まるほどに美しい旋律であろう。
もしサメが人間であったならば、宗教もまた存在するだろう。小魚は、サメのお腹の中でようやく正しく生きることができるのだ、と教わるだろう。ところでまた、もしサメが人間であったならば、現代社会のような「すべての小魚は等しく平等である」という神話は崩壊するだろう。小魚の一部は公職に就き、他の小魚より上の方に置かれるだろう。さらに、幾らか大きい小魚であれば、小さな小魚を食い尽くすことも認められるだろう。それは、サメにとっては好都合にすぎない。というのも、ますますサメ自身、より大きな小魚の塊を食べることができるからだ。大きくて地位の高い小魚は小魚間の秩序を守る職務に就くだろう。教師、将校、ケース建築のエンジニアなどになるだろう。手短に言えば、サメが人間になることで初めて、海に文明ができると言えよう。」
 こちらでも翻訳が掲載されています
こちらでも翻訳が掲載されています