
ほとんど予備知識のないまま観た。長い映画(138分)だったが、飽きることなく見ることができた。現在の男女関係と過去の純愛の回想が交錯するので、最初はなにがなんだか分からず、面倒臭くなって途中で見るのをやめようかと思ったが、途中から盛り上がってきたので、最後まで見ることができた。簡単に言えば、高校の時好きだった女の子が白血病で死んだことをずっと忘れられなかった男が、現在の恋人の行動によって、過去の思い出に正面から向かい合い、やっと心の整理をつけて、現在の恋人との愛を確かめるというストーリーであった。メインの登場人物は、男の主人公が「サクちゃん」こと朔太郎といい、現在を演じるのが大沢たかお、10年ほど前の高校時代が森山未來なのだが、たかだか27歳と17歳の違いなのだから、同じ男優でできないものかと感じた。二人は少し似ているが、どうしても違和感が付きまとった。女の方は、現在の恋人の律子が柴咲コウ、高校時代の恋人の亜紀が長澤まゆみで、この二人は違う人物なので、問題なかった。
こういう悲恋のラブストーリーは昔はよくあった。女性の観客が泣きながらハンカチをびっしょりにして見る映画である。邦画なら『愛と死をみつめて』(吉永小百合、浜田光夫主演)、洋画なら『ある愛の詩(ラブ・ストーリー)』(アリ・マッグロー、ライアン・オニール主演)が代表作であろう。どちらも若い男女の純愛で、女の方が不治の病にかかって最後は死ぬストーリーだ。『世界の中心で、愛をさけぶ』もこのタイプの映画で、こうした映画が21世紀になって製作され、2004年に大ヒットしたということを知って、私は驚くと同時に、何十年経とうが、悲恋物を好む女心は変わらないんだなと思った。私個人の好みとしては、男が死ぬのはいいが、女が死ぬ映画は苦手である。進んで見たいとは思わない。『ある愛の詩』を高校時代に映画館で見た時は、周りの女性がみんなしくしく泣いているのを感じて、辟易したのを覚えている。女性の観客向けのお涙頂戴的な映画は、どうしても途中でしらけてしまう。
ところで、悲恋物の原点は、高村光太郎の詩集「智恵子抄」だと思うが、これは夫婦愛で、男も女もかなり年齢が高く、女の病気は結核だった。「智恵子抄」は二度映画化され、テレビでもドラマ化されている。「智恵子抄」のことは、『世界の中心で、愛をさけぶ』の中にも、二度セリフに出て来るので、明らかに作り手が意識していたのだと思う。男の主人公が朔太郎というので、詩人の萩原朔太郎が引き合いに出され、「智恵子抄」を書いた詩人か?というやり取りなのだが、別にこんなわざとらしいセリフを入れることもないと感じた。父親が萩原朔太郎の詩が好きだったので、命名したと言うだけでいいのではないか。
『世界の中心で、愛をさけぶ』という映画は、ストーリー上、あちこちに奇異に感じる部分はあったものの、高校時代の純愛がよく描けていたし、森山未來と長澤まゆみの熱演で良い映画になっていた。大沢たかおは、ウォークマンを聴きながら、思い出に耽りながら郷里をウロウロしているだけで、画面に出すぎのような気がした。柴咲コウの律子という役は、長澤まゆみ(亜紀)が白血病で入院中に声を録音したカセットを朔太郎に配達する小学生(その母親が同じ病院に入院中)で、この小学生は子役で良いのだが、10年後になぜ律子が、朔太郎の恋人になっているのかが分からなかった。また、最後に録音した亜紀のカセットを、交通事故に遭って朔太郎に渡せず、10年後に律子はこのカセットを聴いて、失踪するのだが、この辺も私には理解できなかった。朔太郎と二人の女性(亜紀と律子)の関係を強引に結びつけようとしているから不自然なのだ。朔太郎の現在の恋人の律子は、彼の昔の恋人で白血病で死んだ亜紀のことを知らず、何かのきっかけで亜紀のことを知り、失踪する設定にすれば良かったのではないか。それと、郷里の写真館の主人として「シゲしい」という中年男が出て来て、朔太郎の親戚らしいが、この役を演じた山崎努に新鮮味がなく、いつもの山崎努そのままで詰まらなかった。
監督は行定勲(ゆきさだいさお)で、この映画のヒットで一躍メジャーな監督になったらしいが、この監督の映画は、以前『北の零年』のDVDを借りて途中でまで観て、詰まらなくてやめた記憶がある。『春の雪』は予告篇を見たが、本編は未見。『今度は愛妻家』という映画は雑誌「シナリオ」で脚本を読んだことがあり、是非見たいと思っているのだが、ビデオショップにDVDが見当たらない。恋愛映画を作るのが好きな監督のようだが、真面目な人のようで、ユーモアのセンスはなさそうである。映画のテンポもなく、森田芳光とはタイプが違う。その森田芳光が『世界の中心で、愛をさけぶ』で映画監督の役としてちらっと出演していたが、どういう訳なのか分からない。















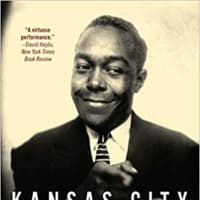

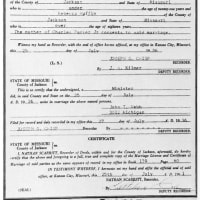








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます