江戸時代は本の制作・卸売・小売が未分化だった。版元(板元、現在の出版社)は、問屋でもあり、小売店も持っていた。そして、印刷・製本業者である板木屋(彫師)、摺り師、仕立屋(表紙屋ともいい、今の製本所である)等を下請けに抱えていた。
出版販売する本の種類によって版元は二系列に分けられた。書物問屋と地本問屋である。主に京大坂の版元から出された、いわゆる「物之本」(硬い本)すなわち和漢の学術書等を出版販売する業者が書物問屋で、地本すなわち地元の江戸の大衆娯楽本である草双紙類(赤本、黒本、青本)、洒落本、噺本、浄瑠璃本、長唄本、そして浮世絵などの出版販売をする業者が地本問屋であった。書物問屋と地本問屋を兼ねる大手の版元もあった。たとえば、京都に本店があり、江戸日本橋に支店を持っていた仙鶴堂・鶴屋喜右衛門がそうであった。
江戸時代中期に株仲間といわれる同業組合ができるが、書物問屋の株仲間が幕府に公認されるのは享保年間で、地本問屋の方はずっと遅れて寛政2年である。ただし、地本問屋にも株仲間はあり、仲間同士の取り決めや約束を定め、違反したものには制裁を加えたりしていた。今で言う著作権というものはなかったが、板株(いたかぶ 版権)や販売権というものはあった。
また、海賊版を作った版元は、被害者が奉行所に訴えれば、吟味の上、お上から処罰が下った。安政7年1月に鱗形屋孫兵衛が罰せられたのも、身内の徳兵衛が大坂の版元からすでに出版されている「早引節用集」(コンサイス国語辞典といった本)を重版し、勝手に鱗形屋から売り出したからであった。
蔦屋重三郎は、版元として初めて吉原細見を出した時、板株を持っていなかったため問題となり、吉原の妓楼玉屋山三郎の口利きで、やっと紛糾を収めたと言われている。
天明3年9月、重三郎が一流版元の居並ぶ日本橋通油町へ進出する時は、地本問屋の丸屋小兵衛の店を買い取ってそこへ本店を移したのだが、丸屋が持っていた版元の権利一切も買い上げたとのことである。トータルでいくら支払ったかは不明であるが、相当な金額であったことは確かだろう。また、その際、問屋有力者のだれかの斡旋があったと思われるが、それが鱗形屋孫兵衛なのか、それとも最大手の鶴屋喜右衛門(通称鶴喜)なのかは分からない。鶴喜は、日本橋通油町に店を構えていたが、その斜向かいに移転してきた蔦屋重三郎と親しく接し、なにかにつけて助力を惜しまなかったようだ。
安永7年、8年の蔦屋の出版点数が激減したことはすでに述べた。出版物というのは編集制作に3ヶ月から半年かかるので、蔦屋のピンチは安永6年の半ばあたりから安永8年の半ば頃までの約2年間であった。その原因は、蔦屋が援助を受けていた版元の鱗形屋孫兵衛の経営破綻であったことは間違いない。
鱗形屋は安永4年から毎年10数点出版していた黄表紙が、安永8年には7点に減り、安永9年には無くなってしまう。その2年後の天明2年にはまた黄表紙を出版し始めるが、鱗形屋の経営者が変わり、建て直しをはかったように思われる。しかし、これは一時期だけの復活で天明期の半ばに第一線から退き、寛政初めには廃業している。
鱗形屋にとって定番の「吉原細見」は、安永9年正月に発行したのが最後で、安永10年(天明元年)は蔦屋版「吉原細見」が1点、天明2年以降は蔦屋が「吉原細見」を独占し、春と秋の年二回に発行することになる。鱗形屋は蔦屋に「吉原細見」のほかにも黄表紙ヒット作の版権(板木も含めて)を売ったと思われる。恋川春町の「金々先生栄華夢」「高慢斎行脚日記」、朋誠堂喜三二の「鼻峯高慢男」などは寛永6年、蔦屋から再刊されている。
安永9年(1780)、重三郎は一気に出版点数を増やす。この年の蔦屋からの発行本は全部で約15点(黄表紙が8点)である。そのうちの半数は、正月発行分だろうから、前年の秋からは編集制作に取り掛かっていたはずである。ということは、安永8年の夏までには出資者を見つけ、出版の資金繰りがついていたのだろう。3年ほど前からすでに版元間で黄表紙(当時はこれも青本と呼んだ)の販売競争が激化していたが、重三郎は、鱗形屋に代わってその競争に加わることを決断し、売れっ子作家の朋誠堂喜三二と専属契約のような約束を結び、喜三二に執筆を依頼していたはずである。また、北尾重政には挿絵を依頼し、愛弟子の北尾政演(山東京伝)とも知り合って、彼の早熟した才能に期待をかけていたと思われる。
この年、蔦屋が出版した朋誠堂喜三二の黄表紙は次の3作が知られている。
「鐘入七人化粧(かねいりしちにんげしょう)」(朋誠堂喜三二作、北尾重政画)
「廓花扇観世水(くるわのはなおうぎかんぜみず)」(朋誠堂喜三二作、北尾政演画)
「竜都四国噂(たつのみやこしこくうわさ)」(朋誠堂喜三二作)
他の作者による黄表紙は、5点ある。
「虚言八百万八伝(うそはっぴゃくまんぱちでん)」(鳥居清経画)の作者・四方屋本太郎正直は、大田南畝ではないかと言われている。そうだとすれば、重三郎は南畝とも親交関係を結んでいたことになる。
「夜野中狐物(よのなかこんなもの)」(北尾政演画)の作者・王子風車は、山東京伝になる前の筆名で、画を描いた北尾政演も京伝のことだから、これは、彼の自作自画の黄表紙である。「通者言此事(つうとはこのこと)」(北尾政演画)には作者名がないようだが、これも彼の自作自画かもしれない。
この年の出版目録に洒落本が2点あるが、「一騎夜行(いっきやぎょう)」の作者・志水燕十(1726~86 しみずえんじゅう)は、絵師鳥山石燕門下の高弟で、絵よりも文筆に才を振るった人物だが、彼も重三郎を支えた一人であった。
重三郎の活躍期は安永半ばから寛政半ばまでの約20年であるが、時流に乗る巧さ、企画の斬新さ、販売方法の大胆さといった才覚に加え、重三郎の人脈作りの能力は著しいものがあった。重三郎の社交性と人柄が大きく物を言ったのだろう。重三郎は吉原で顔がきくことを利用し、著名な作家や画家たちを吉原に招き、接待して、人間関係を広げていく。
出版社は、文章を書く人間の才能と、絵(挿絵、漫画)を描いたり、デザインをしたりする人間の才能に依存する業種である。才能を見出し、才能を発揮させることができなければ出版社は発展しないが、出版社の社長はその才能を引きつけるだけの人間的魅力と人心掌握術を備えていなければならない。重三郎は、その二つを十分に持ち合わせていたにちがいない。
出版販売する本の種類によって版元は二系列に分けられた。書物問屋と地本問屋である。主に京大坂の版元から出された、いわゆる「物之本」(硬い本)すなわち和漢の学術書等を出版販売する業者が書物問屋で、地本すなわち地元の江戸の大衆娯楽本である草双紙類(赤本、黒本、青本)、洒落本、噺本、浄瑠璃本、長唄本、そして浮世絵などの出版販売をする業者が地本問屋であった。書物問屋と地本問屋を兼ねる大手の版元もあった。たとえば、京都に本店があり、江戸日本橋に支店を持っていた仙鶴堂・鶴屋喜右衛門がそうであった。
江戸時代中期に株仲間といわれる同業組合ができるが、書物問屋の株仲間が幕府に公認されるのは享保年間で、地本問屋の方はずっと遅れて寛政2年である。ただし、地本問屋にも株仲間はあり、仲間同士の取り決めや約束を定め、違反したものには制裁を加えたりしていた。今で言う著作権というものはなかったが、板株(いたかぶ 版権)や販売権というものはあった。
また、海賊版を作った版元は、被害者が奉行所に訴えれば、吟味の上、お上から処罰が下った。安政7年1月に鱗形屋孫兵衛が罰せられたのも、身内の徳兵衛が大坂の版元からすでに出版されている「早引節用集」(コンサイス国語辞典といった本)を重版し、勝手に鱗形屋から売り出したからであった。
蔦屋重三郎は、版元として初めて吉原細見を出した時、板株を持っていなかったため問題となり、吉原の妓楼玉屋山三郎の口利きで、やっと紛糾を収めたと言われている。
天明3年9月、重三郎が一流版元の居並ぶ日本橋通油町へ進出する時は、地本問屋の丸屋小兵衛の店を買い取ってそこへ本店を移したのだが、丸屋が持っていた版元の権利一切も買い上げたとのことである。トータルでいくら支払ったかは不明であるが、相当な金額であったことは確かだろう。また、その際、問屋有力者のだれかの斡旋があったと思われるが、それが鱗形屋孫兵衛なのか、それとも最大手の鶴屋喜右衛門(通称鶴喜)なのかは分からない。鶴喜は、日本橋通油町に店を構えていたが、その斜向かいに移転してきた蔦屋重三郎と親しく接し、なにかにつけて助力を惜しまなかったようだ。
安永7年、8年の蔦屋の出版点数が激減したことはすでに述べた。出版物というのは編集制作に3ヶ月から半年かかるので、蔦屋のピンチは安永6年の半ばあたりから安永8年の半ば頃までの約2年間であった。その原因は、蔦屋が援助を受けていた版元の鱗形屋孫兵衛の経営破綻であったことは間違いない。
鱗形屋は安永4年から毎年10数点出版していた黄表紙が、安永8年には7点に減り、安永9年には無くなってしまう。その2年後の天明2年にはまた黄表紙を出版し始めるが、鱗形屋の経営者が変わり、建て直しをはかったように思われる。しかし、これは一時期だけの復活で天明期の半ばに第一線から退き、寛政初めには廃業している。
鱗形屋にとって定番の「吉原細見」は、安永9年正月に発行したのが最後で、安永10年(天明元年)は蔦屋版「吉原細見」が1点、天明2年以降は蔦屋が「吉原細見」を独占し、春と秋の年二回に発行することになる。鱗形屋は蔦屋に「吉原細見」のほかにも黄表紙ヒット作の版権(板木も含めて)を売ったと思われる。恋川春町の「金々先生栄華夢」「高慢斎行脚日記」、朋誠堂喜三二の「鼻峯高慢男」などは寛永6年、蔦屋から再刊されている。
安永9年(1780)、重三郎は一気に出版点数を増やす。この年の蔦屋からの発行本は全部で約15点(黄表紙が8点)である。そのうちの半数は、正月発行分だろうから、前年の秋からは編集制作に取り掛かっていたはずである。ということは、安永8年の夏までには出資者を見つけ、出版の資金繰りがついていたのだろう。3年ほど前からすでに版元間で黄表紙(当時はこれも青本と呼んだ)の販売競争が激化していたが、重三郎は、鱗形屋に代わってその競争に加わることを決断し、売れっ子作家の朋誠堂喜三二と専属契約のような約束を結び、喜三二に執筆を依頼していたはずである。また、北尾重政には挿絵を依頼し、愛弟子の北尾政演(山東京伝)とも知り合って、彼の早熟した才能に期待をかけていたと思われる。
この年、蔦屋が出版した朋誠堂喜三二の黄表紙は次の3作が知られている。
「鐘入七人化粧(かねいりしちにんげしょう)」(朋誠堂喜三二作、北尾重政画)
「廓花扇観世水(くるわのはなおうぎかんぜみず)」(朋誠堂喜三二作、北尾政演画)
「竜都四国噂(たつのみやこしこくうわさ)」(朋誠堂喜三二作)
他の作者による黄表紙は、5点ある。
「虚言八百万八伝(うそはっぴゃくまんぱちでん)」(鳥居清経画)の作者・四方屋本太郎正直は、大田南畝ではないかと言われている。そうだとすれば、重三郎は南畝とも親交関係を結んでいたことになる。
「夜野中狐物(よのなかこんなもの)」(北尾政演画)の作者・王子風車は、山東京伝になる前の筆名で、画を描いた北尾政演も京伝のことだから、これは、彼の自作自画の黄表紙である。「通者言此事(つうとはこのこと)」(北尾政演画)には作者名がないようだが、これも彼の自作自画かもしれない。
この年の出版目録に洒落本が2点あるが、「一騎夜行(いっきやぎょう)」の作者・志水燕十(1726~86 しみずえんじゅう)は、絵師鳥山石燕門下の高弟で、絵よりも文筆に才を振るった人物だが、彼も重三郎を支えた一人であった。
重三郎の活躍期は安永半ばから寛政半ばまでの約20年であるが、時流に乗る巧さ、企画の斬新さ、販売方法の大胆さといった才覚に加え、重三郎の人脈作りの能力は著しいものがあった。重三郎の社交性と人柄が大きく物を言ったのだろう。重三郎は吉原で顔がきくことを利用し、著名な作家や画家たちを吉原に招き、接待して、人間関係を広げていく。
出版社は、文章を書く人間の才能と、絵(挿絵、漫画)を描いたり、デザインをしたりする人間の才能に依存する業種である。才能を見出し、才能を発揮させることができなければ出版社は発展しないが、出版社の社長はその才能を引きつけるだけの人間的魅力と人心掌握術を備えていなければならない。重三郎は、その二つを十分に持ち合わせていたにちがいない。















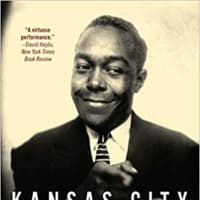

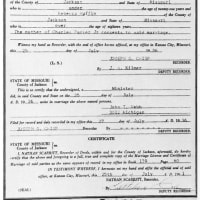



ところで、当ページ上で「安永」の年号が(幕末の)「安政」に9箇所でなっており、前ページでも2箇所発見しました。もしかすると他のページでも同様の変換ミスがあるかも…。
来年は大河ドラマで蔦重が主人公になるため、当ページはアクセスが殺到するかと思い、誤情報が広がる前にと投稿しました。
※せっかくの労作、あくまでもお知らせすることが目的ですので、一読後、この投稿を削除していただいて結構です。本当に素晴らしい蔦重特集ですね!