
写楽 大谷鬼次の江戸兵衛(1794年)
*写楽の絵の中では最も有名なものの一つで、悪役です。
写楽の絵が世に現れてから220年が経ちました。そして、写楽の絵が、日本人や世界の多くの人に愛好され始めてから、およそ100年になります。
日本で写楽の絵の記念切手が初めて発行されたのが1956年ですから、それから60年になりますが、インターネットで調べてみると、写楽の記念切手は、全部で18種類もあるんですね。驚きました。浮世絵師の中ではいちばん多い。次が歌麿の記念切手で、14種類(2枚は同じ絵)です。ほかの浮世絵師はせいぜい一人3,4種類です。
また、これまでに写楽の絵をあしらった商品は、文房具からTシャツまで数多くありますし、インターネットのアイコンにも使えわれています。おそらく、世界の画家の中で、写楽の利用度がいちばん高いのではないでしょうか。ダビンチの「モナリザ」や、ルノワールやピカソやロートレックの絵も思い浮かびますが、写楽の方がたくさん使われているように思います。
浮世絵の複製も今でも世界中に出回っています。その中でも、写楽は人気が高いようです。私はおととい神保町の古本屋を回って、写楽について書かれた本を数冊買ってきましたが、原書房という浮世絵関係専門店へ行ったところ、外国人の方が5人いて、お土産用の浮世絵を探していました。写楽の絵を見ている人もいました。写楽の絵の複製はいちばん種類も多く、50種類以上はあったと思います。一枚3000円くらいで売っていました。
ついでに、手塚書房という歌舞伎関係の専門店へも行って、江戸時代の役者のことが書いてある本を2冊買ってきました。
写楽の絵について、今私が最も関心を持っているのは、第一期の大首絵28枚に描かれた役者たちと出演した舞台での役名(演目と劇場も含まれる)です。写楽の役者絵の中ではいちばん有名な「鰕蔵の竹村定之進」に関し、美術評論家や浮世絵研究者の解説に疑問を抱いたことは、前に書きましたが、まだその疑問につきまとわれています。疑りだすときりがなく、あの絵はほんとうに竹村定之進なのかという疑問も起りはじめました。
それで、写楽の大首絵の役者と役名は、これまでの写楽研究で、いったいどんな人たちが何をもとに、またどういう経緯で特定していったかについて調べているわけです。つまり、写楽研究史みたいなことです。その辺のところをできるだけ知りたいと思っているのですが、と同時に、江戸時代の浮世絵がどういう経緯をたどって現在に至ったかについても興味があります。明治以降の浮世絵の運命とその評価の変遷のようなことですが、なかでも写楽の絵は、そのアップ・ダウン(実際にはダウン・アップ)が極端に激しい。評価の差がこれほど大きな画家はほかにはいないと思います。
肖像画家ではフランス人のモジリアーニ(1884-1920)が思い浮かびますが、彼の場合は亡くなって10年後くらいから評価が上がって、戦後は、彼の人生の悲劇性もあって最大級の評価になりましたが、写楽とは時代的にも無視されていた期間の長さも比較になりません。

モジリアーニ 黒いネクタイをした女(1917年)
ほかに、ノルウェー人のムンク(1863~1944)がいますが、近年、彼の絵の落札額がべらぼうに高いようです(なんと90億円!)。あの有名な「叫び」は、描かれてから約60年後にその評価が急上昇した絵ですが、彼もモジリアーニと同じく現代の画家なので、写楽とは比較になりません。

ムンク 叫び(1893年)
油絵画家と版画家との違いもあります。写楽は、最初に書いたように、18世紀末の画家で、評価され始めるまでに100年ほどの忘却期があり、再認識されてからは、100年間、その評価に変動もなく、最大級の評価を維持し続けている画家です。










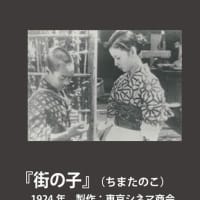



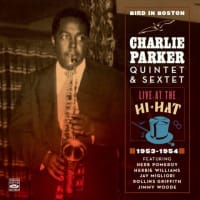
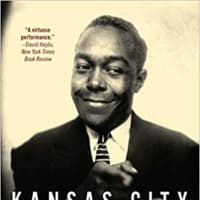

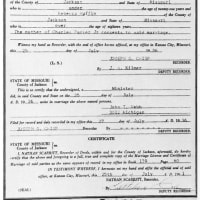



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます