心に残ったセンテンスの続きである。
この部分が一番考えさせられたように思う。
かなり引用部分が長くなりそうだから、極力端折っていこうと思う。
シチュエーションは、メーカー営業、地域問屋専務、酒専門小売店店主の三人がビール販売に収斂したそれぞれの見解を述べ合うといったところ。
こういうのを鼎談というのであったか。
酒屋「先ず、人と人とのコミュニケーションありき。その後でモノは動く。天気の話はどうでもええように見えて、実はどうでもようないんよ。」
メーカーひとりごち「そうだろうか?たかがビールを買うのに、そんな煩わしさは不要だ。」
酒屋「人生たかだか80年。巡り会う人の数もしれとる。そういう出会いを大切にしたい。売ることばっかあくせく考えとると、結局、人生、何も残らん。」
メーカーひとりごち「俺や酒屋のオヤジにとって一番大事なのは1本でも多くビールを売ることだ。商売して金を貰っているくせに、何を偉そうにほざいてる。」
ここで酒屋が持ち出したのが瘤取り爺さんの話。
「天真爛漫な爺さんは鬼と楽しく遊んで、翌朝、瘤が取れていた。計画的でマーケティング派の爺さんは、瘤を取ってもらおうと鬼の宴に出掛けたが、かえって瘤をつけられた。」
専務「瘤を取ってもらった爺さんは心がオープンやった。変化を受け入れ素早く対応出来た。夏海(酒屋)さんは瘤をつけられた爺さんのような企みは世の中に通用せんと悟った人じゃ。いや、企みを企みに見せんように、巧妙に天真爛漫、自然さを装うておる。じゃが、普通の人があんたのように普通に商売するのは難しい。先ずはわかりやすい商売のテクニックを学ばんといけん。そのためには誰にでもわかるノウハウが必要じゃ。夏海さんがいくら文化を大切にしていても、酒屋は酒屋。あくまで商売じゃ。」
メーカーひとりごち「夏海(酒屋)さんはちゃんと売ることを考えている。それを嫌らしく見せないためにオブラートに包む。だから葡萄屋(酒店)には人が集まり、商売が成り立つんだ。」
メーカー「酒は嗜好品です。美味しいかどうかは人それぞれ。でも、美味しいだけでは売れません。パッケージがカッコよかったり、宣伝が好きだったり。酒はイメージで売れていく部分が大きいです。たとえば、個性を大切にする夏海さんがビールを売ると、売られるビールがいくら画一的な大量生産品でも個性的なビールになり得ますよ。」
以上の部分が、妙に考えさせられる。
建前と本音が交錯して葛藤しつつも、「商売は人なり」であるし、その根本的な方針、気持ちの持ちようは、突き詰めれば、人生観に行き着くのではなかろうか。
反面、商売とは職業であり、職業とは食い扶持であればこそ、儲けることが出来なければ、文字通り食ってはゆけぬ。
だからこそ、建前と本音のギャップに喘ぐことにもなる。
結局堂々巡りのようだが、人は食うために生きているのではなく、生きるために食うのだから、「如何に生きるか」が芯となるべきだろう。
商売とは人と人との心に橋を架けること
この辺りまでくると酒乱の主人公の中に酒に対する愛情が芽生えてくるようになる。
以下は主人公のスタンス。
「売る」というのは、「こっちの思い通りになって欲しい」という勝手なベクトルだ。買う側には選択肢はたくさんある。
中略
買う側に何かメリットがなければモノを買わない。
メリットを「幸せ感」と言ってもいい。
その結果モノは動く。
無理矢理動かそうとしてもモノは動かない。
客はセールスマンの人格や、企業の社格を見てモノを買う。
勿論、商品の質がいいことが前提だが。
中略
臨機応変に得意先の心に対応出来る営業マンが、結局は可愛がられ、結果としてより多く売ることになる。
営業マンの心の在りようがきっと商売に反映される。
ただビールが売れればいいというわけじゃない。
売った後が大事だ。
そうでなければ得意先と長いつきあいなんて絶対に出来ない。
俺という商品のファンをつくること。それがビールの売り上げにつながると思う。
こういう話は耳タコ目イボになるくらい聞いたり、見たりしてきたが、物語の筋立ての中で反芻させられると、改めてそうだなあと思う。
ああ、まだおさらいは半分程度だ。
その6では終えることが出来るだろうか。
ここではあと少し、気に入ったセンテンスを。
根拠のない自信がじわっと湧いてきた。
酒屋とつきあううちに、明日をも知れぬ商売の緊張感がわかってきた。
個人商売の緊張感と心地よさは、宣伝部時代には決して想像出来なかったものだ。今の俺には営業に飛ばされてつらいという感情は全くない。酒屋の気持ちに寄り添えるようになったのは、俺にとって大きな変化だ。
今は、酒屋商売の楽しさ苦しさ、その酒屋にビールを買ってもらうセールスの思いも体でわかってきた。
ふと思い出した。
大学4年のときに、父が、郷里の市役所の試験を受けてみないかと連絡をよこした。
知人のコネクションで有利にことが運ぶとのことだった。
それが事実かどうかは別として、私は全くその気がなかった。
後年、時々一緒に飲みながら、「市役所ならお日さん西西で楽でええのに、なんでかのう。」と笑っていた。
私は、自分の通信簿が数字で如実に出る世界の方が自分に向いていると思ったのだ。
今でもその気持ちに変わりはない。
だが、悲しいかな、現在の私の通信簿はどんどん劣等生になっている・・・
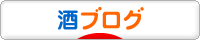 ランキング
ランキング
この部分が一番考えさせられたように思う。
かなり引用部分が長くなりそうだから、極力端折っていこうと思う。
シチュエーションは、メーカー営業、地域問屋専務、酒専門小売店店主の三人がビール販売に収斂したそれぞれの見解を述べ合うといったところ。
こういうのを鼎談というのであったか。
酒屋「先ず、人と人とのコミュニケーションありき。その後でモノは動く。天気の話はどうでもええように見えて、実はどうでもようないんよ。」
メーカーひとりごち「そうだろうか?たかがビールを買うのに、そんな煩わしさは不要だ。」
酒屋「人生たかだか80年。巡り会う人の数もしれとる。そういう出会いを大切にしたい。売ることばっかあくせく考えとると、結局、人生、何も残らん。」
メーカーひとりごち「俺や酒屋のオヤジにとって一番大事なのは1本でも多くビールを売ることだ。商売して金を貰っているくせに、何を偉そうにほざいてる。」
ここで酒屋が持ち出したのが瘤取り爺さんの話。
「天真爛漫な爺さんは鬼と楽しく遊んで、翌朝、瘤が取れていた。計画的でマーケティング派の爺さんは、瘤を取ってもらおうと鬼の宴に出掛けたが、かえって瘤をつけられた。」
専務「瘤を取ってもらった爺さんは心がオープンやった。変化を受け入れ素早く対応出来た。夏海(酒屋)さんは瘤をつけられた爺さんのような企みは世の中に通用せんと悟った人じゃ。いや、企みを企みに見せんように、巧妙に天真爛漫、自然さを装うておる。じゃが、普通の人があんたのように普通に商売するのは難しい。先ずはわかりやすい商売のテクニックを学ばんといけん。そのためには誰にでもわかるノウハウが必要じゃ。夏海さんがいくら文化を大切にしていても、酒屋は酒屋。あくまで商売じゃ。」
メーカーひとりごち「夏海(酒屋)さんはちゃんと売ることを考えている。それを嫌らしく見せないためにオブラートに包む。だから葡萄屋(酒店)には人が集まり、商売が成り立つんだ。」
メーカー「酒は嗜好品です。美味しいかどうかは人それぞれ。でも、美味しいだけでは売れません。パッケージがカッコよかったり、宣伝が好きだったり。酒はイメージで売れていく部分が大きいです。たとえば、個性を大切にする夏海さんがビールを売ると、売られるビールがいくら画一的な大量生産品でも個性的なビールになり得ますよ。」
以上の部分が、妙に考えさせられる。
建前と本音が交錯して葛藤しつつも、「商売は人なり」であるし、その根本的な方針、気持ちの持ちようは、突き詰めれば、人生観に行き着くのではなかろうか。
反面、商売とは職業であり、職業とは食い扶持であればこそ、儲けることが出来なければ、文字通り食ってはゆけぬ。
だからこそ、建前と本音のギャップに喘ぐことにもなる。
結局堂々巡りのようだが、人は食うために生きているのではなく、生きるために食うのだから、「如何に生きるか」が芯となるべきだろう。
商売とは人と人との心に橋を架けること
この辺りまでくると酒乱の主人公の中に酒に対する愛情が芽生えてくるようになる。
以下は主人公のスタンス。
「売る」というのは、「こっちの思い通りになって欲しい」という勝手なベクトルだ。買う側には選択肢はたくさんある。
中略
買う側に何かメリットがなければモノを買わない。
メリットを「幸せ感」と言ってもいい。
その結果モノは動く。
無理矢理動かそうとしてもモノは動かない。
客はセールスマンの人格や、企業の社格を見てモノを買う。
勿論、商品の質がいいことが前提だが。
中略
臨機応変に得意先の心に対応出来る営業マンが、結局は可愛がられ、結果としてより多く売ることになる。
営業マンの心の在りようがきっと商売に反映される。
ただビールが売れればいいというわけじゃない。
売った後が大事だ。
そうでなければ得意先と長いつきあいなんて絶対に出来ない。
俺という商品のファンをつくること。それがビールの売り上げにつながると思う。
こういう話は耳タコ目イボになるくらい聞いたり、見たりしてきたが、物語の筋立ての中で反芻させられると、改めてそうだなあと思う。
ああ、まだおさらいは半分程度だ。
その6では終えることが出来るだろうか。
ここではあと少し、気に入ったセンテンスを。
根拠のない自信がじわっと湧いてきた。
酒屋とつきあううちに、明日をも知れぬ商売の緊張感がわかってきた。
個人商売の緊張感と心地よさは、宣伝部時代には決して想像出来なかったものだ。今の俺には営業に飛ばされてつらいという感情は全くない。酒屋の気持ちに寄り添えるようになったのは、俺にとって大きな変化だ。
今は、酒屋商売の楽しさ苦しさ、その酒屋にビールを買ってもらうセールスの思いも体でわかってきた。
ふと思い出した。
大学4年のときに、父が、郷里の市役所の試験を受けてみないかと連絡をよこした。
知人のコネクションで有利にことが運ぶとのことだった。
それが事実かどうかは別として、私は全くその気がなかった。
後年、時々一緒に飲みながら、「市役所ならお日さん西西で楽でええのに、なんでかのう。」と笑っていた。
私は、自分の通信簿が数字で如実に出る世界の方が自分に向いていると思ったのだ。
今でもその気持ちに変わりはない。
だが、悲しいかな、現在の私の通信簿はどんどん劣等生になっている・・・
 | ビア・ボーイ新潮社このアイテムの詳細を見る |





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます