囁きから凱歌まで、明滅する点だけで描かれる連打音の最高傑作、リストの「ラ・カンパネラ」を暗譜した。
遠くから響くこだまのような前奏は、各変奏のクライマックスで常に収斂するDis 音連打のさり気ない前兆。
H dur に始まり次々と転調していく第2の主題は右手から左手へ、左手から右手へ、精巧に飛び火する。
一方、終結部へなだれ込む、反行するオクターブの半音階は、最後の方で半音をはしょり、両手の黒鍵、白鍵を一致させ、弾き易くしている。*
優れたピアノ曲は「2つの手」ではなく「10本の指」のために書かれたものだと言われるが、この曲こそまさに。
僕が幼児の頃親から初めて買ってもらったレコードには「エリーゼのために」、パデレフスキーの「メヌエット」に続き、この曲が入っていた。
* 128小節目の最後の4つの16分音符
右手:[H] 全音 [Cis◎] 半音 [Cisis] 半音 [Dis◎]
左手:[Fisis] 半音 [Fis◎] 全音 [E] 半音 [Dis◎]
(◎ 黒鍵)![]()
==フランス人Guillaumeさんのコメント==
128小節目の最後の4つの16分音符が半音階から外れて、両手の白鍵、黒鍵が一致しているのは分かった。けれどなぜ?演奏上の理由では無いのではないか。127小節目や128小節目の頭はそうなっていないから。和声的な理由ではないの?
==僕の返答==
128小節目の最後だけ半音が省かれているのは、127と128小節目はドミナントで、129小節目の頭でトニックになるから。半音階のすべての半音は経過音として扱われ、和声には一切影響を及ぼさない。ピアノ曲の書き方は演奏し易いことが重要で、調性の選び方も同様。もし「ラ・カンパネラ」がイ短調で書かれていたら演奏し難いよ。いわばこれはピアノの楽譜を3次元で読み解く考え方だ。![]()
![]()
最新の画像[もっと見る]
-
 アルトフルートのための"The Salutation" 再演
8年前
アルトフルートのための"The Salutation" 再演
8年前
-
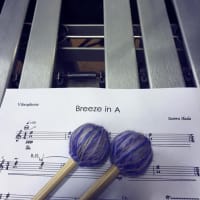 《Breeze in A》の指揮/YouTube
10年前
《Breeze in A》の指揮/YouTube
10年前
-
 島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)
13年前
島村楽器ピアノフェスティバル語録(第8回~第10回)
13年前
-
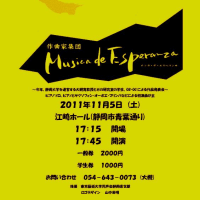 アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定
13年前
アルトサックスとピアノのための《詩篇》初演予定
13年前
-
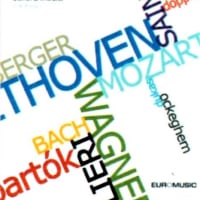 ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版
14年前
ユーロミュージックから「ショパンのノクターン」楽譜出版
14年前
-
 6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定
14年前
6手のための「ショパンのノクターン」編曲/初演予定
14年前
-
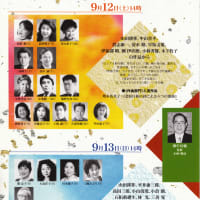 バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂
15年前
バリトン歌曲《月》再演/奏楽堂
15年前
-
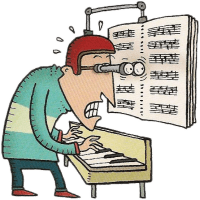 初見課題曲
17年前
初見課題曲
17年前
-
 ウィンドオーケストラ作品の委嘱
19年前
ウィンドオーケストラ作品の委嘱
19年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます