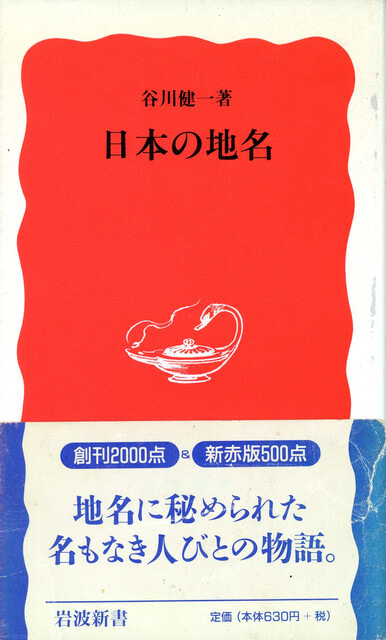
1997年・岩波新書
山名、地名の読みというのは甚だ難しく、いつも苦労させられる。それは、こうした固有名詞には、それぞれの歴史的、地誌的な意味、つまりはそれぞれの地域の文化があって名付けられているからであり、また、長い時間の営為の中や、その土地土地の風土によって名前が変化(訛ったり、省略化されたり)してきている場合もある。さらに、後付けによって特殊な意味合いを付与されるなどということもあるので、一層複雑になってくる。そのような事情もあって、およそ当てられている漢字にのみ囚われていると、頓珍漢な方向に行ってしまったりすることもあるのだ。山名(地名)というのは、読みから辿らなければならないのである。逆に言えば、名前と、その変化してきた経緯(当てられた漢字を含めて)から、その土地の時間の流れ、風土などを垣間見ることもできるのである。
日本語の文字(漢字)というのは、万葉の時代、中国から輸入されたもので、当初は漢字の音のみを当て字的に利用し、和語(本来の日本語)を表記していた。例えば万葉集などを見れば、そこに使われている漢字が全く意味を持たないものであり、仮名として利用されていることがわかる(万葉がな)。当然のことながら、文字(漢字)がもたらされるずっと以前から、言葉(和語)は存在していたのであり、人々は周りの様々な事物、事象に、名前を付けていたのである。また、文字(漢字)が地方の一般民衆にまで広く利用されるようになるのは、さらに長い時間を経て近世に入ってからであり、ローカルなものである山名や地名に、最初に文字ありきということは少ないと思われる。
山名を読むとき、まず頭を悩ますのが、[やま]と読むか、[さん]と読むかということだろう。前に来る名を訓読みしていれば[やま]、音読みしていれば[さん]であることが多いと思うが、必ずしも全てに当てはまるわけではない。例外では、近くに高根山(たかねさん)がある。信仰対象の山を[さん]と呼ぶという説も聞いたことがある。これは、お稲荷さんとか、八幡さんとか呼ぶのと同じ感覚という意味か。確かに高根山(おたかねさん)には該当するが、これとて例外はあるもので、丹沢の大山には阿夫利神社があり昔から大山詣で有名な所だが「おおやま」と読む。一方、鳥取の伯耆大山は「だいせん」と読むのだから、ますます判らなくなる(ちなみに[サン]は漢音、[セン]は呉音)。話が逸れるが、山のことを峰(みね)ともいうが、これは棟(むね)、畝(うね)などと同じ語源と考えられる。いずれも頂点を成す部分で、つまりは中心だから、胸(身体の中心)、旨(事象の核心)なども同系列の言葉なのだろう。
川根本町の大井川左岸に無双連山という山がある。以前、しばらくの間「むそうれんざん」と呼ぶと思ってきた。「並ぶものの無いほど立派な峰々」という意味合いで付けられただろうかと。これなどは、完全に当てられた漢字に引っ張られたものだった。正しくは「むそ(ぞ)れやま」であり、「ソレ(ゾレ)」は「ソリ、ゾウリ」などと共に、焼畑地あるいは崩壊地を表す言葉であるという。「剃る」「削ぐ」などと同系の言葉なのだろう。木々の無い有様や、荒々しく削られた姿が想起される。大井川流域の山間部や北遠地方には、この焼畑、崩壊系の地名が多く見られる。水窪に「大嵐(おおぞれ)」という集落があって、これも焼畑地に関連する地名であるらしいが、果たして浜松市となった現在、残されているのだろうか。
現在も進行中の平成の大合併は、功罪両面があると思うが、罪のひとつは歴史性を持った固有の地名の消失にあるだろう。民俗学者の谷川健一氏は、『日本の地名』(岩波新書)の「はじめに」の中で
私にとっては地名はたんなる標識の符号ではない。「おくのほそ道」のはじめに「道祖(岨)神のまねきにあひて」とあるが、私もここ三十年間、地名という土地の精霊に招かれて各地を旅してきた。そうしたことから本書を「土地の精霊との対話」と受け取っていただいて差し支えない。
と述べ「各地に残された地名こそ弥生の時代から近世まで、名もなき人々の暮らしの記憶を伝えてきたもの」として、その一点で平成の市町村大合併に反対されてきた。平成の合併によって失われていく小さな字名などは、全国に何万とあるだろう。その名を奪われた小さな「精霊」たちは、どこに行く運命にあるのか。花も木も鳥も動物も、全てのものは名付けられることで初めて存在する。山に対しても、その固有の名を正しく呼んであげる努力をしたいと思う。ところで、「○○ノ頭」などの頭を[あたま]と読むのか、[かしら]と読むのか、かねがね気になっている(私は[あたま]派)のだが、これはまた機会を改めたい。
(2006年10月記)










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます