先日「大室高原歩こう会」で修善寺の北側にあたる「奥の院」とその周辺を歩いてきた。
修善寺周辺には弘法大師=空海ゆかりの場所がいくつかある。
修善寺の街中には空海が独鈷を衝いたところから温泉が噴き出したと伝えられる「独鈷の湯」があり、奥の院の横を流れる湯舟川の上流には空海が突き刺した桂の杖が成長して樹齢千年を超える桂の大木となったという「桂大師」がある。
「奥の院」も空海が一八歳のときに滝に打たれながら修業したところだと言い伝えられている。
「奥の院」を出てその近辺を歩いていたら、たまたま道端に「奥の院道」という道標があるのを見掛けた。その道の名称らしい。
しばらくその道をたどったが、道に沿って一定の間隔で同じような石柱が立てられているのに気付いた。
最初に気付いた石柱の頭には「き」という文字が刻み込まれており、次に見掛けたのが「さ」、その次が「あ」という字であった。
その後すぐに帰りのバスに乗ったから、見掛けた道標は三本だけだったが、どうやらこの道には同じ石柱がいくつも設けられているらしい。
「きさあ」という文字の配列、いや反対からは「あさき」となるが、この文字列がなんだかが気になった。
一緒に歩いたI氏とあれこれ考えてみたが、これはひょっとしたら「いろは歌」の「浅き夢みし」の仮名ではあるまいかということになった。
この辺りの生まれだというバスの運転手さんにも聞いてみたが、この石碑のことは彼は知らないという。

帰宅したらI氏からメールがあり、インターネットで調べたら、この道はやはり「いろは道」で、その道標であると教えられた。
「いろは道」は、「修善寺」にある「い」から始まって「奥の院」の「ん」で終わり、全行程五キロメートル、歩いて一時間半のなだらかな登り道だとある。

「いろは歌」は弘法大師=空海の作とされているから、空海ゆかりの「修善寺」から「奥の院」に至る道が「いろは道」と名付けられているのはもっともなことだと納得した。
「いろは」にかかわる道といえば、日光に有名な「いろは坂」があるが、「いろは道」というのはこれまでに聞いたことがなかった。
大師伝説ゆかりの地は日本全国各地に散らばっているからほかにもありそうだと思い、インターネットで調べてみたが、その限りでは修善寺の「いろは道」のほかには存在していないようである。
修善寺は伊豆高原から車で一時間少しあれば行き着くところでもあり、往復一〇キロメートルの道ならウオーキングの距離としては真に手頃である。いずれ近いうちにこの道を歩いてみたいと思っている。





















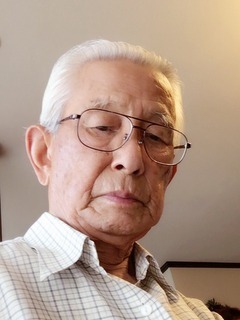





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます