7月1日 (月) 
先月22日、ようやく富士山が世界文化遺産に登録され、本日は登録後初めての山開きだという。お天気はいまひとつ冴えないが、登山道には人があふれかえっているに違いない。
これまで居所を転々としてきた割には富士山に縁があった私だが、今にして思えば、若く元気がいいときに一度だけでも富士山頂をきわめておくべきだったとちょぴり残念だ。だが、こう齢を重ねてしまったからにはもう遅い。
ところで、富士山を見たいと思えばいつでも見ることができる恵まれた当地に住んで23年、毎度ながら秀麗な富士の姿には心を癒されている。
カメラを持っておりさえすれば、変わることのない富士の眺めだがついその姿を写して写真にとどめてしまう。
顧みると、当地に来てからこれまでに一体何度富士の姿をカメラで捉えてきたことか。
いつ見てもこれほどまでに人を魅了する山がこれまで世界遺産登録されなかったことに日本人の大多数は疑問に感じていたのではないだろうか。
この半年の間だけとってみても、富士山に触れ写真に写した回数を拾い上げてみたら6度、ブログに取り入れたのは3回もある。
取りあえず、そうした写真を取り出しコラージュしてみた。

2013/1/29 「伊豆長岡の史跡をめぐる」 http://blog.goo.ne.jp/tengoro7406/d/20130131
2012/11/22 「箱根ウオーク」 http://blog.goo.ne.jp/tengoro7406/d/20121123
2013/4/8 「絶景大室山頂上」 http://blog.goo.ne.jp/tengoro7406/d/20130408
2013/3/11 「伊東市ショッピングプラザ デュオ 屋上駐車場から」
美しい富士山の姿を脳裏に描きながらあれこれ考えていたら、かつて「三金会雑記」に書いた記事があったことを思い出した。
パソコンでPDF化された「三金会雑記」の中から探し出したら、今から18年前、当地に住んで5年目になる「三金会雑記32号」に「富士山麓オウム泣く」と題して一文を寄せていた。
オウム真理教事件が世間を騒がせた頃のもので、あまりにも古く、なんとも時代には合わないが、これが私の「富士讃歌」であることは今も変わらない。
PDF文書からテキスト文書に変換するのは簡単なので、これを貼り付けてみた。
富士山麓オウム泣く
一年で最も美しく自然が息づく爽やかな五月だというのに、このところ雨模様の日が多く、農作業ができないまま家に引きこもることが多い。
そのため日頃は余りTVを見ることが少ない私だが、サリン事件をはじめとするオウム真理教が引き起こした一連の事件の報道を、同じことの繰り返しだとブツブツ文句を言いながらも、午前、午後、そして深夜まで、ひっきりなしにチャンネルをあちらこちら変えながら見ることになってしまった。
これは全く奇怪至極な事件で、その規模の大きさ、事件内容の複雑・多様さ、そして事件に登場する人物の異様さなどは劇画そのもので、日本犯罪史上に類をみない妄想軍事集団が引き起こした恐るべき組織犯罪であるようだ。
この不可解な事件によって、これまで刑事法上ほとんど学問的関心を惹くことがなかったといえる内乱罪や破防法などに関する論議が高まることになり、学者諸先生の甲論乙駁、勝手気ままな論議が関係文献の紙数を埋めることになるであろうが、こんな機会だからこそ坂口裕英大先生なども奮起し、「雑記」の中で「女のおっぱい」などと白昼夢みたいなことを言うのはやめにして大いに論陣を張り、法学者としての名を高めて欲しいものだと願っている。
ところで、この事件の主要な舞台は上九一色村である。TV報道では繰り返し繰り返し、この村に存在する一群のサティアンとやらいう怪しげな建物を富士山を背景に映し出している。
そのためか、あの秀麗な富士山が、いつのまにかオウム専用の山であるかのような印象を与えてしまい、なにか禍々しい不吉な山に感じられるようになったのはなんとしたことか。
オウム真理教はあの秀麗な富士山をすっかり貶め汚してしまっているようだ。
この上九一色村だが、この村名は今やオウム真理教によって日本全土に知れ渡ることになった。
だが、実は私個人はこの村を今回の事件で初めて知ったというわけではない。
今から20年も前になるが、甲府に2年間勤務したことがあり、ちょうどその時期、自動車の運転免許を取ったものだから、車を運転することが楽しくて、毎週のように休日には山梨・長野県下の観光地を車で徹底的に走り回ったことがあった。
そうした観光地の中でも、特に富士山を湖面に映す富士五湖は、甲府市から御坂トンネルを抜けるか、精進湖有料道路を通れば、1時間もあれば行き着け、2,3時間のドライブコースとしては絶好のところだった。
そんな富士五湖の中でも本栖湖は大きい方に属し、また東京からもっとも外れたところになるため、観光施設とは無縁で当時は人工の手がほとんど加えられていず、五湖中もっとも水深があるというその青い湖面に、自然のままの素朴な樹林を麓に据えた富士山の姿は私の最もお気に入りのものだった。
その本栖湖付近から広々した朝霧高原にいたる一帯があの上九一色村なのである。
昭和50年の元旦には、その上九一色村の朝霧高原で富士山の麓から立ち昇る初日を拝もうと家族を引き連れ深夜に出かけたことがあった。
前日の大晦日に下見をして、ここぞと決めておいたポイントの高台は漆黒の闇だったが、そこに車を停めて、東方の暗い空を背景に黒々と聳え立つ富士山の影を見ながら日出を待った。
やがて、次第に暁の空が赤みを増し、周囲が徐々に明るくなっていくにつれ富士山の影は刻々とその色彩を変えていき、間もなく裾野近くの稜線から元旦の太陽が真っ赤に燃えて姿を現す。
そして、その太陽がやがて白銀の輝きに変わる頃、雪を頂いた秀麗な富士山の全容が圧倒的な迫力を以てくっきりと浮かび上がってくる。
真冬の高原の早朝だから寒気だけは物凄く、車の暖房がなければとてもおられるものではなかったが、その感動的な一瞬の光景は今でもまざまざと思い出すことができる。
今回の事件は、そうした貴重な思い出のある場所の富士山をすっかり汚してしまったのである。誠に苦々しい限りである。
そんな想いの中で「富士山麓」とか「オウム」とか何気なく口の中で 呟いていたら、ふっと、この言葉、どこかで聞いたことがあるという奇妙な思いにとらわれたのである。
いつだったろうか、どこだったろうか、古い記憶の糸をたどり寄せ、どこか記憶の襞に潜んでいるかもしれないものを探っていたら、ついに思い出したのである。
そうだ、中学時代の数学だ。古い記憶の底から浮かび上がってきた言葉。それは「富士山麓鸚鵡鳴く」。
平方根、そうだ平方根だと思ったら、突如一連の数字の記憶が甦ってきた。
ルート2は「一夜一夜に人みごろ」 √2=1.41421356 、ルート3は「人並みにおごれや」 √3=1.7320508 、そしてルート5とは「富士山麓鸚鵡鳴く」 √5=2.4360679 ではなかったか。
驚くべきことだが、50年以上も前に中学生の頭に叩き込まれた一連の数字、以後は文系に進んだため二度と思い起こす必要もなくまったく忘れていた数字が忽然と頭に浮かんだのである。なんと昔の中学校の詰め込み教育はすごかったんだなァ。
それにしても、これは誠に奇妙な一致だ。まさにXデーまじかの現状は「富士山麓オウム泣く」ではないか。
まさかオウム真理教がルート5を意識してこの土地を選定したわけでもあるまいに……。
世の中には不思議な一致があるものだと仰天する想いだが、このことに気付いていた人、ほかにも誰かいるのだろうか。
(注)ここで思い違いがないか念のため検算してみた。ところが「フジサンロクオームナク」2.4360679を2乗してみたら、5の近似値にはならないのである。記憶した文句に間違いはないはずだがと、身近なところにいる理系の元秀才上野君に電話で聞いてみた。
さすがである。「フジ……」の「ジ」は「4」ではなく、「次」つまり「2」だよと。
2.2360679×2.2360679 でなるほど正解となった。暗記用の言葉は正しく記憶していても肝心の数字を誤っていてはどうにもならない。かくて文系頭脳のお粗末さを改めて思い知らされた。
ところで、こんな風に、今はすっかりオウムに汚されてしまった霊峰富士山だが、この機会に私の「富士山讃歌」を書いて、その名誉回復を図ることにしたい。
私と富士山との縁は、九州人にしては特に深いものがあるといっていいであろう。子供の頃年に何回か高台から遠く富士山を望めた東京の荻窪に居たことがあり、20年前には山合から頂上を覗かせた富士をいつも見ることができる甲府市の宿舎に2年間住んだことがあり、そして今は富士を望める伊豆東海岸の高台を永住の地として23年になる。
山梨県から見る富士山を「裏富士」といい、静岡県から見る富士山を「表富士」というようだが、昔からこの両者の間ではどちらがより美しいかもめぐってそれぞれ地元の身贔屓もあって激しく競われている。
江戸時代の酔狂人だった太田蜀山人に有名な狂歌がある。
「裾野より 捲り上げたる富士の山 甲斐で(嗅いで)みるより 駿河(するが) 一番」
だが、これは猥雑な言葉遊びの類で、この美人コンテストの客観的評価ではない。
実際は、駿河からみる「表富士」は、宝永年間の大噴火でできた宝永山がなだらかな稜線の一部をそのでっぱりで崩しており、減点されることは明らかだ。
しかし、同じ「表富士」でも伊豆から眺める富士山となるとこれは文句なく美しい。特に戸田や土肥といった伊豆西海岸からの眺めは駿河湾を隔てて富士山が高々とそびえ、宝永山の隆起は前面にくるから稜線を乱すことなく素晴らしい眺めである。
海岸からでなく高台からの眺めとしては、私は西伊豆スカイラインに入る手前の達磨山レストハウスからの展望を推奨したい。
そこからの富士山は、いつだったかの万博に写真が出品されたとの説明板があり、なるほどさもありなんと納得させられる見事さである。
同じ伊豆でも私の住む東海岸では、いながら富士山を望むことは難しい。しかし、大室山や小室山では頂上だけでなく麓付近でそれなりにかなりの大きさで見ることができる。
我が家から歩いて30分ほどのところにある大室山麓にある駐車場へ向かう坂道を登り切った前面には、おおかたの予想を超える大きさで富士の全容をみることができる。
こうした優美な「表富士」に比べて、山梨県側から見る「裏富士」は山襞が深く切れ込み荒々しく男性的な厳しさを見せているが、こちらを好む人も結構多い。
甲府市街からでは前山の御坂山系が邪魔して頂上付近しか見えないが、河口湖に向かう御坂トンネルを潜り抜けると、暗い視野が俄かに開けて、眼前一杯に広がる河口湖の上に聳え立つ富士の威容に接すると初めての人は必ず感嘆の声を上げる。
また、太宰治の「富士には月見草がよく似合う」という句碑のある旧道の御坂峠から眺める富士山は、朽ちかかった峠の茶屋が廃屋としてその頃は残っており、辺りの鄙びた味わいにマッチする独特の美しさがあった。20年も前のことだから、あの茶屋が現存しているとは思われないが……。
その他には、かつての500円札の裏に印刷されていた三ツ峠山からの富士の姿もよく知られている。いずれにせよ、「裏富士」は野性味を帯びた美しさがその魅力である。
ところで、富士山という山は一年中いつでも見えるというものではない。季節としてよく見えるのは空気がよく澄んでいる冬で、春と秋はよく晴れたさわやかな日、そして夏の間は月に数度、よほど機嫌がいいときに顔を見せる程度で、それも頂上付近に雲がかかって、全身を見せてくれるようなことは少ない。
時間帯でいえば、早朝が最もよく、午後になると雲が出て山頂を隠してしまうことが多い。
そして「表富士」では朝日が白い雪の衣をピンクに染め上げる明け方が絶品で、これは一般に「赤富士」と呼ばれている。
この「赤富士」の現象は「裏富士」では夕日に映える姿となり、韮崎辺りの国道でたまに見かけたが、これもなかなか見応えがあった。
思うに、富士山の知名度はあまりにも高く、そのためその美しさも却って通俗的なものにとられがちである。銭湯の富士山の絵もそうだし、「来てみれば 聞くほどもなし 富士の山 ……」と富士山をコケにする歌があるのもその反映であろうか。
しかし、美しいものはやはり美しいと素直に認めるげきであろう。
日本だけでなく、おそらく世界でもこれほど完璧な美しさを持つ山はないのではなかろうか。
こんな山をこの極東の小さな島国に持てた日本という国は、本当に自然に恵まれた国、オウムの神ならぬ本物の日本古来の神が作りたもうた比類なき山、そして国だとこころから思うのである。





















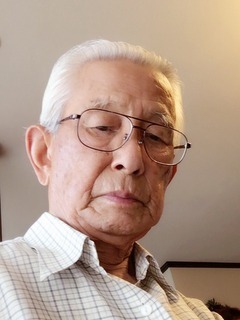





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます