11月20日 (月) 
伊豆諸島についての話の続きである。
伊豆半島の東方沖から南にかけて点々と連なる伊豆諸島は、明治9年に静岡県の管轄となった直ぐあと明治11年には東京府に移管されているので、いまは我々が所属する「静岡県」とは無縁の存在となっている。
しかし、伊豆半島東海岸に住む私としては、これらの島々はごく身近な存在、行政上所属している「静岡県」の他地域と比べても古くからの「伊豆」という名でくくられる同一地域のような思いもあり、そんな島々にかかわる神話もしくは伝承には興味がそそられる。
最近、この島々の誕生とその名称に関する神話というか伝承が記された古文書「三島大明神縁起」「三宅島薬師縁起」というのがあることを知った。
原典を直接読む機会には恵まれないが、これを基にして民俗学者として知られる谷川健一が「列島縦断地名逍遥」という著書の中で伊豆諸島の誕生にまつわる伝承、そして島名の由来について記している。( 「伊豆の島々(新しい造島神話)」という部分)
内容は極めて簡単で稚拙なものだが、古くからの言い伝えとはそんなものだろう。
以下、その文意を省記してみた。
伊豆の島々の造島神話
天竺から来たという王子が富士山頂の神の許しを得て、「三島大明神」と名乗って伊豆の海中にいくつかの島を焼きだした。
三島大明神は、配下となった「若宮」と「剣」という名の男の子、「見目」という女の子に命じて龍神や雷神をやとって大規模な島焼き作業を行なった。
すなわち伊豆の海中に大きな石を置いて、火雷が焼き、水雷が水を注いで一日一夜で一つの島を出現させた。続いて七日七夜かかって十の島々が焼き出された。
(これは、つまり火山噴火により島々がつぎつぎと作り出されたということ。)
三島大明神は最初に焼きだした島を「初島」と名付けた。次に第二の島は神々が集まって詮議したところなので「神集島」と名付けた。
第三の島は大きいので「大島」とし、第四の島は潮の泡を集めて作ったので色が白いことから「新島」、第五の島は家が三つ並んだ格好をしているので「三宅島」、第六の島は明神の御倉としたので「御蔵島」、第七の島ははるか沖合にあるので「沖の島」と名付けた。
第八の島は「小島」、第九の島は「オウゴ島」。第十の島は「十島」と名付けた。
「沖の島」とは一名ヤタケ島、「八丈島」のこと、第八の小島は「八丈小島」、第九の島「オウゴ島」は「青ヶ島」、第十の島は「利島」だとみられる。
内容的はなんともたわいのないものだが、島々の名が列挙され伊豆の諸島がまとめられているのが面白い。
ふむふむ、そういう古伝があるのだな、頼りない短い文章ではあるが私には興味ぶかかった。
なお、なぜかそこに「式根島」が触れられていない。
式根島はなぜかいつも伊豆諸島の中で軽視されている。
これは式根島はかつて新島と地続きの一つの島であり、地震・津波によって分離されて別の島になったという言い伝えがあるからであろうか。現在でも式根島は行政区として独立していず、新島に属しているという。
伊豆諸島の位置関係





















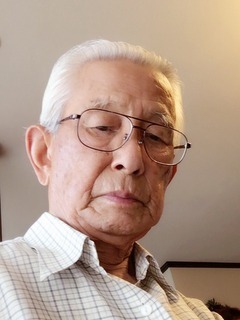





大変興味深い話で参考になりました。
・どこかの誰かに知ったかぶりして離してみたい衝動にかられます(^_-)-☆
もう直ぐ19年になります。
伊豆七島が身近な島で、自宅からも
3島が見えますが、上陸したのは
伊豆大島のみです。友達が遊びに来た
時に、知ったかぶりをして、島を説明して
いるのですが、1、伊豆大島 2、利島
3、式根島(新島とも言う)4、神津島
5、三宅島 6、御蔵島 7、八丈島
これぞ伊豆七島だ~よく言えた~
ONさんの、コメントを見せて頂き
奥が深い島々の事が、良く解りました
一つだけ、疑問があります。
ウブド島の事が、無い様ですが
今度、聞かせてください。