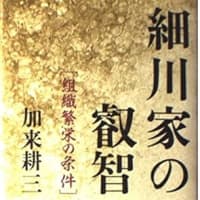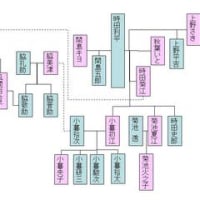辛亥革命で孫文が大総統になる臨時政府が樹立され、国号も中華民国となったが、まもなく旧軍閥を背景とする袁世凱が共和政体を宣言するに至った。孫文は事態を収集するため袁世凱に地位を譲った。この間、各国から政治的介入があり英国、ベルギー、米国、日本などが大陸に進出を図った。世界大戦が勃発したのはその後、日本は戦勝国としてドイツの租界地を譲渡された。そして袁世凱に対して21か条の要求を提出した。石光真清はこの行為を中国のメンツを潰す愚行と避難、過去300年にわたって欧州諸国が東洋で強行してきた植民地手段に日本も手に染めてしまったと嘆いた。こうした中、弟の真臣は真清に支那錦州での貿易商社設立を進めたのであった。そしてそのビジネスは順調に推移した。
しかし、その時、軍からの要請でブラゴベシチェンスクに赴いて情報収集を行うことを依頼されてしまう。当地には日本人7千名が住んでいて、ロシア革命下の混乱で、革命軍、清国軍、旧体制勢力が入り乱れる中に、連合国からのシベリア出兵がちらついていた。そこに石光機関を設置する。石光機関には鳥居肇三を始め6名と安倍道瞑師がいた。この陣容で活動をするが、ロシア内政干渉となることになる、シベリア出兵という日本の方針と現地の状況が錯綜し、日本人居留者の立場が難しい。コザック首脳部に日本人居留民は協力する、という約束をするが、それが関東軍総督府の方針と食い違い、陸軍大臣名で、越権行為をとして咎められ任務を解除されてしまう。
世界情勢も複雑化していた。レーニンはドイツとの友好関係を宣言するが、ロシアでボヘミア王国以来の祖国復活を夢見るチェコスロバキア軍はレーニン政府の承認を得てシベリアを横断、ウラジオストクから太平洋、大西洋をわたり独墺軍と戦うことになる。この途上チェコマサリック博士は日本にも援助を求めたがアメリカの顔色を伺い態度を明らかにしなかったため米国に渡ったのである。こうした中で、ブラゴベシチェンスクのアムール政権は経済的に破綻、ロシア革命軍の勢いが増してきた。こうした中、石光真清は現地のロシア人と情報を交換しながら、ロシア革命後のソビエト連邦では日本人には居留を続けることはできないと判断、退去を決める。
石光真清はウラジオストクの大井司令官を訪ねて、日本軍のシベリア出兵についてその真意を正す。しかし、司令官からは「一体誰のために働いているのだ」と逆に叱責される。その場で司令官と言い争いになり任務を解かれる。一体誰のために、という問いは石光真清本人にとっても自問自答、答えに窮する問題であった。
石光真清は自伝であり、日本の大陸進出の側面史であり、日露戦争を描いた場面や、支那での馬賊とのやり取りなどは普通の歴史書では得られないことばかりである。日露戦争には辛うじて勝利した、と歴史では習うが、戦場ではロシアの近代兵器に押しまくられて、兵士たちの国家成長に対する責任感がかえって戦死者を多くし、ロシア軍も極東での戦いにつかれたことが終戦につながったのであり、決して勝利したと言えるような終わり方ではなかった。石光真清本人の生涯も日露戦争のようなものではなかったか。家族を得て、子供にも恵まれたが、家族は本当に幸せだったのだろうか。手記をまとめた子の真人に、真清は次のように言っている。「将来も決して大陸へなんか行くんじゃないよ。内地で良い家庭を持ち良い仕事が出来ればそれが一番さ。大陸に行くにしても、お父さんのように出発点を間違うとどこまでも外れてしまってね、時が立つほど正道に戻れなくなってしまう。物事は初めが大事だよ。」
この手記で明らかに書かれている明治時代の日本人の心、武士の心が生きていると感じる。明治日本人をもっと学んでみたい。誰のために―石光真清の手記 4 (中公文庫 (い16-4))