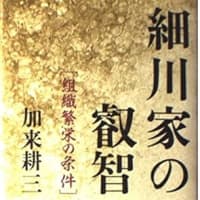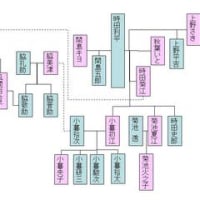観光で訪れる京都は、歴史ある寺社、祇園を歩く舞妓さん、そしておいしい食べ物、と旅行者にはたまらない訪問先だと思いますが、歴史があるというのはしがらみが多いということ。よそ者にも想像はできるが京都の知りえない部分を取材している。
1. 寺社 浄土真宗の大本山である本願寺には西と東がある。西はもともとある本願寺、東は家康が保護した大谷派。その大谷派では昭和37年の「お東さん騒動」で親鸞の子孫が就任してきた門主と宗門改革を目指した宗派の行政部門である内局が対立した。昭和55年に門主は法主となり、実権は内局側に移った。宗門の最大のイベントである報恩講には門主が法要を行うはずだが遺恨を残していた法主は現れない。法主は大谷ホールで開催されていた全国大会の方に参加していたのである。そして浄土宗の大本山は知恩院、これも家康が徳川初代に分断を図っていて、江戸に増上寺を設置していた。それが、現代になって東西対立を招いた。こちらの門主は東の増上寺が勝ち取った。全国のお寺にまで及ぶ権力と数百億といわれる予算に対する権限をにぎる、それが対立の根源である。本願寺派も大谷派もいずれも予算総額年間200億といわれるが、それ以外にイベントへの寄進など膨大な額に上る。しかしそうした宗派からの締め付けを嫌って宗派離脱が起きている。それも本山自身が離脱したのが東寺、真言宗の本山が真言宗を離脱、東寺真言宗と名乗った。同様に、北法相宗の本山である東山・清水寺も宗派を離脱、天台宗に属していた洛北・鞍馬寺は鞍馬弘教総本山となっている、洛中・聖護院は天台宗に属したが、本山修験宗として独立、それぞれ宗派から離脱している。つまり自分のお寺で財政的に自立できるなら宗派に拘束されることのメリットはないということ。
2. 家元 お茶の千家は三代目宗旦の時代に表、裏、武者小路の三千家に分かれた。千家には十職といわれる職人集団がいるが、原則的に千家以外の仕事はしないといわれる。塗師の中村家、楽焼の楽吉家、袋物師の土田家、指物師の駒沢家、釡師の大西家、一閑張り細工の飛来家、金物師の中川家、表具師の奥村氏、柄杓師の黒田家、土風炉師の永楽家である。千家は先生と門弟を結ぶ免状制度で成り立つ。表千家では8段階あり、入門、習い事、飾り物、茶通、唐物、台天目、盆点、乱飾までで、唐物が地方講師、盆点が教授、乱飾は家元自身が許可する。裏は18段階、武者小路は10段階ありこれらから得られる免許料は収入であると同時に組織力の源泉ともなる。
3. 花街 京都には5つの花街がある。それぞれに踊りのイベントがあり、春には祇園甲部の都をどり、宮川町の京をどり、上七軒の北野をどり、先斗町の鴨川をどり、秋には先斗町の鴨川をどり、祇園東の祇園をどりがある、舞妓と芸妓が総出演して芸事を披露する。スポンサーたる各企業、室町のお店には観覧券が送られてきてご祝儀とともに他の請求書とともに払い込まれる。これは交際費であるが認識としては広告宣伝費として処理されるという。
4. 御所 昭和21年にGHQは御所の接収を要求したというが、当時の宮内庁は拒否、御所内の木立を切り倒して幹部たちのハウスが立ち並ぶことに大反対した。このおかげで現在の静かな御所のたたずまいがある。この御所の大通りにひかれている白砂、建物の屋根を葺く檜の皮が不足、職人たちも不足していて30年に一度の大修理が滞っているという。江戸時代まで御所の中にあった公家の家は立ち退きを命じられたが、御所に面する北側にあった冷泉家だけは立ち退きをまぬかれた。書院づくりの母屋、土蔵などが重要文化財に指定され、定家の「明月記」、「古今和歌集」などのご文書などとともに歌会や年中行事などを歴史的な文化として守っている。
5. 室町の商人 室町とは室町通りを中心に東が高倉、西は西洞院、北は二条、南は五条あたりまでとされる南北2キロ、東西700メートルに1500件の会社がひしめく。売り上げは1兆円を超え、伝統を守りながら代替わり、商売替えを経て平安京創建時から生き延びてきている。
6. 共産党 京都は全国で一番共産党が強い土地、1923年に非合法で立ち上げされた京都の共産党、最初の党員は6名、そのうち4人が西陣の職人の指導者で、のちに衆議院議員となった谷口善太郎は清水焼の職人だった。戦後の28年間知事を務めた蜷川虎三の与党を社会党とともに務めたのも共産党である。イデオロギーでは共産党にアレルギーを持つ人たちも、京都の共産党を支持する。それは日常の商売の困りごと相談に乗る民商、機関紙赤旗の読者拡大努力、そしてアンチ権力、アンチ東京、アンチ自民党、という反権力志向からきているという。
ここまでが本書の内容。取材された内容の不足を感じるのは京都の奥底にある「やくざ」と「」が入っていないこと、大新聞の限界か。京都のやくざは上記勢力と対立と協力関係を結び、は解放活動の流れの中で各勢力と対立と協力を繰り返してきた。これらを踏まえなければ京都の裏社会は語れないはずである。