なんか駄洒落のようなタイトルになってしまった。
先日、小さなリードオルガンを修復して納品しました。
納品先は、特別養護老人ホームです。
そこに入所しているおばあさんのための楽器です。
最近、リードオルガンが、介護用品にカテゴライズされたりします。
たしかに、演奏をするという行為はとても良いですし、みんなで歌ったりすれば、他の多くの人達の助けにもなるでしょう。
そのおばあさんが幼い頃から家にあったオルガンだそうです。
大正時代の保証書が付いていたので、1910~1920年代の楽器でしょう。
アンティーク家具修復のイディオムに従って、傷や割れは補修しますが、全体の塗装を完全にやり直すことはしていません。
傷なども時間の履歴として保存されるべきものと考えるのです。
絵画や彫刻作品の修復も同様の考え方に基づいています。
もちろん、いたみがひどい場合や、お客様からのリクエストがあれば、全体を完全に塗装し直すこともあります。
僕も、普段オルガンの話をする時、当たり前に歴史的時間を語っています。
1800年代半ばがどうのとか、紀元前3世紀がどうのなどと。
自分が存在していない時間です。実感のない時間です。
でもこうして、現実の時間を生きて来た人が、同じ時間を過ごして来たモノと再会する時に感じる時間の重さというのは、いったいどういうものだろうかと思います。
歴史を語るときに、人ひとりひとりが重ねた時間に対する想像力を無くしてはいけないと改めて思ったのです。
年代を単なる時間のものさしと考え、その中での出来事を単に事実の羅列や数値にしてしまう、これは歴史を扱う時にはやむを得ないことではありますが、時間の重さに対する敬意みたいなものは常に持っていたいものです。
先日、小さなリードオルガンを修復して納品しました。
納品先は、特別養護老人ホームです。
そこに入所しているおばあさんのための楽器です。
最近、リードオルガンが、介護用品にカテゴライズされたりします。
たしかに、演奏をするという行為はとても良いですし、みんなで歌ったりすれば、他の多くの人達の助けにもなるでしょう。
そのおばあさんが幼い頃から家にあったオルガンだそうです。
大正時代の保証書が付いていたので、1910~1920年代の楽器でしょう。
アンティーク家具修復のイディオムに従って、傷や割れは補修しますが、全体の塗装を完全にやり直すことはしていません。
傷なども時間の履歴として保存されるべきものと考えるのです。
絵画や彫刻作品の修復も同様の考え方に基づいています。
もちろん、いたみがひどい場合や、お客様からのリクエストがあれば、全体を完全に塗装し直すこともあります。
僕も、普段オルガンの話をする時、当たり前に歴史的時間を語っています。
1800年代半ばがどうのとか、紀元前3世紀がどうのなどと。
自分が存在していない時間です。実感のない時間です。
でもこうして、現実の時間を生きて来た人が、同じ時間を過ごして来たモノと再会する時に感じる時間の重さというのは、いったいどういうものだろうかと思います。
歴史を語るときに、人ひとりひとりが重ねた時間に対する想像力を無くしてはいけないと改めて思ったのです。
年代を単なる時間のものさしと考え、その中での出来事を単に事実の羅列や数値にしてしまう、これは歴史を扱う時にはやむを得ないことではありますが、時間の重さに対する敬意みたいなものは常に持っていたいものです。















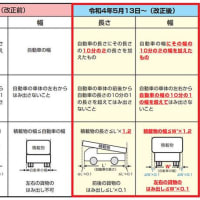




しかしリードオルガンが介護用品とは!
信じられないですね。
以前、TVで大量のリードオルガンが処分されているのを見て愕然としたことがありますが、それ以来のショックです。
世間的にはあまり良い扱いをされていないようですね。でも私は魅力のある楽器です。いつかストップのいっぱい付いたのを手に入れたいなと考えています。
リードオルガンが介護用品となり得たのは、一定期間、確実にそれが日本に定着したからです。
今のお年寄りが若い頃に、慣れ親しんだからです。
僕としては、パイプオルガンもそのように定着して欲しいと思ってやっているわけです、その音が「懐かしい音」になるように。
これからの子供達が年寄りになる頃の話ですから、僕は当然生きていませんが。
廃棄されるリードオルガンをカンボジアなどへ輸出するプロジェクトもあったそうです、電気が無くても弾けますし、半音階で音の揃っている鍵盤楽器は民族固有の音階と妥協しやすいようです。
ちなみに、リコーダーはダメだったと聞きます。
楽器というモノの主な構成素材である木は、湿度などで動きますが、生物的には「死んだ」素材です。
人間や生き物はそれぞれの時間ですべての細胞が入れ替わるというすごいシステムなのに、傷も残るし、何よりも「老化」という、物質の劣化や老朽化とは全く異なる衰え方をします。
うまくまとまらないのですが、同じ時間に存在する人とモノについて感じるところがありました。