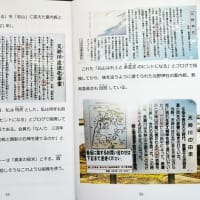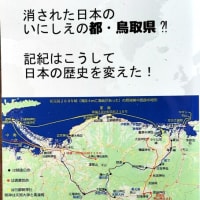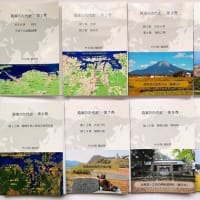記紀の神武天皇・ヤタガラスの記述以降は鳥取県中部(内つ国)が舞台であった。
1 ヤタガラス
(1)古事記のヤタガラス
イワレヒコの夢の中に、タカギの大神が現れて、次のように教えていった。「天神の御子よ。この土地から奥のほうへ深入りしてはならない。この奥には、荒々しくすさまじい神々が、多勢いることだ。今、天から八咫烏(ヤタガラス)を送り届けてやろう。このヤタガラスが道案内をしようから、その飛び立ってゆくのに従って、道をとるがよい。」このように言った。
そこで夢の中で教えられたとおりに、ヤタガラスのあとを追って旅を続けると、やがて吉野河の河上に達した。・・・。
この宇陀の地には、兄宇迦斯(エウカシ)・弟宇迦斯(オトウカシ)と呼ぶ二人の兄弟が頑張っていた。そこでまずヤタガラスを使いに出して尋ねさせるには、「今、天神の御子が、このところにお出ましになった。お前たちはお仕え申すか、どうだ?」このように訊いた。
これに対して兄のウカシは、唸りをあげて空を飛ぶ鏑矢を手にして、使いのヤタガラスを待ち受け、矢を放って追い返してしまった。
(2) 日本書紀のヤタガラス
皇軍は内つ国に赴こうとした。しかし、山の中はけわしくて行くべき道もなかった。進みも退きもならず、迷っているとき、夜また夢を見た。天照大御神が天皇に教えて言われるのに「吾は今、八咫烏を遣わすから、これを案内にせよ」と。はたして八咫烏が大空から飛び降ってきた。天皇が言われる。「この鳥のやってくることは、瑞夢に適っている。偉大なことだなあ。天照大神がわれわれの仕事を助けようとして下さる」と。このときに、大伴氏の先祖の日臣命は、大来目を率いて、大軍の監督者として、山を越え路をふみ分けて、烏の導きのままに、仰ぎ見ながら追いかけた。ついに宇陀の下県についた。・・・。
皇軍は大挙して磯城彦を攻めようとした。まず使者を送って兄磯城を呼んだ。兄磯城は答えなかった。さらに頭八咫烏を遣わして呼んだ。そのとき烏は軍営に行って鳴いていうのに「天神の子がお前を呼んでおられる。さあさあ」と。兄磯城は怒っていうのに「天神が来たと聞いていきどおえいるときに、なんで烏がこんなに悪く鳴くのか」と。そして弓を構えて射た。烏は逃げ去った。次いで弟磯城の家に行っき鳴いていうのに「天神の子がお前を呼んでいる。さあさあ」と。弟磯城はおじてかしこまっていうのに「手前は天神が来られたと聞いて、朝夕畏れかしこまっていました。烏よ、お前がこんなに鳴くのは良いことだ」と。そこで平らな皿八枚に、食べ物を盛ってもてなした。そして烏に導かれてやってきて申上げるのに「わが兄の兄磯城・・・」。
(3) 私見
奈良の宇陀に住んでおられる方には申し訳ないが、本当の宇陀は倉吉市高城地区であった。イワレヒコが内つ国(鳥取県中部)に赴くためヤタガラス(鴨建津之身)の案内で降り立った宇陀とは倉吉市高城地区であった。蒜山高原(高天原)から倉吉市高城地区に降りるには、鏡ヶ成からスタートしなければならない。鏡ヶ成は饒速日が降臨するに際し猿田彦が待っていたところである。イワレヒコの降臨にはヤタガラス(鴨建津之身)がついて案内した。
ヤタガラス(鴨建津之身)は古事記では宇陀の兄宇迦斯(エウカシ)・弟宇迦斯(オトウカシ)に使いを出された。日本書紀では磯城の兄磯城に遣わして呼び、弟磯城の家に行って鳴いた。古事記では「宇陀」に遣わされ、日本書紀では「磯城」に遣わされている。古事記と日本書紀では遣わされた場所が違うが、どちらにしても鳥取県中部に八咫烏は降り立った。日本書紀では頭八咫烏とあるので、頭がおり、何羽もいたということである。ヤタガラスは鴨建津之身であり、倉吉市関金町鴨ヶ丘に一族で住んでいたと思われる。鴨ヶ丘には山守鴨ヶ丘地蔵堂がある。北栄町北条島にいた猿田彦一族は登美の地にいた出雲神族(ナガスネヒコ一族)に囲まれていたと思われる。
2 饒速日(ウマシマジ)
(1)古事記の饒速日(ウマシマジ)
ここにニギハヤヒが陣中に参上して、天神の御子に次ぎのように言った。「天神の御子が、高天原からお降りになっておいでになると聞きましたので、私もあとを追って降ってまいりました。」こう言って、同じ天神の裔(子孫)であることを示す、証拠の宝物を献上して神武天皇に仕えた、とある。
(2)日本書紀の饒速日(ウマシマジ)
さて、長髄彦は使いを送って、天皇に言上し「昔、天神の御子が、天磐船に乗って天降られました。櫛玉饒速日(ニギハヤヒ)命といいます。この人が我が妹の三炊屋媛を娶とって子ができました。名を可美真手(ウマシマデ)命といいます。それで、手前は、饒速日命を君として仕えています。一体天神の子は二人おられるのですか。どうしてまた天神の子と名乗って、人の土地を奪おうとするのですか。手前が思うのにそれは偽物でしょう。」と。天皇が言われる。「天神の子は多くいる。お前が君とする人が、本当に天神の子ならば、必ず表があるだろう。それを示しなさい」と。長髄彦は、饒速日命の天の羽羽矢とかちゆきを天皇に示した。天皇はご覧になって「いつわりではない」といわれ、帰って所持の天の羽羽矢一本とかちゆきを長髄彦に示された。長髄彦はその天神の表を見て、ますます恐れ、畏まった。・・・。饒速日命は、もとより天神が深く心配されるのは、天孫のことだけであることを知っていた。かの長髄彦は、性質がねじけたところがあり、天神と人とは全く異なるのだということを教えても、分かりそうもないことを見てこれを殺害された。そして、その部下達を率いて帰順された。天皇は饒速日の命が天から降ったということは分かり、いま忠誠のこころを尽くしたので、これをほめて寵愛された。これが物部氏の先祖である、とある。
(3) 私見
日本書紀は長髄彦を殺害したのはニギハヤヒであるとする。先代旧事本紀は宇摩志麻遅とする。先代旧事本紀では、饒速日は降臨後、長髄彦の妹である三炊屋媛を娶って宇摩志麻遅ができる前に亡くなっており、追いかけてきて証拠の宝物を献上したのはウマシマジと思われる。ウマシマジは天皇に帰順したときにはすでに長髄彦(出雲神族の王)を殺害していたと思われる。そして、証拠の宝物を献上して神武天皇に帰順した。
蒜山高原(高天原)から倉吉市高城地区(宇陀)に下りてくるには蒜山高原の鏡ヶ成から降りるしかない。イワレヒコは高天原(蒜山高原)の鏡ヶ成から降りてきた。このとき、ウマシマジは何処にいたのだろうか。私は蒜山高原の西の鳥取県江府町江尾にいたのではないかと思う。江尾神社の主祭神は饒速日命(天照国照彦天火明櫛玉饒速日命)である。鳥取県神社誌831社の中で饒速日命を祀る神社は江尾神社だけである。祭神は饒速日だがその子のウマシマジも江府町江尾に住んでいたと思われる。ウマシマジは江府町江尾から鏡ヶ成に上がり鏡ヶ成から神武天皇を追って倉吉市高城地区(宇陀)に降りてきた。追って降りてきたのは、饒速日命ではなくその子のウマシマジである(先代旧事本記)。
古事記の文章は、ふつうに有りそうなことであるし、原古事記に書いてあったそのままだと思われる。問題は日本書紀である。初代の長髄彦ならばニギハヤヒの弟のニニギの存在は知っているはずである。もし、天神が二人いたことを知らないならばそれは2代目以降の長髄彦(出雲神族の王)と思われる。
ウマシマジは北栄町の土下山(鳥見の白庭山のちの天の香具山)で生まれて、イワレヒコが福山市にいた時は江府町江尾に住んでいたようである。ウマシマジは母方の長髄彦を殺して父方のイワレヒコに帰順した。ウマシマジの子孫は倉吉市大原にいて石上神宮を守り、物部氏と言われていた。大原には倉◯、倉▢姓が多い。
高天原とは蒜山高原のことである。神武天皇は内つ国(鳥取県中部)に帰るのに、岡山県の旭川を北上して蒜山高原に上がり、鏡ヶ成から倉吉市高城地区(宇陀)に降りてきた。鏡ヶ成は江府町江尾と近い。直線距離で11.5kmである。歩いても3時間余りで着く。江府町江尾にはウマシマジが住んでいたから、イワレヒコが高天原から降りて行ったことは誰かが伝えたと思われる。先代旧事本記はニギハヤヒではなくウマシマジとし、ウガヤフキアエズは彦火火出見のあだ名であったから、ウマシマジはイワレヒコの叔父くらいの年齢であったと思われる。ウマシマジは略奪集団の母方のナガスネヒコではなく人々の心をつかんだ父方のイワレヒコにつくことにした。
長髄彦は、青銅器文化の一族の長であった。青銅器文化の一族は気性の激しい大国主の兄の八十神であり、大国主が鳥取県東部の八上姫を娶るときには出雲からきた八十神(長髄彦一族)は鳥取県中部に住み着いていた。当初は天孫族と住み分けていたが、イツセとイワレヒコが九州に行って帰って来たときには、鳥取県中部の宇陀も忍坂邑も磯城も葛城も青銅器文化の一族に占領していた。長髄彦は中洲の豪雄(先代旧事本紀)と呼ばれていた。中洲とは笠沙之御前の柄のことであり、鳥取県中部にあった。北栄町土下集落は神武天皇の家来二人が香久山の土を下したところである。北栄町土下集落は中洲にある。
イワレヒコは「昔兄を殺した長髄彦」と言っている。イツセは長髄彦の矢で傷つき鳥取県智頭町で亡くなった。その後、イワレヒコは福山市で倭国を取り戻す機会をうかがっていた。そして、イワレヒコは内つ国(津のある鳥取県中部)に帰るのに、岡山県の旭川を北上して蒜山高原に上がり、ヤタガラス(鴨建津之身)の案内で鏡ヶ成から倉吉市高城地区(宇陀)に降りて行った。
3 参考
※ 内つ国 「つ」とは「津」であり奈良にはないが鳥取県中部にはあった。北栄町にあった葦原の中津を「御真津」といい、湯梨浜町にある東郷池を「師木津」と言っていた。
※ 宇陀 倉吉市高城地区であった。このことは、弥生時代後期の阿弥大寺遺跡や紀元前100年頃に始まる後中尾遺跡の存在より明らかである。
※ 忍坂邑 三朝町片柴であった。垂仁天皇川上宮から石上神宮に行くのに波関峠の坂を通らなければならないが、坂を下りた三朝町片柴集落が忍坂邑と思われる。
※ 兄磯城 忍坂から降りて行った先は湯梨浜町花見地区であった。兄磯城は湯梨浜町花見地区(羽衣石集落)にいた。
※ 墨坂 兄磯城を挟み撃ちにした墨坂は湯梨浜町羽衣石集落の坂と思われる。
※ 伊那佐山 北栄町の茶臼山と思われる。茶臼山は北条砂丘に囲まれていて砂でない(否砂)山である。
※ 香久山 北栄町の土下山と思われる。饒速日が降臨した登美の白庭山はこの山であった。饒速日の妻はナガスネヒコの妹であり、ナガスネヒコも麓の中洲にいた。天孫族の山になってからは、天の香久山と呼んだ。
※ 中洲 「中洲」とは笠沙之御前の柄の部分(伊那佐山から天香久山までの間の砂地)と思われる。天神川の度重なる洪水により東側から土砂が流れて中洲の跡もわからなくなっているが、中洲の上を土砂が流れた形跡は残っている。
※ 国見丘 北栄町の蜘ヶ家山と思われる。のちに葛城山と呼ばれるようになった。
※ 磐余邑 兄磯城の軍があふれていた磐余邑は北栄町土下山と蜘ヶ家山との間の米里集落と島集落であった。中央は汽水池になっていたから片方にしか居ることができなかった。今でも米里集落は西方と東方に分かれている。中央部分は池であった。
※ 畝傍山 倉吉市大谷の四王寺山であり、彦火火出見の宮があった。神武天皇の4兄弟はここで生まれた。ウガヤフキアエズは彦火火出見のあだ名であった。日向3代ではなく日向2代であった。豊玉姫も玉依姫も彦火火出見(ウガヤフキアエズ)の妻であった。
※ 吉野 奈良では宇陀に隣接して吉野があるから、倉吉市高城地区に隣接している北谷地区と思われる。北谷地区は古墳時代の遺跡が多い。長谷(泊瀬)の地名は北谷地区から出ている。細長い谷である。
※ 来目邑 倉吉市服部の北の丘陵まで久米ヶ原という。その南を流れる国府川を久米川と言っていた。久米川の南、上米積の南西に紀元前100年頃の後中尾遺跡があり、ここが来目邑であった。
※ 猛田 伯耆国河村郡竹田郷と思われる。弟ウカシは猛田(竹田)の県主に任命された。
※ 磯城(師木) 東郷池周辺であり兄磯城・弟磯城がいた。兄磯城・弟磯城は湯梨浜町花見地区にいたと思われる。弟磯城は磯城の県主に任命された。
※ 多芸志 湯梨浜町長瀬高浜である。当時は西に石山があり、石山が「船の舵の柄」に見えたと思われる。
※ 橿原 倉吉市大宮と思われる。この倉吉市大宮は四王寺山(畝傍山)から見れば、東南になる。また、歴代天皇の皇居の中で鳥取県中部(倭国)では一番山奥にある。
※ 耳 倉吉市関金町耳集落は倉吉市大宮(橿原宮)の川上4kmくらいのところにある。神武天皇の后の産屋があったところと思われる。子供に耳が付く。
※ 秋津洲 日本書紀・神武天皇・橿原即位・において「神武天皇の御巡幸があった。掖上の嗛間の丘に登られ国のかたちを望見していわれるのに、『なんと素晴らしい国を得たことだ。狭い国ではあるけれども、蜻蛉がトネメして(交尾して)いるように、山々が連なり囲んでいる国だなあ』と。これによって始めて秋津洲の名ができた」とある。倉吉市灘手神社の丘から見れば灘手の指にあたる数本の尾根が重なり、秋津がトナメをしているように見える。北栄町大島はこの秋津にあった洲(島)だから秋津洲と呼ばれた。