日本に滞在中、母校である筑波大学で「ブラジルにおける日本語教育」というテーマで講演を行った。
まずこの場をお借りして、僕の講演をしたいという要望を快諾してくださった学類長、大学時代にお世話になった先生方に感謝の意を述べたい。
また、同講演会でお手伝いしてくださった先生方、さらには、講演会を聞いてくれた後輩に当たる日本語・日本文化学類の学生方にも感謝したい。
本当にどうもありがとうございました。
僕が今回この講演を行った意図は、「ブラジルの日本語教育を日本人に知ってもらいたい」という想いと就職氷河期で苦しんでいる学生に「就職で挫折したとしても、外国でも何とかやれる」というメッセージを伝えたかったからだ。
その想いが伝わったかどうかは分からない。単なる自己満足に過ぎなかったのかもしれない。でも、人は自分がいいと思った事、やりたいと心から思った事を「やる」しかない。
人からやらされるのではなく、自分からやりたいことを「やる」。受け身的に人生を送るのではなく、主体的に動いて人生を楽しむ。
そういった行動をするには情熱が必要で、面倒くさくもある。でも、人は情熱がなくなったら、もう人の形をした「抜け殻」に過ぎなくなる。そんな風に「生きる」のは嫌だ。
ただ、日本にいたら、今回のような大胆な行動は取れなかったと思う。日本は「出る杭は打たれる」文化であり、「能ある鷹は爪隠す」必要がある。
僕は能もないのに出しゃばって出て行った。日本人としては本当に出過ぎた行動かなと反省している。でも、やらないで後悔する人生よりは、やって後悔した方が絶対にいいと思う。そうプラス思考になるしか方法はない。
さて、実際の講演の方だが、あまり盛り上げられなかったなあというのが率直な感想である。
大学生向けのあの懐かしい机がある教室に、学生が50名ほど、先生方が5、6名ほど出席して頂いたかと思うが、教室内がポカポカと温かかったこと、パワーポイントでの講演で教室を暗くしたこと、僕の声にメリハリがなかったことなどが眠気を誘ったのか、3分の1くらいの人が寝てしまっていた。
僕の講演の内容に一貫性がなく、全体として何が言いたいのか分からないのかも反省すべき大きなポイントかなと思っている。
ただ、僕が日本の大学生に講演して気づかされたのは大学生たちの無反応ぶりである。僕がする問いかけに答えようともしない。大半の学生は答えを知っており、それぞれが意見を持っているはずなのに、恥ずかしいから人前ではそれを発表しない。
僕自身が学生時代はそういう学生であったし、今もそうだと思うので、正面切って彼らを批判することはできない。「出る杭は打たれる」訳だから、目立てば他のクラスメートから嫌な奴と捉われかねない。日本には日本社会のルールがあり、そのルールに反した者は排除される。
その点、ブラジル人を相手にした講演・授業はやっていて楽しい。彼らは良くも悪くも大いに反応してくれるし、冗談にも笑ってくれるし、自分の意見もはっきり言う。
そして、日本の大学生にように寝ている人はまずいない。ブラジル人の場合、授業中に寝るくらいなら授業に出席しないほうがましという感じである。または、授業中に教室から出て行ってしまうことも多い。だから、教室にいる学生は一応授業を聞いている。
最後に、講演の時間が結構余ったので、司会の先生が質問はないか学生に聞いたところ、やはり何の反応もない。それで仕方がないので、司会の先生が「質問が出ないようなので、10分ほど時間を与えるので、紙に質問や感想を書いて、それに答えてもらう形にします」と助け船を出していただいた。
僕はそのやりとりを見て、思わず苦笑いをしてしまった。その方法が本当に日本的な授業運営だなと思ったからである。ブラジル人であれば、そんな面倒くさい事は絶対にやりたがらないのである。
国が違えば、文化も違う。面白いなあと思った。
とにかく本当に貴重な経験をさせて頂いた。どうもありがとうございました。










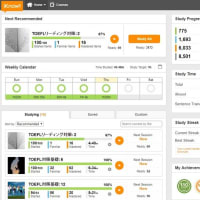



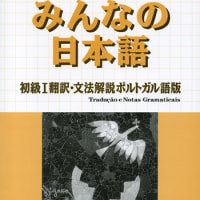
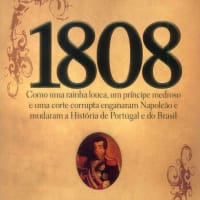
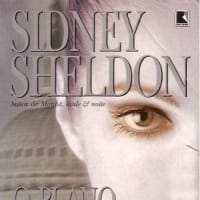



É a vida. Como você observa, nossos universitários conterrâneos se comportam de maneira que eles acham o melhor、somente dentro das limitações deles. Nada mais, nada menos.
A maioria deve ser filhos bem educados e bonzinhos. Mas, muito domésticos e sem ter idéia como são os outros mundos, eles ainda terão que aprender muito mais para entender corretamente o que você procurou transmitir para eles.