四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝第9回
平成26年8月25日 第五十二番 瀧雲山(りゅううんざん)太山寺を参詣しました
太山寺は 587年 九州 豊後の国 真野長者が 商いのため大阪に向かって航海中
高浜沖きで暴風雨に遭い 長者は日頃から信仰していた 十一面観音さまに 一心に祈願したところ
瀧雲山に観音さまの光明が輝き 海は穏やかになり 観音さまのお蔭と 豊後に帰って
木組をした建材を 瀧雲山の山頂に運び 一夜で建て上げ 一夜建てのお堂と呼ばれ
それが太山寺の始まりと言われています その後739年に聖武天皇
(在位724~749)の勅願で行基菩薩が十一面観音像を刻み 真野長者が
瀧雲山で見つけた小さな観音像を 胎内に納め 本尊にしたと伝えられていまず
弘法大師は824〜834年この地を訪れ 護摩供の修法をされ
それまでの法相宗から真言宗に改宗し 霊場に定められています

太山寺境内図

標高200mの経ヶ森の山腹にある 大山寺
バスから下りて 上り坂の参道がつづきます

参道の左上段に 一畑薬師堂
目の病気に 霊験があると言われ 自分の年の数だけ「目」「め」「メ」の文字
または目の絵を書いて供え 薬師如来の ご真言 (おんころころ せんだり
まとうぎ そわか)を唱えると ご利益があるそうです

参道右に 中門 奥に 納経所 庫裏 客殿があります

上り坂の正面に 手水場


手水場の周辺にはi色々な石仏が あります 左に十三仏と 大日如来像
「一字一石」黄色の篭の中の小石一つにお経の一文字を書いて納めると 願い事が叶うそうです


修行大師像 子育て地蔵


水子地蔵 観音像

赤帽子は延命地蔵 その隣?愛嬌のあるお顔しているので拡大

右に折れて石段を40数段上ると 三の門


四天王が安置され 多聞天 持国天

境内から 三の門
三の門をくぐると正面に本堂、左手上に 大師堂が見えます
二の門 仁王門は 撮れていませんが 鎌倉時代の特徴の 入母屋造り
単層の八脚門で 1485年の建築 国の重要文化財です

厄除け大師堂 休息所にもなっています

鐘楼
梵鐘は1383年に鍛造の 県の有形文化財です

護摩堂と稲荷堂 前に修行大師像
近くに聖徳太子堂の 法隆寺と同じ夢殿 があるはずですが・・・
(先達さんも?時間がなく 見失い!)
毎年1月15日 太師祭には 多くの参拝者が しゃもじをもって訪れ
幸福をすくいあげる お祀りがあるそうです

三の門をくぐると 正面に壮大な本堂の 屋根が目を見張ります
長者建立から三代目の 重厚風格のある本堂は 1305年の建築
松山城主 河野家が寄進されたもので 国宝に指定されています
ご本尊は十一面観世音菩薩
喜怒哀楽のお顔をもち 全ての人々の悩みを救って下さり 災難除けの仏さまです

本堂の左上壇に 大師堂

大師堂の右に 長者堂
太山寺 創建者と言われる真野長者(九州 豊後の人)が祀られ
「長者}の号は天皇からの贈り名だそうです

大師堂の 右に この寺の三重塔の礎石があり タワシでこすると
大腸 痔の病気に霊験があるそうです


礎石の奥に左の石像は? 十一面漢世音菩薩 つぎのお堂は?
つぎ53番札所 円明寺まで 約2.5km バスで約10分です
おしまい 















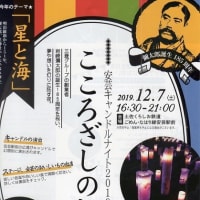




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます