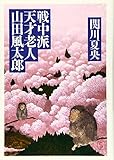【追悼】さいとう・たかをさん「私の頭の中にだけ眠る『最終回のアイデア』」最後に語った“ゴルゴのプロ意識”
9/29(水) 18:12配信
44
さいとう・たかをさん ©文藝春秋
日本の漫画界を牽引し、7月には『ゴルゴ13』が世界最長の漫画シリーズとしてギネス記録に登録された、さいとう・たかをさんが9月24日、膵臓がんのため84歳で亡くなりました。ギネス登録直後に行われたさいとうさん本人へのインタビュー記事を公開します。(初出:「文藝春秋」2021年9月号、「文藝春秋digital」8月27日公開。記事中の肩書・年齢等は掲載時のまま) 【画像】『ゴルゴ13』を制作する若き日のさいとう・たかをさん ◆
「俺は俺の考えで動く」
世の中に世界最長の漫画シリーズ記録があることは知っていましたが、この7月に『ゴルゴ13』201巻が発売されると、ギネスレコードに認定されて取材依頼が殺到。それで初めて、大した記録なのだなと実感しました。 連載をはじめたのは1968年ですから、もう半世紀以上も経ちます。「ゴルゴ」はなぜ、こんなにも長く親しまれているのか、とよう聞かれます。「ゴルゴ」は約束をしたことは必ず守り、自分の仕事に対しては、全て自身が責任を負い、筋を通す生き方を貫いている。こういうタイプは、今の日本には非常に少ない。だからこそ、日本人は「ゴルゴ」に惹かれるのかもしれません。 「ゴルゴ」は「俺は俺の考えで動く」、と自分の価値観で行動し、周囲にも左右されない。ただし、つねに周りの意見には耳を傾けており、情報を手に入れることは決して怠らない。そのどちらか一方だけでは、プロとは言えません。
当初から考えている「最終回のアイデア」
でも、正直に言ってしまえば、「ゴルゴ」が201巻まで続くことになるとは、私も予想していませんでした。最初は、10話限りで終えるつもりでしたから。そもそも漫画の連載なんて、いつ終わるかわかりません。漫画家とは、いわば、いまにも落ちそうな腐った橋の上を猛スピードで走り抜けるような仕事なのです。連載がいつ終わってもいいように、当初から最終回のアイデアも考えてありました。以来、最終回のアイデアは、ずっと私の頭の中にだけ眠っているんです。 よく何十年も同じことしていて飽きませんか、なんて聞かれることもありますが、漫画家としての「長寿」の秘訣をあえて語ると、私の場合、この世界に入ったときから、漫画を描くことは仕事だという意識をもっていました。農家が「米を作るのに飽きた」「麦を作るのに飽きた」と言ったらどうなるでしょうか。私はそんな気持ちで、生業として劇画を描き続けてきたのです。これは、「ゴルゴ」のキャラクターにも通じる、私なりのプロ意識なのです。 プロフェッショナルに、もっとも必要なことは「約束を守ること」です。つまり、連載で言えば、締め切りは必ず守る。かつては漫画雑誌自体も少なかったこともあり、競争も激しく、いつ連載が終わるかもわからない状況でしたから、休んだり、締め切りを守らなかったりすることはありえなかった。 若い頃、作家仲間で集まっているときに、「売れっ子が休むことをまるでステータスみたいに言ってるけど、職業としてやる限り、締め切りを守るのは最低限のルールだぞ。他の仕事だったら違約金をとられるぞ」と偉そうなことを言ったことがあるんです。本心ではありましたけど、おかげで休めんようになりました(笑)。 忙しい時期は、月600枚以上、原稿を描いていることもありましたね。28歳で網膜剥離になり、43歳で糖尿病になりまして、そのときは流石にピンチでした。
さいとうさんが見た『鬼滅の刃』ブーム
これだけ長く仕事を続けていると、「時代の変化をよく乗り越えてきましたね」と言われます。でも、私が60年以上、仕事を続けてきてわかったことは、本質、やるべきことは不変だということです。それは劇画の強みや特徴を理解した上で、劇画にしかできないことを考えるということです。 漫画『鬼滅の刃』が今、人気でアニメ化されていますが、作家は劇画にしかできないこと、アニメにしかできないこと、実写映画にしかできないことを、それぞれ追求するだけです。私がかつて、この世界に飛び込もうと思ったとき、ペンと紙さえあれば映画みたいな作品が作れると考えていたのですが、その思いは今でも変わりません。映画みたいに多くの時間、お金を使わなくてもそれに匹敵する、映画を超える娯楽を生むことができると思っています。 でも最近は『ゴルゴ13』が私の作品であるという意識が薄くなってきているんです。私の作品であると同時に、読者のものでもある。普段から、読者に受け入れられるであろうことしか考えてこなかったですから、いつも待ち続けてくれている彼らあっての『ゴルゴ13』だと思っています。だから読者から求められる限り、私の身体が動く限り、描き続けたいと思います。97歳までやった、「伝説の劇画師」植木金矢先生がいますから。私なんか、まだまだひよっこです。
さいとう・たかを氏「私にアシスタントはいない」。『ゴルゴ13』連載継続を可能にしたプロダクション方式
加山竜司漫画ジャーナリスト9/30(木) 11:16
外務省の「中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」にも協力したさいとう氏。(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)
『ゴルゴ13』などの作品で知られる劇画作家、さいとう・たかを氏が膵臓がんのため9月24日に亡くなったことが発表された。
『ゴルゴ13』の掲載誌「ビッグコミック」(小学館)編集部は「今後は、さいとう・たかを氏のご遺志を継いださいとう・プロダクションが作画を手がけ、加えて脚本スタッフと我々ビッグコミック編集部とで力を合わせ『ゴルゴ13』の連載を継続していく所存です」と、作品継続の意向をあわせて伝えた。
アニメの世界では『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』、『ドラえもん』のように、原作にはないオリジナルストーリーを脚本家が創作し、原作者の死後も作品が継続されるケースはある。あるいはアメリカン・コミックスだと、DCコミックスやマーベルコミックスに代表されるように、作者を変えながら連載を続けてきた例も多い。
それと同様に、『ゴルゴ13』もさいとう・プロダクションによって続編が描かれ続けていくわけである。
さいとう氏のプロダクション方式に寄せた情熱
これが可能なのは、さいとう氏が早期から分業・プロダクション方式での作品制作を実施してきたからにほかならない。
さいとう氏が最期まで連載中だった『ゴルゴ13』と『鬼平犯科帳』(リイド社「コミック乱」)は、いずれも雑誌掲載時には最後のコマにスタッフの名前がクレジットされており、携わったスタッフの名前が確認できる(『ゴルゴ13』はリイド社刊行の文庫版の巻末にも収録されている)。
『ゴルゴ13』の「脚本」を担当してきたスタッフには、マンガ原作者の小池一夫(故人)や工藤かずや、さらには外浦吾郎(吾朗)などがいる。外浦吾郎とは、小説『虹の谷の五月』で直木賞を受賞した船戸与一の変名である。
あるいは1980年代中頃の「担当編集」を見ると、長崎尚志の名前を見つけることができる。長崎は小学館を退社したのち、マンガ原作者・プロデューサーとして『PLUTO』や『BILLY BAT』をはじめとする浦沢直樹作品の制作に携わったり、数多くのマンガ原作を手掛けたりする。フリー転身後、今度は脚本担当として『ゴルゴ13』に関わるという、“凱旋帰国”を果たしている(「429話 真のベルリン市民」「555話 ロンメル将軍の財宝」)。
私は2018年にさいとう氏にインタビューをする機会に恵まれた際に、プロダクション制を導入した意図を聞いた。なお、さいとう・プロダクションの設立は1960(昭和35)年である。
――さいとう先生は早くからプロダクション制を導入しました。さいとう みんなそれぞれ自分に足りないところで悩んでいるな、と思ったんです。だって、絵を描く才能とドラマをつくる才能は別物ですから。もちろん天才は出てきますよ。手塚先生(※注:手塚治虫)とか章太郎(※注:石ノ森章太郎)みたいな。でも、そんな人ばかりじゃないです。それぞれの才能を持ち寄れば、もっと完成度の高い作品ができるはずだと考えていたので、最初から組織づくりについては考えていました。ただ、現在のような“さいとう・たかをのためのさいとう・プロ”にするとは考えていなかったですけど。――と言いますと?さいとう 核をこしらえて、そのまわりにスタッフを置く……。核っちゅうのは、映画でいえば監督ですわ。そしてゴルゴのようなキャラクターができた時には、5つぐらいのグループで『ゴルゴ13』をつくれば、もっと読者にアピールできたと思うし、楽しいと思うんですよ。――その『ゴルゴ13』を例にすれば、雑誌掲載時の最後のコマには、映画のエンドロールのように、スタッフのクレジットが入ります。さいとう ええ、私の作品にアシスタントはいません。すべて“スタッフ”ですから。編集者も、プロデューサーだと考えてます。(宝島社『生誕80周年記念読本 完全解析! 石ノ森章太郎』より)
この言葉からも、さいとう氏がアメコミのようなプロダクション方式を志向していたことが読み取れるだろう。
さいとう・プロダクションによる『ゴルゴ13』の連載継続は、決して「作者の死」による急場しのぎ的な施策ではなく、あらかじめ作者本人によってデザインされた作品制作体制であるという点は特筆に値する。
さいとう氏が情熱を傾けたプロダクション方式。今後のさいとう・プロダクション制作による『ゴルゴ13』にも注目していきたい。
『ゴルゴ13』で語られた「ゴルゴに仕事を依頼する方法」が感動するほどオモシロイ!
柳田理科雄空想科学研究所主任研究員9/30
- 柳田理科雄
空想科学研究所主任研究員
イラスト/近藤ゆたか
『ゴルゴ13』や『無用の介』や『超人バロム・1』などを描かれたさいとう・たかを先生が亡くなられた……! 貸本マンガ時代から活躍され、「劇画」というスタイルを守り抜かれた功績は計り知れない。筆者も本当に長く楽しませていただいた。心からご冥福をお祈りいたします。
それにしても、さいとう先生の代表作『ゴルゴ13』は息が長い。雑誌の連載開始が1968年。主人公のデューク東郷は、半世紀以上にわたって「狙撃手」という危険な仕事を続け、世界の政治経済に大きな影響を与え続けてきたわけだ。恐るべきヒトですなあ。
彼が驚異的な実績を残せるのは、日頃からモノスゴク慎重に行動しているからだ。それゆえに決まりごとが多く、たとえば、ゴルゴ13の背後に立ってはならないし(立つと反射的に殴られる!)、右手をポケットに入れてはならないし(銃を取り出すと思われて、撃たれる!)、依頼の内容に嘘や隠し事があってはならない(あったら殺される!)。
他にも、ゴルゴ13は握手に応じないし、相手より先に車に乗らないし、出された飲食物に手をつけないし、椅子に座らない。まことにめんどくさそうな人である。
また、この人はびっくりするほど無口だ。
たとえば「天使の一滴」という全41ページのエピソードにおいて、ゴルゴ13が口にしたセリフは次のとおり(すべて、一般人を装ってバーテンに言ったもの)。
「いや……、人が殺されたようだな……?」「店の客か?」「スコッチをダブルで…… もう一杯もらおう……」「釣りはいい」
以上が、この作品におけるゴルゴのセリフの全部なのだ! まるで、監督の温情でセリフをもらった端役の俳優さんのようである。
◆46人に1人がゴルゴに依頼!
かなり個性的なゴルゴ13だが、引き受けた仕事は99%以上の確率で成功させるので、依頼はめちゃくちゃ多いらしい。
「デリート・G Gの消滅」というエピソードによれば、依頼が来るペースは「1秒に1件」だという!
そのエピソードのなかで、ゴルゴへの依頼について情報交換しているのは、テッドとマシューという2人のCIA職員。よって、かなり信用できる情報だろう。
テッドは「ここ五年に絞っても、平均年間一〇〇件以上の暗殺や、世間では事故と思われている死亡事件の裏に、Gが関わっている可能性が濃厚だ!」と言い、「いや、俺の勘では百%間違いない!」と断言する。
なんとゴルゴの暗殺件数は、年間100件以上!
これに対してマシューは「平均毎秒約一件の依頼文らしき文字列が、世界の都市のどこかで現れている」と、自分が調べた極秘の情報を明かす。
テッドは驚いて「ざっと一日八万六千件の依頼が舞い込むってことか?」。
これはすごい。1日は8万6400秒だから、1秒に1件だと確かに「1日8万6千件」になる。
ということは、1年365日では3153万6千人。テッドの言う「ここ5年」に限っても、1億5768万人が、ゴルゴ13に仕事を依頼した計算になる。
地球の人口は73億人(2017年)だから、46人に1人! それほど多くの人が、誰かに殺意を抱いたり、抱かれたりしてきたということか。うむむ。人間の信頼はどこへ……。
こんなにたくさんの依頼が来て、ゴルゴ13はどうするのかと思っていたら、マシューがこう続けた。「そのうち三分の二が、やり方がまずく、奴に届いていない」。
なるほど、1日8万6400件の依頼のうち、ゴルゴ13に届くのは3分の1。だいぶ減ったが、それでも1日に2万8800件である。
さらにマシューは「残りの九割以上は、奴自身の厳しい依頼人調査ではねられている」。えっ、この2万8800件については、ゴルゴ13が依頼人について調べている!? 3秒に1件ずつという計算になるが……!?
そのうえゴルゴ13は、引き受ける仕事を選択しなければならない。2万2800件のうち、1割が依頼人調査をパスするということは、1日2880件、1年間で105万1200件。このなかから1年に100件だから、1万512件に1件という狭き門である。
これをどうやって選ぶのか。マシューは「その基準が、よくわからない……」と頭を抱えていたが、ゴルゴ13はメチャクチャ苦労をしていると思う。筆者だったら、選ぶだけで全時間が費やされてしまい、暗殺などしている時間はありません。
◆ゴルゴ13への依頼方法
ところで、依頼人はゴルゴ13にどうやって依頼するのだろうか。
さまざまなアプローチ手段が物語のなかで紹介されているが、有名なものの一つに、アメリカ連邦刑務所に服役しているマーカス・モンゴメリーに仲介してもらう方法がある。それは、こんな手順だ。
1)依頼人は、マーカスに手紙を出す
2)マーカスは、ラジオ番組「夕べの祈り」に『讃美歌13番』をリクエストする
3)それを聞いたゴルゴ13は、新聞「ニューヨーク・タイムズ」に「13年式G型トラクター売りたし」という広告と連絡先を載せる
4)広告を見た依頼人はそこへ連絡し、自分の連絡先を伝える
5)そこに、ゴルゴ13から連絡が入る
ヒジョーに手間がかかる! 1日2万2800件なんて絶対ムリ! だいいち「夕べの祈り」だって『讃美歌13番』ばかり流すわけにいかないだろう。「次のリクエストは『讃美歌13番』です。(讃美歌を流して)次のリクエストも『讃美歌13番』です。(讃美歌を流して)次のリクエストも『讃美歌13番』です……」などということになって、もうメチャメチャ怪しまれる。
謎に満ちたゴルゴ13への依頼と選択の方法だが、ゴルゴ13がそこに莫大な手間をかけているのは間違いないだろう。
最終選考に残った2880人に毎日会って仕事の内容など聞いているヒマはないから、徹底的な調査をして、引き受けることをほぼ決めてから依頼者に会うに違いない。だからこそ実際に会ったときは、数語のやり取りで「わかった、引き受けよう」となるのだ。
――半世紀以上にわたって劇画ジャンルの先頭を走り続けただけあって、ゴルゴ13は本当に魅力的なキャラだ。さいとう先生が亡くなっても連載は続くというから、これからも彼の活躍を楽しませてもらいたい。
さいとう先生、長いあいだ、本当にありがとうございました。
- 『「名探偵」に名前はいらない ニューハードボイルド原作大全集』東京三世社 1981
- 改訂版 『「名探偵」に名前はいらない』講談社 1988→ 講談社文庫 1991
- 『ソウルの練習問題 異文化への透視ノート』情報センター出版局 1984→ 新潮文庫 1988→ 集英社文庫 2005
- 『海峡を越えたホームラン 祖国という名の異文化』双葉社 1984→ 朝日文庫 1988→ 双葉文庫 1997
- 『貧民夜想会』双葉社 1986→ 文春文庫 1990→ 改題『かもめホテルでまず一服』双葉文庫 1997
『東京からきたナグネ 韓国的80年代誌』筑摩書房 1987→ ちくま文庫 1988
- 『水のように笑う』双葉社 1987→ 新潮文庫 1990
- 『水の中の八月』講談社 1989→ 講談社文庫 1996
- 『森に降る雨 Rain in April』双葉社 1989→ 文春文庫 1992
- 『七つの海で泳ぎたい。フォト・ルポ』講談社文庫 1990
- 『知識的大衆諸君、これもマンガだ』文藝春秋 1991→ 文春文庫 1996
- 『よい病院とはなにか 病むことと老いること ドキュメント』小学館 1992→ 講談社文庫 1995
- 『家はあれども帰るを得ず』文藝春秋 1992→ 文春文庫 1998
- 『退屈な迷宮 「北朝鮮」とは何だったのか』新潮社 1992→ 新潮文庫 1994
- 増補版 『「北朝鮮」とは何だったのか 退屈な迷宮』 KKベストセラーズ〈ワニ文庫〉 2003
- 『「ただの人」の人生』文藝春秋 1993→ 文春文庫 1997
- 『砂のように眠る むかし「戦後」という時代があった』新潮社 1993→ 新潮文庫 1997
- 『戦中派天才老人・山田風太郎』マガジンハウス 1995→ ちくま文庫 1998
- 『二葉亭四迷の明治四十一年』文藝春秋 1996→ 文春文庫 2003
- 『中年シングル生活』講談社 1997→ 講談社文庫 2001
- 『昭和時代回想』日本放送出版教会 1999→ 集英社文庫 2002
- 『豪雨の前兆』文藝春秋 1999→ 文春文庫 2004
- 『豪雨の前兆』』文藝春秋 2000→ 文春文庫 2003
- 『やむにやまれず』講談社 2001→ 講談社文庫 2004
- 『本よみの虫干し-日本の近代文学再読』岩波新書 2001
- 『石ころだって役に立つ-「本」と「物語」に関する記憶の「物語」』集英社 2002→ 集英社文庫 2005
- 『昭和が明るかった頃』文藝春秋 2002→ 文春文庫 2004
- 『女優男優』双葉社 2003。映画エッセイ
- 『白樺たちの大正』文藝春秋 2003→ 文春文庫 2005
- 『「世界」とはいやなものである』日本放送出版協会(現:NHK出版) 2003→ 集英社文庫 2006
- 『現代短歌 そのこころみ』日本放送出版協会 2004→ 集英社文庫 2008
- 『おじさんはなぜ時代小説が好きか』岩波書店 2006→ 集英社文庫 2010
- 『「坂の上の雲」と日本人』文藝春秋 2006→ 文春文庫 2009
- 『汽車旅放浪記』新潮社 2006→ 新潮文庫 2009→ 中公文庫 2016
- 『女流 林芙美子と有吉佐和子』集英社 2006→ 集英社文庫 2009
- 『家族の昭和』新潮社 2008→ 新潮文庫 2010
- 『寝台急行「昭和」行』日本放送出版協会 2009→ 中公文庫 2015
- 『新潮文庫 20世紀の100冊』新潮新書 2009
- 『子規、最後の八年』講談社 2011→ 講談社文庫 2015
- 『「解説」する文学』岩波書店 2011
- 『「一九〇五年」の彼ら-「現代」の発端を生きた十二人の文学者』NHK出版新書 2012
- 『東と西-横光利一の旅愁』講談社 2012
- 『やむを得ず早起き』小学館 2012
- 『昭和三十年代 演習』岩波書店 2013
- 『夏目さんちの黒いネコ やむを得ず早起き②』小学館 2013
- 『文学は、たとえばこう読む 「解説」する文学Ⅱ』岩波書店 2014
- 『人間晩年図巻 1990-94年』岩波書店 2016
- 『人間晩年図巻 1995-99年』岩波書店 2016
- 『人間晩年図巻 2000-11年』岩波書店 全3巻 2021.10-12












![文藝春秋2021年9月号[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NBlO0to+L._SL160_.jpg)