
「質問は、相手を強制的に特定の方向で考えさせる力を持っています。」谷原誠著『「いい質問」が人を動かす』より

社員がなかなか定着しない、育たないという職場において、その原因の一つは間違った命令と質問力の不足でないか?と私は考えています。
『質問の効力』シリーズ 第3回目は「自尊心の扱い方」です。
規模の大小を問わず、組織で若手の教育を担当する立場になった場合、かつて自分が教育された時の経験が強く影響すると言われています。(親が子を育てるのと似ています)
本人が意識しなくても、かつて優しく丁寧に教えてもらった経験のある人は、同じように丁寧に教育しようとするし、厳しい指導を受けた経験がある人は、やはり厳しく当たろうとします。
前回は、「部下の、失敗から学ぶ場面」を題材にしましたが、そういった何か問題が起きた場面こそ、かつて自分が”された様に”接していませんか?
社員教育に欠かせない”自尊心”という観点。

社員教育の場面では、優しさか、厳しさか、その両方かという手法選択論になりがちですが、今回は「相手の自尊心をどう扱うか」という観点について考えてみました。
そして、”自尊心”を「自分を大切にする気持ち」という広義の捉え方で進めます。
人は誰しも、自尊心を損ねることにとても不快感を覚えます。
例えば、上司に「覚えが悪いな~」「だらしないな~」「格好悪いな~」などと言われると、よほどの信頼関係がない限り、イラッとくるはずです。少なくとも嬉しいとは思わないでしょう。
しかも、それが自分でも気にしていることなら、尚更不愉快になるはずです。
そして、個人差はあるものの、大きく自尊心を傷つけられると、心が痛むだけでなく、体調不良にもなり、さらにはトラウマになったり、うつ病のきっかけになったりします。
では、逆に自尊心を満たすようなことなら、どうでしょうか。
人は、自尊心を満たすことなら、何度でもやろうとします。
例えば、上司に「君のお陰で助かったよ、ありがとう!」などと言われると、あまり好きではない上司でも、またサポートしてあげようと思うはずです。少なくとも不快には思わないでしょう。
さらに、それが尊敬する上司なら、より一層、また役に立ちたいという気持ちになるはずです。
そして、個人差はあるものの、自尊心を満たす経験は自信となり、もっと上手くなりたいという気持ちを高めたり、新たな挑戦へのきっかけになったりします。
この様に、人の自尊心を軸に社員教育を考えると、優しくとか厳しくという手法の前に、いかに相手の自尊心を損ねることなく、どう満たすことができるかの方が、よほど大切ではないでしょうか。
前々回の「人を動かす質問」の中で、「人は、命令よりも自分で決めた事に喜んで従う」と紹介しましたが、これも自尊心を損ねることがないからだと説明できます。
人は誰しも、自分の自尊心に忠実に反応します。だからこそ、相手の自尊心を理解し、それをどう扱うことが出来るかが、優れた上司か否かの分かれ目という訳です。
痛い目に遭わせるだけでは逆効果
前回の実例でもそうですが、新入社員はよく失敗をします。初めての仕事なら当然です。
しかし、若いうちに仕事の厳しさを確り理解させ、ミスを最小限で抑えるためには、失敗を教訓にしてもらうという名目で、「痛い目に遭わせる」という旧戦法が、未だに多くの職場で用いられているようです。
例えば、皆の前で恥をかかせる、大きな声で怒鳴る、追い詰める質問を繰り返す、罰と称して無益な仕事を与えるなどの行為を伴う指導法です。
この手法は、確かに”見た目”には効果絶大です。目の前の部下が落ち込むからです。
しかし、肝心の”教訓になる”という点では、まったく効果がないのをご存知ですか?
効果どころか、実はほとんどの場合が負のスパイラルの入り口にしかなりません。
この手の指導法は、部下の自尊心を大きく損ねることになり、上司とよほど良好な関係性を築いていても、程度を超えてしまうと、その良好さが逆に危険度を高めます。
なぜなら、信頼関係は互いの自尊心を尊重することから生まれるからです。理由や目的はどうであれ、自尊心を傷つけられた相手を、人は信頼しません。
さらに、人は本能的に自尊心が損なわれた経験を遠ざけようとします。
思い出したくない事、なかった事にして、心の奥にしまい込むのです。なので、本来考えるべき「失敗を引き起こした原因や対策」にまで頭が回らず、ただ嫌な思いをしたという嫌悪感だけが鮮明に心に刻まれ、行動変容にまで至らないので、またぞろ同じような失敗を繰り返すことになります。
当然ながら、同じようなミスを繰り返すことで、上司の指導の厳しさも増すことはご想像の通りです。本来、部下の成長を促すはずの上司が、「こんな目に遭っても反省がない、分からないのは本人の気持ちの問題だ。」などと思うようになり、当の部下は、「あんな思いをするくらいなら、もうこの仕事はやりたくない、自分には向いていない。」と思うようになり、まさに負のスパイラルに陥てゆくのです。
それでも、この戦法が未だに無くならないのはなぜでしょうか?
確かに潰れる人が出てくる一方で、それを機に良い方向に変わる人もいるのはなぜでしょうか?
結果オーライの社員教育になっていませんか?
私も含めて、かつて痛い目に遭わされたという方は大勢いると思います。そして、あの時、あんな痛い思いをしたから成長できたと思っている方も大勢いるでしょう。
しかしそれは、痛い目に遭わせるという手法が功を奏したのではなく、その本人が自身の自尊心を大切に扱ったに過ぎず、言い換えれば、当事者の”負けん気”や”ひたむきさ”に頼っているだけです。
そして、痛い目が良い経験になったと思っている人は、その上司や周囲の人が、痛い目に遭った後に”適切な”フォローをしてくれたり、家族や友人が愚痴を聴いてくれたりと、様々な支えがあったからです。
どんな状況であれ、相手の自尊心を損ねるような方法だけでは、成長どころか将来有益となる能力さえも摘んでしまうことになります。そもそも、若い社員を育てる上で大切なのは、失敗を成長に変える術を教えることにあるはずです。
しかし、未だに多くの人が、痛い目という”負のエネルギー”を与えなければ、人の成長はないと勘違いしています。人は、痛い目に遭わなくとも、負けん気やひたむきさを発揮できます。それどころか、自尊心を満たすために発揮する力の方が、何十倍も効果を出します。
社員教育に本当に必要のは、自尊心を高める”正のエネルギー”を与えることです。
今現在、部下を指導する立場の貴方は、かつてどの様な社員教育を受け、どのような指導をされていますか?
もしも結果オーライの社員教育になっていると思ったら、直ぐに改めることをお勧めします。
なぜなら、部下を自分との相性で判断してしまうことになるからです。
次回は、自尊心を高めるきっかけとなる「自尊心をくすぐる質問法」です。











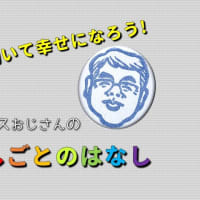

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます